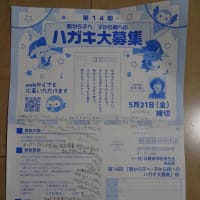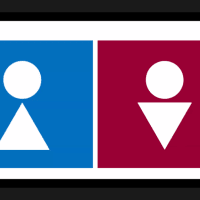さらがお風呂に入る前に、話してたこと。
最近、中休み(私の時代で言う20分休み)に、クラスでドッジボールをしようということになってるそう。さらの学校は、当番や係とは別に、○○会社という役割があって、外遊び会社が決めたそう。
さらはドッジボールには行きたくない。
ある日、さらと親友のあおりんがドッジに行ってなくて、休み時間後、「何で来なかったん?」と聞かれたそう。さらは、決められたことは断れなさそうなのに意外。
その時は、その前の授業で黒板で描き写してなかった絵をノートに描いたり、終わってからは折り紙をしてたらしい。流れで行かなかったということなら、この子ならあり得る。でも、終わってもすぐ行かずに折り紙をしてたというのは、自分のしたいことをする意思の表れか。
あおりんに、「行かなまた何か言われるで」と椅子を引っ張られたこともあるらしい。でも、さらは椅子を押さえて、「何か言われたら、こう言ったらいい」と動かなかったらしい。そこは意思が強い。
どう言ったかと言うと、「他の人だってイヤって言ってた人いたから、その人は外遊び会社に連れ去られたっていうことになると思う」「20分でも自分の時間があるのに、それをムダにしたくない」
私なら、行きたくなくても、行ってる子が多かったら、集団の力に流されそう。他の行きたくない子だって、最終的に行く方を選んでるんだから、多数決でいうと数の力では負けるし。
ドッジに行きたくなくて、「お腹痛くなって来た」という子もいたそう。
さらは前にも、「お母さん、多数決が正しいとは限らないよ」って言ってた。
そうだ、それを4年生の時によく言った。
多数決に流されるから、戦争とかに発展しても、誰も反対しないんだ。
お友達は、さらの意見は分かるけど、「そうだけど~」とさらの椅子を引っ張ってたけど、さらは椅子をずーっと押さえてたらしい。
さらって、言われたら、相手の言う通りにしちゃうかな、人に何か言ったり(主張とかコミュニケーションとか)する方じゃないから、我慢したりしてないかなと思ってた。けど、イヤなことはイヤというのははっきり言ってる。言うというより、態度で示してる。それを他の人にまで主張して、自分の考えを広めるとかはないけど、自分の意思は静かに体現している。
そう言えば、先日さらの行ってた幼稚園に近所のイベントのチラシを持ってって、話してた時、さらがクラスで発表とかは相変わらずしないんですけどねって話をしたら、養護の先生が「でも、自分の大切なところは言いますよ」と言ってくれた。先生、よく見ててくれてたんだな。
さらに、人に何かをしないと言う時に、「~だからイヤ」って言ったら、相手は更に正当な理由をつけて言い返して来るから、何も言わんとただそうする方がいいでと言うと、「さらちゃん、そうしてる」と言う。
私は、何かする・しないに対して、反対されそうなとき、正当な理由を言わないと、相手が納得しないと思って、主張するんだけど、主張すると相手は自分なりの正当な理由を言って来る。世の中、口が立つ方が勝ちみたいなところがあって、口が立つ人が相手だと言いくるめられてしまう。
(これが、大人と子どもなら、大人の言う事がもっともらしく聞こえて、子が折れる事もある。)
これを言ったら納得してくれると思っても、反対する人は何があっても反対して来るのであって、そうなると戦いになる。それを私は今まで気付かなかった。気付かず、どう言ったら、納得してくれるか考えてた。
最近、Mちゃんという昔同じ講座に参加した同期の子と話してて、そういう時、「議論はしない。疲れるから」と教えてくれた。「したくない事はただしない。否定を頑張るより、自分のできる事をする」と。
そういう戦い方があるのか、と思った。でも、私も元々戦うつもりはないのだ。分かってくれないから、言い合って戦いになる。これを理解してもらうとなる。そうなると、だんだん目的が変わって来る。本来自分がしたい事ができてない。
そういう方法があるんだ。
やりたくないことはやらない。
やりたいことをやる。
彼女曰く、「やらない=他にやりたいことがある」ということ。
私が、自分の人生がしんどいと思った時、心理学を学んだりして40過ぎてようやく気付いたのが、私の人生の課題は「イヤなことを言う」ということ。それをさらは早い段階でクリアしてる。
というか、イヤなことでも言ったらいけないと変なものをくっつけてるのは大人。大人の役目は、イヤなことを言う=ワガママみたいな先入観を植え付けないことだと思う。
さらは主張しないと思ってたけど、肝心なところ・自分の大事な所は守ってる。口で言わなくても、体現してる。意思がしっかりしてる。芯がある。このままでいってほしい。
ファンになりそう。同学年やったら、ついてくわ。
親として、して来たこととして、良かったと思うのは、子どもの意思・思いを否定しないこと。
子どものことで、こんなんでいいのかな(例えば、友達が少ないけど、いいのかな?)とかあっても、言わない。
子どもに、「それって悪い事?」って先入観を植え付けてしまうから。
親は不安を口にしたら楽になるかもしれないけど、子は呪いをかけられることもある。