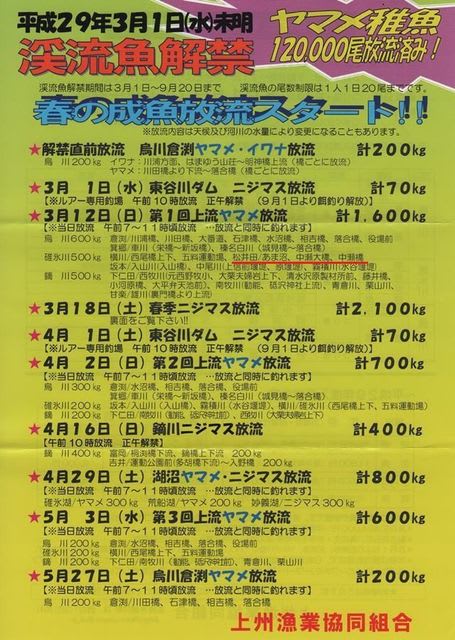あれから6年・・・大きな揺れで勤め先の被害状況を調査し夜遅く家へ帰ると停電で真っ暗だった。そしてガソリンが買えなくなって仕事に通うのも心配な状況の中で彼方此方の放射能調査などを行っていた。 さらに6日後に母が亡くなって停電の合間の葬儀となり心も体も疲れ切っていたことを思いだします。
やっとワカサギはCsの数値も下がって持ち帰り可能となりましたが、未だに一部地域では渓流魚を持ち帰ることが出来ずシカやイノシシも捨てている状態が続いているのですねぇ~
さて、地震とは関係ない樹に咲く花のお話しです・・・
綺麗な花弁を持った花が咲かない樹木を見た人から「この木は花が咲かないのですか?」とよく聞かれることが有ります。
「植物は全て子孫を残すために花を咲かせるのですよ!」と簡単に説明していますが、それは「被子植物であれ裸子植物であれ胚珠のある生殖器官を花とする」という考え方で目立つ花弁が無くても花という意味なのです。
つまり、風によって花粉が運ばれる樹木は虫などを呼び寄せるための綺麗な花びらや良い香り・甘い蜜も要らないので、必要最小限の機能だけを持った地味な花が多いのということなのです・・・
風で運ぶため行き当たりばったりの送・受粉となるので「数撃ちゃ当たる」方式で大量な花粉を生産し、花粉も飛びやすいような構造になっています。
さらに、雌花と雄花が分かれているものが多く、雄花は風に吹かれて花粉を飛ばしやすいように枝の先端や外側に着き、雌しべも花粉をキャッチしやすいように柱頭が長く大きく発達ししています。
・・・ここまでは私が講座を持っている樹木学や樹木学実習で講義している内容なのですが、学生たちには実際に観察してもらう機会は非常に少ないのです。
今回取り上げたケヤマハンノキも4月の授業が始まるよりも早く、3月中に花が咲いてしまい農林大のシンボル樹なのに学生たちには観察の機会が有りません。
(↓)冬芽と葉痕です。 有毛で柄を持った冬芽で半円形の葉痕と3つの維管束痕が特徴的ですね・・・

ケヤマハンノキの雄花は尾状花序で7~9cmもあって枝先に3~4個垂れ下がって着き、真っ黄色の花粉を大量に飛散させます・・・
【参考】
スギやヒノキの花粉症と同じ時期で目立たなかったのですが、最近はこのハンノキの花粉でも花粉症になることが分かってきました。 また、ハンノキ花粉症の人は口腔アレルギーを起こしやすいようで、キウイやリンゴ・モモ・メロン・スイカなどの果物、ナッツ類・アボカド・セロリ・トマトなどの野菜を食べて口の中が痒くなったり、喉がいがらっぽくなる症状が出た場合は要注意だそうです。

そして雄花よりも元の方に着いているのが雌花で花鱗の間から紫紅色の長い花柱を出して受粉します・・・(↓)は既に受粉が始まっていました。

そして、昨シーズンの果実・・・

この果実はタンニンが多く草木染などに使われるのですよね・・・「伊香保ろの 沿ひの榛原 わが衣に 着きよらしもよ ひたへと思えば」
「風媒花は花粉が多い・・・だから花粉症になりやすいのか!」と思ったら・・・ (↓) 応援クリック よろしくお願いします! (3361話目)
「にほんブログ村ランキング」に参加中です。
【アウトドア】  【釣り】
【釣り】 

「人気ブログランキング」にも参加しています。
【自然観察】  【鮎釣り】
【鮎釣り】