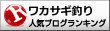ケヤキは日本の代表的な樹木で、身近にあるのだけど今まで拙ブログの冬芽と葉痕シリーズで扱っていなかったのでアップ!
単木的に生える時の樹形は円形の箒状型(↑)で、老木の樹皮(↓)は鱗片状に剥がれ、遠目に見ても樹皮を見てもケヤキって分かっちゃうね・・・

小枝は細く茶褐色で節ごとにジグザグに屈折する。 冬芽は先の尖った円錐状卵形で小さく二列互生する・・・

先端の冬芽は仮頂芽で上部の側芽とほぼ同じ大きさ・・・

芽鱗は托葉由来と言われ4~5対で無毛、葉痕はやや潰れた半円形で3個の維管束痕が確認できる・・・

冬芽は混芽(花芽と葉芽が一緒)で枝から離れ開出する。 日陰側に小さな平行予備芽を持っている。

ケヤキは「けやけき木=際立って目立って美しい木」ということに由来し、別名の「槻木(つきのき)」は強き木の略だと言われている。
材としても木目が美しく狂いが少ないので珍重され、建築材・彫刻材・漆器の木地などとして使われ年輪の詰まった木や杢目のある木は高価で取引されているんだ!
(冬芽と葉痕:246種目)
二つのブログランキングに参加しています。 (↓)のバナーをクリックして応援よろしくお願いします! (4105話目)
 |
冬芽ハンドブック |
| クリエーター情報なし | |
| 文一総合出版 |