このごろ「ネット依存」がよく話題になる。スマホが普及してから、中高生で一層問題にされるようになった。「ネット依存」のきちんとした定義はないが、要するに一日に何時間もネットと繋がっていないと気が済まない状態を言うらしい。
「ネット依存」の良くない点は、夜遅くまでやっていて寝不足になるとか、まぁ今のところその程度である。
電車やバスの中で、ずっとスマホをいじっている人がいるけれども、彼らは「ネット依存」なのだろうか?
寝不足になるほどネットをやり、電車やバスの中でもネットをやり、歩きながらでもネットをやる。このような行為のどこがいけないのだろうか?
昔は、本に夢中になってついつい寝不足になるとか、電車やバスの中で本を読むとか、歩きながら本を読むということがあった。(二宮金次郎が、その典型である。)
「ネット依存」の伝で行けば、これは「本依存」ということになってしまう。「ネット依存」が問題となって、「本依存」が問題にならないのは、どこかバランスを欠くように思うのだが、どうか?
「ネット依存」の良くない点は、夜遅くまでやっていて寝不足になるとか、まぁ今のところその程度である。
電車やバスの中で、ずっとスマホをいじっている人がいるけれども、彼らは「ネット依存」なのだろうか?
寝不足になるほどネットをやり、電車やバスの中でもネットをやり、歩きながらでもネットをやる。このような行為のどこがいけないのだろうか?
昔は、本に夢中になってついつい寝不足になるとか、電車やバスの中で本を読むとか、歩きながら本を読むということがあった。(二宮金次郎が、その典型である。)
「ネット依存」の伝で行けば、これは「本依存」ということになってしまう。「ネット依存」が問題となって、「本依存」が問題にならないのは、どこかバランスを欠くように思うのだが、どうか?












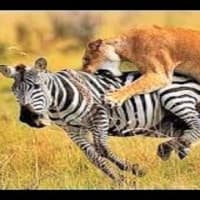






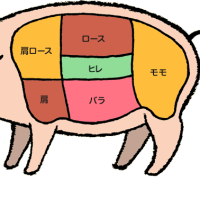
私たちが小学校のころ漫画は「悪書」でしたよね。ところが現在では並みの文学作品をしのぐような漫画がたくさんあります。悪書かどうかは時代の規範に左右されるようです。
私には「ネット依存」をまるで「アルコール依存」のように「病気」の範疇に入れてほしくないという気持ちがあります。「病気」の定義は生物学的な問題に限るべきで、社会規範との比較によって「病気」を造ってはならないと思います。この点でマスコミは無神経です。
「ネット依存」がいけないなら、二宮金次郎だっていけないだろうとこのコラムで言ったのは、社会規範なぞ時代によってすぐに変わってしまうよと指摘したかったからです。それに対して感染症のように生物学的な根拠がある病気なら、規範が変わっても存在し続けます。
ネット依存の弊害は生活リズムの乱れだけだと理解してよろしいですか。どこかに病的依存となる閾値のようなものはないのでしょうか。