観光地に行ってラウドスピーカーで歌謡曲が流されていると白ける人が多いだろう。
私は土産物屋があるだけで白けてしまう。しかも、売っているものが中国製だったりする。私が土産物屋を喜んだのは中学生までだった。
中学生のときの学校旅行では、土産物屋の商品が珍しく、夢中になって買った。それが、家で開けてみると箱は大きくても表面だけしか品物が入っていないもの(上げ底)、石鹸くらいの大きさの羊羹をの包みを解いていくと、紙ばかりを何重も剥がさなければならず、最後に消しゴムほどの羊羹しか出てこないもの(十二単衣)、縦長のビンの内側にわさび漬けが塗ってあって外側からはいっぱい入っているように見えるが、開けると中が空洞になっているものなど、騙しのテクニックの粋を尽くしていて、とてもイヤな気分になった。
いま、このような不正包装はなくなったけれども、土産物屋のDNAは消えてはいない。何の価値もない木片に焼印を押しただけのような商品が1000円程度で売っている。旅の浮かれた気分に乗じて、客はついつい買ってしまうが、家に持って帰っても何の役にも立たない。
だから私は、観光地ではないと思って行ったところに土産物屋があると、こんなところにまで観光客を騙そうとするヤカラがいるのかと、とたんに白けてしまう。すべての観光地には土産物屋があるから、私は観光地と名がついたところには行きたくない。いきおい私が遊びに行くところは、何の変哲もない地方都市になってしまう。見るものはというと、土地の人の生活である。これは、とても面白い。しかし、観光地でない都市には観光ホテルがないから、ビジネスホテルに泊まることになる。ビジネスホテルさえない都市もある。
大学生のころ私は、毎年夏休みになるとある高山の中腹にある民宿に滞在した。周囲にはなんの観光物もない。ただ夏も涼しいということだけが売りの民宿だった。1泊3食付で1日880円。この値段は、1か月逗留しても、都市の下宿代にも満たなかった。気が向くと近くの牧場や川に散歩に行った。学生が個人のエアコンをもつのが難しい時代で、涼しさを求めるなら、高山に行くしかなかった。涼しいので勉強がはかどった。
息子や娘が小学生なったころ、家族でふたたびその民宿を訪れた。学生時代とまったく変わっていなかった。牧場や川にはあいかわらず人っ子一人いなかった。むかし高校生だった民宿の長女がその民宿を継いでおり、旧交を温めた。
それから3年後、その高山への道が大幅に改善された。そして、その村にも観光客が押し寄せるようになった。家族でまたその民宿に行って驚いた。人っ子一人いなかった牧場には茶店や土産物屋が造られ、大駐車場が完備されて、観光客が押し寄せていた。開発とはこういうものかと感心した。
話は跳ぶようだが、最近、テレビ番組が面白くない。とくにゴールデンタイムが面白くない。どこのチャンネルに回してもお笑い芸人が雛段に座っていて、芸とも呼べないような振る舞いで笑いを取っているが、あれのどこが笑えるのだろうか?
テレビは視聴率を稼がなくてはならない。だから、なるべく多くの人が見る番組を安く作らねばならない。そうした努力の結果が、雛壇に並ぶお笑い芸人という番組に収れんするのだろう。
つまり、多くの人を民主的に喜ばせようとすると、ああいう番組になるのだ。(視聴率にたよって行動するのはきわめて民主的である。)観光地も観光客に来てもらおうとすると、道をよくして牧場には茶店や土産物屋を作らなくてはならないのだ。
民主的とはよいことの代名詞のように思われているけれども、こと観光地やテレビ番組については、民主的なのはよくないことである。
(「テレビは視聴率ばかり狙ってはならない」と言っている人たちは「テレビは民主的であってはならない」と言っているのと同じだということを、自分で分かっているのだろうか?)
私は土産物屋があるだけで白けてしまう。しかも、売っているものが中国製だったりする。私が土産物屋を喜んだのは中学生までだった。
中学生のときの学校旅行では、土産物屋の商品が珍しく、夢中になって買った。それが、家で開けてみると箱は大きくても表面だけしか品物が入っていないもの(上げ底)、石鹸くらいの大きさの羊羹をの包みを解いていくと、紙ばかりを何重も剥がさなければならず、最後に消しゴムほどの羊羹しか出てこないもの(十二単衣)、縦長のビンの内側にわさび漬けが塗ってあって外側からはいっぱい入っているように見えるが、開けると中が空洞になっているものなど、騙しのテクニックの粋を尽くしていて、とてもイヤな気分になった。
いま、このような不正包装はなくなったけれども、土産物屋のDNAは消えてはいない。何の価値もない木片に焼印を押しただけのような商品が1000円程度で売っている。旅の浮かれた気分に乗じて、客はついつい買ってしまうが、家に持って帰っても何の役にも立たない。
だから私は、観光地ではないと思って行ったところに土産物屋があると、こんなところにまで観光客を騙そうとするヤカラがいるのかと、とたんに白けてしまう。すべての観光地には土産物屋があるから、私は観光地と名がついたところには行きたくない。いきおい私が遊びに行くところは、何の変哲もない地方都市になってしまう。見るものはというと、土地の人の生活である。これは、とても面白い。しかし、観光地でない都市には観光ホテルがないから、ビジネスホテルに泊まることになる。ビジネスホテルさえない都市もある。
大学生のころ私は、毎年夏休みになるとある高山の中腹にある民宿に滞在した。周囲にはなんの観光物もない。ただ夏も涼しいということだけが売りの民宿だった。1泊3食付で1日880円。この値段は、1か月逗留しても、都市の下宿代にも満たなかった。気が向くと近くの牧場や川に散歩に行った。学生が個人のエアコンをもつのが難しい時代で、涼しさを求めるなら、高山に行くしかなかった。涼しいので勉強がはかどった。
息子や娘が小学生なったころ、家族でふたたびその民宿を訪れた。学生時代とまったく変わっていなかった。牧場や川にはあいかわらず人っ子一人いなかった。むかし高校生だった民宿の長女がその民宿を継いでおり、旧交を温めた。
それから3年後、その高山への道が大幅に改善された。そして、その村にも観光客が押し寄せるようになった。家族でまたその民宿に行って驚いた。人っ子一人いなかった牧場には茶店や土産物屋が造られ、大駐車場が完備されて、観光客が押し寄せていた。開発とはこういうものかと感心した。
話は跳ぶようだが、最近、テレビ番組が面白くない。とくにゴールデンタイムが面白くない。どこのチャンネルに回してもお笑い芸人が雛段に座っていて、芸とも呼べないような振る舞いで笑いを取っているが、あれのどこが笑えるのだろうか?
テレビは視聴率を稼がなくてはならない。だから、なるべく多くの人が見る番組を安く作らねばならない。そうした努力の結果が、雛壇に並ぶお笑い芸人という番組に収れんするのだろう。
つまり、多くの人を民主的に喜ばせようとすると、ああいう番組になるのだ。(視聴率にたよって行動するのはきわめて民主的である。)観光地も観光客に来てもらおうとすると、道をよくして牧場には茶店や土産物屋を作らなくてはならないのだ。
民主的とはよいことの代名詞のように思われているけれども、こと観光地やテレビ番組については、民主的なのはよくないことである。
(「テレビは視聴率ばかり狙ってはならない」と言っている人たちは「テレビは民主的であってはならない」と言っているのと同じだということを、自分で分かっているのだろうか?)












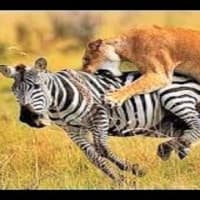






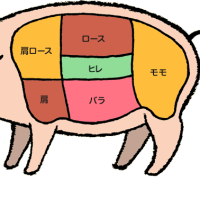
仙台の行きつけの飲み屋で、そこに居合わせたさる劇団の人たちと意気投合し、その劇団の公演を(原則会員限りのところ、特例で)観せてもらいました。その開演直前に、空席を残さぬよう、観客が一斉に席詰めすることを求められました。その指揮をとっていたのが、地元の女性代議士T.O.で、その際の指示が、「さあ、皆さん、民主的に席をつめましょう!」でした。その口調、至って真面目。その気持ち悪い掛け声の響きは今も私の耳に残っています。
豊橋市医師会は会長を選ぶのに選挙なんかやりません。5年先くらいまで「次回はあの人」というのが暗々裏に決まっています。「民主的でない」なぞと文句を言う人はいません。
精神科関連学会がいくつもあります。それらは同好会に毛が生えたようなものです。それなのに、しきりに人事を民主化しようとします。理事や理事長を選挙で決めるのですが、みなさん何故そんなに選挙が好きなのか、私には分かりません。
席を詰めるのが「民主的」なら、下の俳句はさぞかし「民主的」な俳句ということになりますね。
一人来てみな膝送る忘年会 (作者失念)
「テレビで芸人がバカ騒ぎして面白くない」という言説は、もう60年くらい繰り返されています。「面白い面白くない」は感性の問題なので、管理人さんが「面白くない」と言われればそれで話はおしまいです。
が、あまりにも「最近のテレビは面白くない」という言葉を(私の場合、実に40年近くも!)各方面で聞かされているので、コメントさせていただきます。
テレビのお笑いの手法は、ここ60年くらい、ほとんど変わっていません。なのに、新聞やネットなどで常に(お笑いの文脈で)「テレビが面白くない」という言説が繰り返されていることに、私は興味を持っています。
「テレビが面白くない」という言説の代表は大宅壮一の「一億総白痴化」という言い方でしょう。これはウィキペディアによると1956年、「出演者が早慶戦で慶應側の応援席に入って早稲田の応援旗を振り、大変な騒ぎになって摘み出される」というシーンを観た大宅が言った言葉だそうで、現在、ゴールデンでやっている番組とそう変わりません。
テレビのお笑いは、昔からつまらなかったとも言えるし、そのことをほとんどの人が忘れてしまい、「過去にはすばらしいテレビ番組があったが、今はない」という幻想を、どういうわけだか抱いているとも言えます。
おっしゃるとおり、テレビが面白くないとは昔から言われていますね。このブログではみなが言っていることは言わないことにしていますが、今回は「テレビが面白くない」とみなと同じようなことを言ってしまいました。うかつでした。
大宅壮一が一億総白痴化と言った時代には私はまだ子どもで、けっこうおもしろくテレビを見ていました。だから当時「財布は妻が主導権、テレビは子どもが主導権」という父親の嘆きの言葉が流行りました。
子どもにとってテレビは面白かったのです。逆に言うと大宅壮一みたいな大人には詰まらなかったのでしょうね。だから、一億総白痴化という言葉が受け入れられたのだと思います。
テレビは昔から詰まらなかった、というペロチャンさんの主張に賛成です。あるいは、テレビは昔から子ども向けだった、と言ってもよいかもしれません。