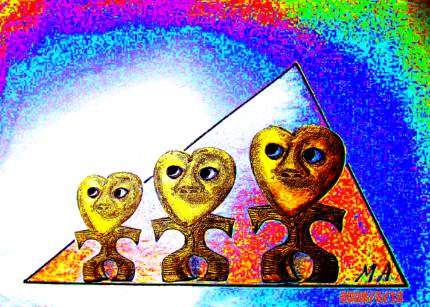アメリカの大統領、ニッポンでは歓迎されたようだが、韓国ではフクザツで、ホテルに帰るコースを変更せざるをえなかった。
韓国の聯合ニュースは、
「夕食会を終え 宿泊先のホテルにクルマで向かう途中 ルートを変更することになった」
その理由は、
「訪韓に反対する団体が車道に モノを投げ込んだためと見られる」
このニュースでは、
「戦争反対などと声を上げ 刷り物や蛍光棒などを 車道に投げ入れたもようだ」
ニッポンのネットでえは、
「投げ入れたもんが ウンコでなくて良かったね」
こういったことはよくあるようだ、日本が統治する前の街はクソだらけだったという記録がある、そして、
「これで 韓国に対するイメージが いっそう悪くなったわけだ」
また、こんな意見が、
「イヴァンカが行かなかった理由が よく分かった」
ということは、アメリカは、ある程度、予測していたのかもしれない。