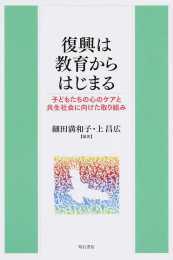
いったい、いつから読み始めたものだろうか?
図書館の新刊、新着図書を借りて、2回も返却期限を延長して、ようやく読み終えました。
振り返ると、6月の半ばから読み始めたもののようです。
正式なタイトル
「復興は教育から始まる」子どもたちの心のケアと共生社会に向けた取り組み
細田満和子・上昌広【編著】 明石書店 (2014年5月20日発行)
2011年3月11日に起きた地震と津波、そして原発事故の被災地に関して、その後の復興について書かれた本を読むのは初めてでした。図書館でたまたま出会った本です。
6月には、菅直人氏と南相馬市長の講演会を聴きにいったこともあり、それと重ねて被災地について読んでみようと思いました。
この本を読んでいくと、最初のほうは養護教諭の方等の現地の学校での子供のたちの様子や取り組みなどが書かれていました。
そして、教員や医療従事者や、元々別の地域に住む人で被災地に赴いた方々の活動報告などが個々に記されていました。
子どもたちの精神的な問題、学校が統合されたり先生が転勤したりなどによる不安定さ、家族が狭い住宅に住むことでの軋轢、健康的問題、地域の特徴、対応としてのカウンセリング、旅行の企画、スポーツや学習支援、医療の対応 等、いろいろとありました。
長い間読んでいたので、今記憶も定かではないのですが、これらの様々な多くの人々が、現地で有意義な活動をされたんだなあと、今つくづく感じ、感謝を述べたい気分です。
正直言うと、読んでいるうちに、この先読み続けるのが苦痛になってきたことがありました。それは、個々のレポートのようなものの連続であったからであり、これは一般人に向けたものではなく、これらの活動を行った団体の内輪の報告書のようなものではないだろうかと思えてきたからです。
ここに出てくる「星槎グループ」「星槎大学」などという耳慣れない名前は一体なんだろうか?というのは、最初のころの疑問でした。これが私立の学校であり、神奈川県に本拠地を置くものらしいことがだんだんわかってきました。
この学校のサイトを見ると、「槎」とは、大きさの不揃いな木でできた筏(いかだ)のことだそうで、それぞれ個性の違う人間が、協調したり力を合わせたりして、1つのイカダが結成されることを示す名前だということがわかりました。
子どもというのも、それぞれ大きさも太さも性質も違う木のようなものでしょうが、被災地において支援活動をした人々もまさしくそういうものであり、それぞれの人が、それぞれの個性や能力を持って、自分の専門分野や得意とすることで、被災地で力を尽くし、しかしそれらの人々の意思や心は、筏のように結束されていたのだなあと思います。
ともかく、被災地でそういう活動がおこなわれてきたのだ、という具体的真実を知ることができたのは、この本を最後まで読んでよかったことでした。


















