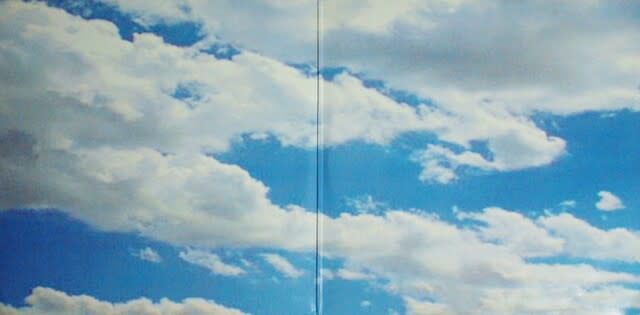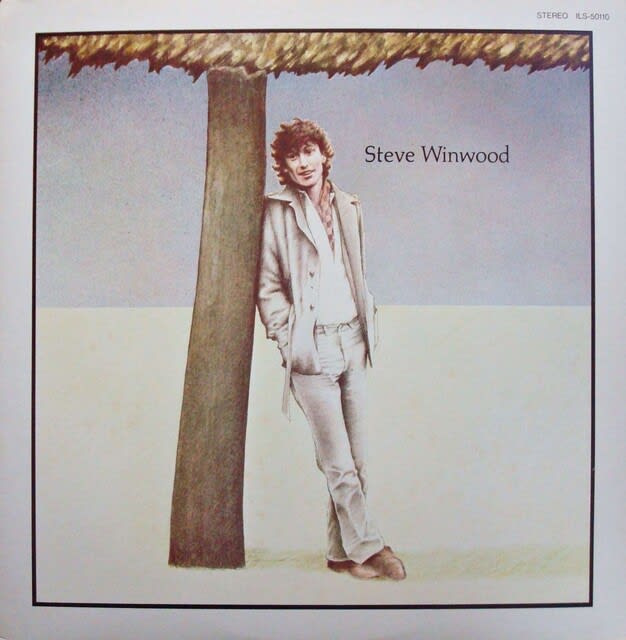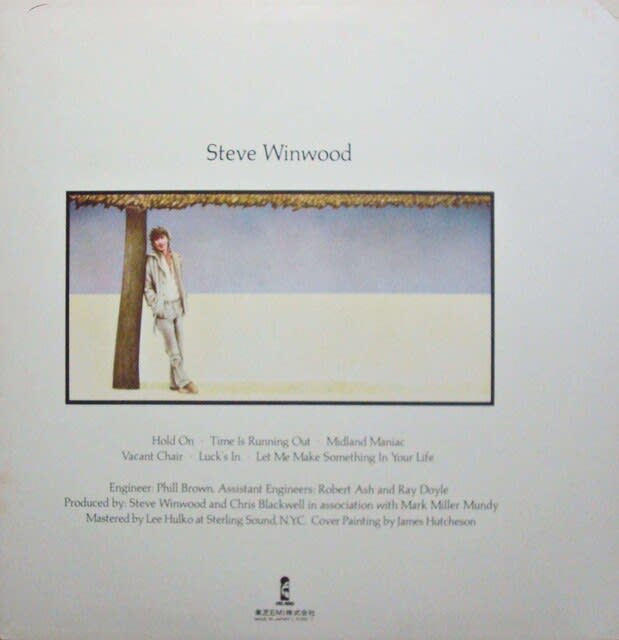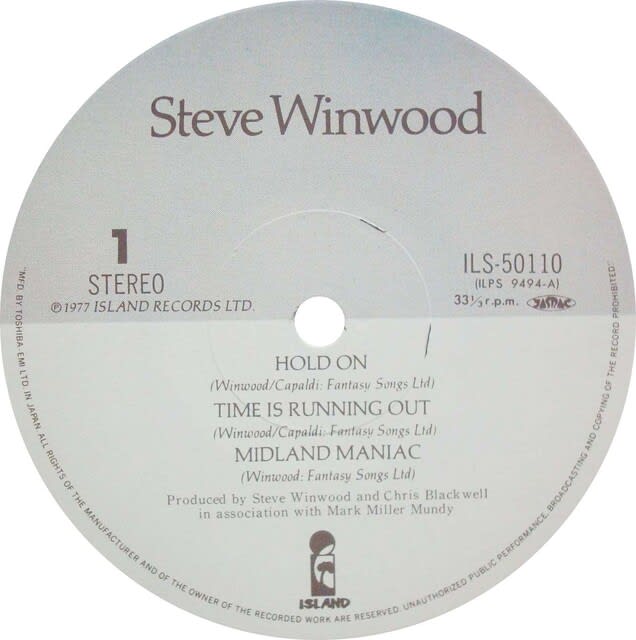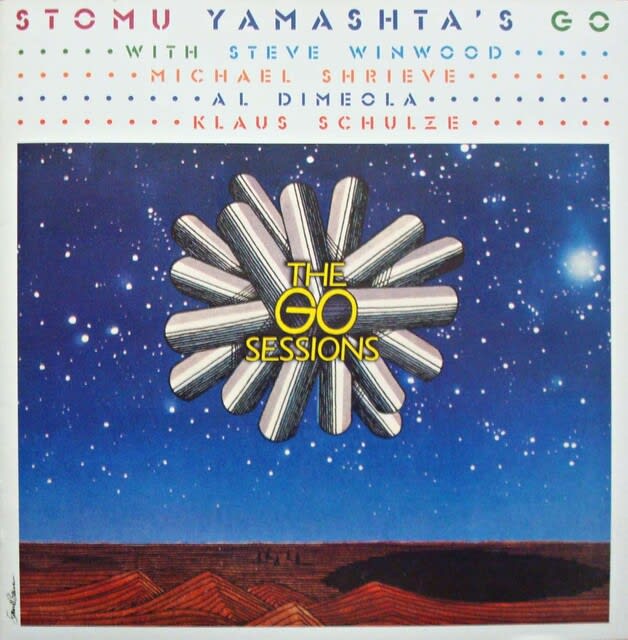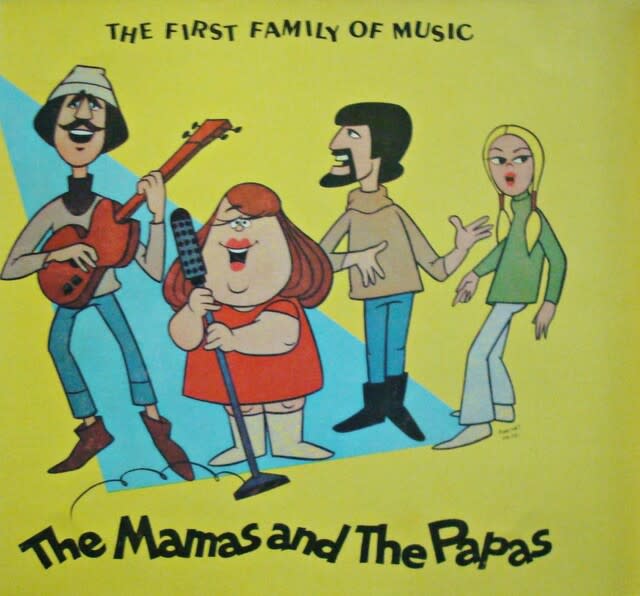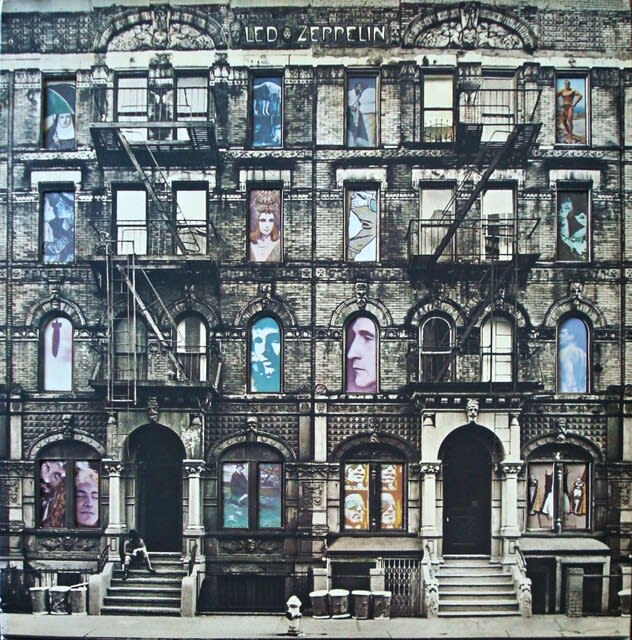1973年のアルバム、Crazy Eyesの後バンドの創設者であった大黒柱のリッチー・フューレイがバンドから脱退。
4人組となってPocoはどうなってしまうのかと思ったが、以外や以外それまでスティール・ギターの演奏専門だったラスティー・ヤングに責任感が芽生えたのか、曲を作ったりまたリード・ボーカルを取ったりと変化を見せグループとしてのまとまりもさらに強くなり、大ヒットとはならずもコンスタントに好アルバムを発表してきた。
そして前所属レーベル、エピックとの契約が切れABCレコードと契約し心機一転。
その第1作目が1975年のアルバム、Head Over Heels。直訳すれば頭が踵を越えるってことで真っ逆様の意。

即ち、それぐらいもう夢中で活動しているよ!ってニュアンスですかね?
収録された各曲、余計と思われたところは削りコンパクトに約3分程度の曲に編集。それまでのカントリー重視から少しばかりポップさも加わり親しみやすくなっている。
ティモシー・シュミット作のヒット曲、Keep On Tryin’にポール・コットンがカバーするスティーリ・ダンの幻の曲、Dallasなど聴きどころはいっぱい。そしてラスティーも歌ってます!

(ティモシー・シュミット作のKeep On Tryin’がアルバムのオープナー)

(ドナルド・フェイゲン-ウォルター・ベッカー作、DallasはサイドーBに)
もう少し派手にやれば第二のイーグルスとしてもっと人気が出たのではないかと…
しかしこの地味さが個人的には何とも味があり彼らの魅力になっているんだと思う。