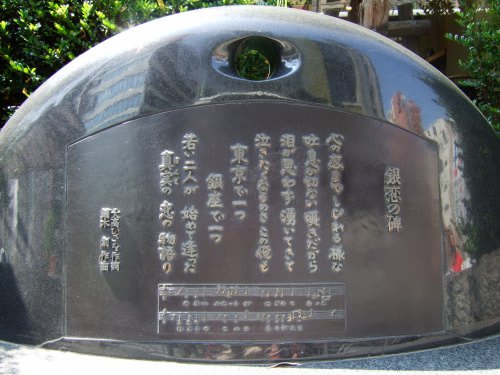四国遍路道の道しるべ、その2は、高知県で見かけたものです。
室戸岬を過ぎて、標高164mにある26番金剛頂寺へは、東側
から林間のへんろ道を上がります。寺まで150mのところにあっ
た簡単な道しるべ。お寺さんで作ったものでしょうか。

残りどのくらいか、距離が分かると安心です。
金剛頂寺から南西の国道55に向かって、やはり林間を下り
ます。「国道へ1k」と記されています。

27番神峰寺(こうのみねじ)へは、標高200m辺りから車道に
別れて「真っ縦」と呼ぶ急坂の遍路道を標高430mの寺まで
上がります。

遍路道の入口に立つ「神峯遍路道」の標識。車道は石碑の
右側を上がります。
その遍路道の途中に下がる、へんろみち保存協力会の遍路札。

あちこちの遍路道にたくさん下がっているこの札を確認でき
ると、道を間違えていないと分かり、ホッとします。
29番国分寺から30番善楽寺へ向かう車道、南国市の西端
近くにあるヘンロ小屋5号蒲原付近の「四国のみち」の標識。

へんろみち保存協力会の赤い遍路札も止めてあります。
高知市内に入り、浦戸湾を見下ろす32番禅師峰寺(ぜんじ
ぶじ)の下、遍路道と車道との分岐点に立っていました。

遍路道は、右側からひとしきりの急登です。
最近、電柱などに印刷されるようになった、遍路道である
ことを記す四鈷マークと、ブルーのシール。どういう団体の
ものなんでしょうか。

36番青龍寺を打ち終え、浦ノ内湾沿いに進む、高知県水産
試験場付近の県道23号線の電柱にあったもの。
浦ノ内湾を過ぎ、県道314号にある佛坂は、県道をショート
カットする短い遍路道で越えます。その入口にある新しい遍路
標石。

このような標石は、平成に入って建てられたので「平成遍路
石」と呼ばれています(2つ手前の写真・禅師峰寺の下にある
ものも「平成遍路石」です)。
坂を下ると、番外霊場・仏坂不動尊(岩不動)があります。
仏坂遍路道の途中にある37番岩本寺への道標。

誰が吊したのか、鈴が下がっていました。
36番青龍寺から37番岩本寺への途中の中土佐町で、七子
峠(287m)に向かって、そえみみず遍路道と大坂遍路道の
二つの遍路道があります。その分岐に立つ標識です。

そえみみず遍路道は、古くからの遍路道の雰囲気をよく残す
コースとして人気が高かったのですが、現在、四国横断自動車
道の工事のため、2008年末まで通行止めです。
37番岩本寺から、足摺岬にある38番金剛福寺までは80km
の長丁場。岩本寺から5km余り、国道55号をショートカットする
片坂遍路道の入口付近にあった標識。

落ち葉がいっぱいの林間を抜ける、気持ちよい遍路道です。
足摺岬まで9kmほどに迫った窪津漁港の横から、漁港を見下
ろす遍路道に上がりますが、その入口付近にあったかと思われ
る古い石仏の台座に彫られた遍路道の標識です。

このような、お地蔵さんなどの石仏に遍路道であることを記し
たものは、何か所かで見ました。(続く)
室戸岬を過ぎて、標高164mにある26番金剛頂寺へは、東側
から林間のへんろ道を上がります。寺まで150mのところにあっ
た簡単な道しるべ。お寺さんで作ったものでしょうか。

残りどのくらいか、距離が分かると安心です。
金剛頂寺から南西の国道55に向かって、やはり林間を下り
ます。「国道へ1k」と記されています。

27番神峰寺(こうのみねじ)へは、標高200m辺りから車道に
別れて「真っ縦」と呼ぶ急坂の遍路道を標高430mの寺まで
上がります。

遍路道の入口に立つ「神峯遍路道」の標識。車道は石碑の
右側を上がります。
その遍路道の途中に下がる、へんろみち保存協力会の遍路札。

あちこちの遍路道にたくさん下がっているこの札を確認でき
ると、道を間違えていないと分かり、ホッとします。
29番国分寺から30番善楽寺へ向かう車道、南国市の西端
近くにあるヘンロ小屋5号蒲原付近の「四国のみち」の標識。

へんろみち保存協力会の赤い遍路札も止めてあります。
高知市内に入り、浦戸湾を見下ろす32番禅師峰寺(ぜんじ
ぶじ)の下、遍路道と車道との分岐点に立っていました。

遍路道は、右側からひとしきりの急登です。
最近、電柱などに印刷されるようになった、遍路道である
ことを記す四鈷マークと、ブルーのシール。どういう団体の
ものなんでしょうか。

36番青龍寺を打ち終え、浦ノ内湾沿いに進む、高知県水産
試験場付近の県道23号線の電柱にあったもの。
浦ノ内湾を過ぎ、県道314号にある佛坂は、県道をショート
カットする短い遍路道で越えます。その入口にある新しい遍路
標石。

このような標石は、平成に入って建てられたので「平成遍路
石」と呼ばれています(2つ手前の写真・禅師峰寺の下にある
ものも「平成遍路石」です)。
坂を下ると、番外霊場・仏坂不動尊(岩不動)があります。
仏坂遍路道の途中にある37番岩本寺への道標。

誰が吊したのか、鈴が下がっていました。
36番青龍寺から37番岩本寺への途中の中土佐町で、七子
峠(287m)に向かって、そえみみず遍路道と大坂遍路道の
二つの遍路道があります。その分岐に立つ標識です。

そえみみず遍路道は、古くからの遍路道の雰囲気をよく残す
コースとして人気が高かったのですが、現在、四国横断自動車
道の工事のため、2008年末まで通行止めです。
37番岩本寺から、足摺岬にある38番金剛福寺までは80km
の長丁場。岩本寺から5km余り、国道55号をショートカットする
片坂遍路道の入口付近にあった標識。

落ち葉がいっぱいの林間を抜ける、気持ちよい遍路道です。
足摺岬まで9kmほどに迫った窪津漁港の横から、漁港を見下
ろす遍路道に上がりますが、その入口付近にあったかと思われ
る古い石仏の台座に彫られた遍路道の標識です。

このような、お地蔵さんなどの石仏に遍路道であることを記し
たものは、何か所かで見ました。(続く)