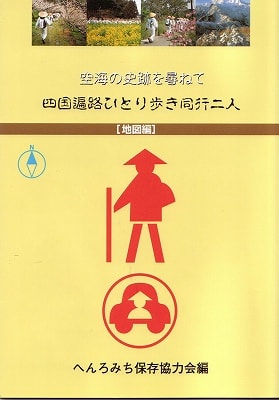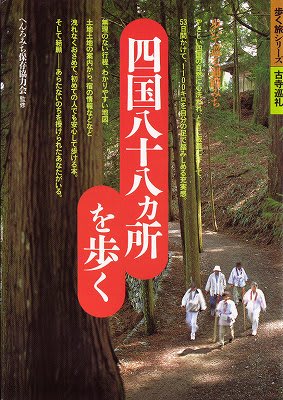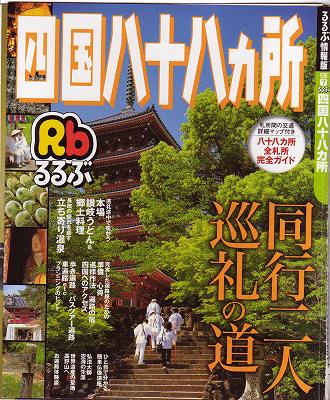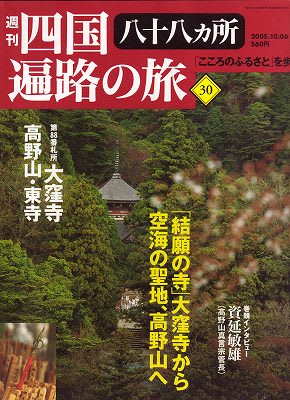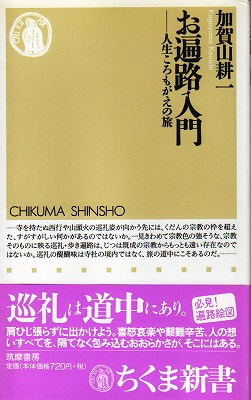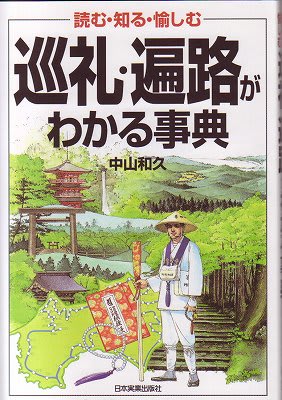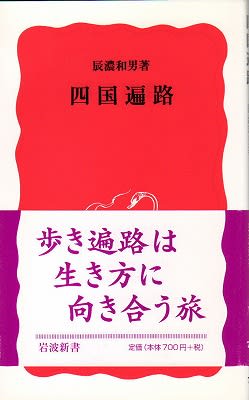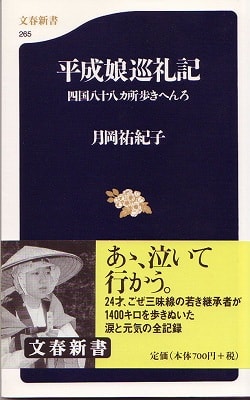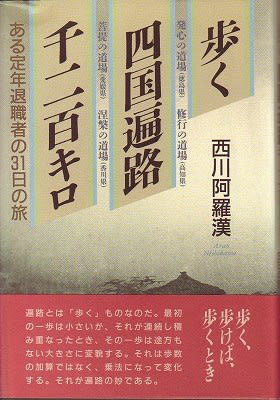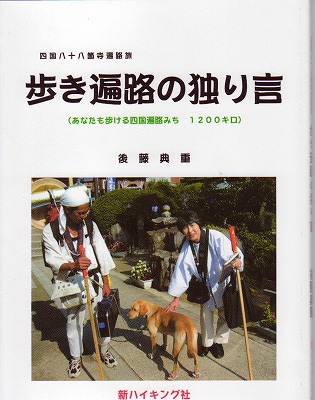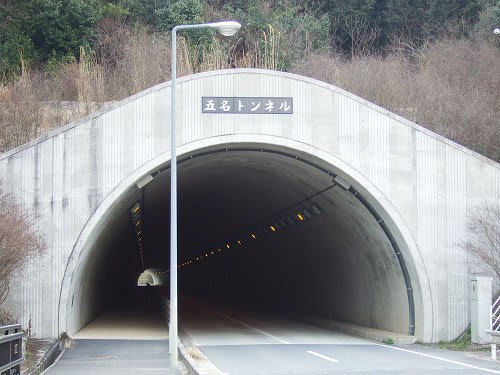関東地方、今日は季節外れの台風20号の接近で、
冷たい雨となりました。この雨の中、カントリウオーク
の仲間は、福島県会津地方の廃線跡歩きに出かけて
います。
私は、用事が2,3あり不参加となりましたが、会津
でも雨の中を、歩いたのでしょうか。
そのレポートを報告することが出来ないので、同じ
ように一昨年の今ごろ歩いた、茨城県常陸太田市内
から日立市への廃線歩きを含めたカントリウオークに
ついて、紹介します。
======================
=常陸太田市内と、日立電鉄廃線跡を歩く=
2005年11月29日(土)
常陸太田市内の旧跡を巡る

JR大宮駅集合の14人は、8時41分発宇都宮線に
乗り、水戸線経由で水戸駅に11時29分に着く。
一方、常磐線組の7人は、上野駅9時10分発に上野
と柏から乗り、宇都宮駅11時13分着、全員が合流し、
JR水郡線常陸太田駅に12時47分に着いた。

予報では雨も心配されたが、雲は高目でどうやら持ち
そう。駅から北北西へ、西バイパスと呼ぶ車道を500m
ほど進み、県道61号から、山吹運動公園に隣接する
「そば越路」に入る。
県推奨銘柄の秋そばを、手刈り天日干しして石臼(い
しうす)で引き、1日12食限定という「常陸あきそば」、
今日の担当、Mさんが依頼して特に21食分用意して
もらった。

まずアルカリイオン水で香りをかいでから、つゆで味
あう。

歩く前なので、もう少し食べたかったが、限定品だけ
あり、十割そばの味には、みな満足した。
食べた終えた人から出発となり、早めの私は先発し
た。ひこばえの伸びた田んぼの間を進み、宮作集落
の手前を南東に向かう。
天神林町近くの林に「山寺水道」の碑があり、集落
には説明板が立っていた。

それによれば山寺水道は、寛文8年(1668)、水戸
藩主、徳川光圀(みつくに)の命で構築した用水、暗
渠(あんきょ)により水を集め岩樋をもって送り、延長
は2000mに及ぶ、当時としては類例のない工法で、
現在も近隣の農家を潤しているという。

ツリガネニンジンの咲く静かな集落、畑の間を抜け
ようとしたらキジが飛びだした。
県道61号に出てすぐ先の、坂東三十三番観音霊場、
佐竹寺に参拝する。

佐竹寺は、寛和元年(985)、花山天皇の勅願により
開山と伝えられる古寺。天文15年(1546)佐竹義昭
によりこの地に再建され、安全、厄除けの仏様として
巡拝者が絶えないとという。
りっぱな仁王門をくぐった正面に、かやぶき寄せ棟
造り、国宝の本堂がどっしりと構えている。

本堂前に童顔のお地蔵さんがたくさん並び、境内の
大イチョウにはギンナンがいっぱい色づいていた。

北側の民家の前に、古代米の黒米、赤米の無人ス
タンドがあり、1袋100円で売っている。健康食品なの
で、黒米を一つ買い求めた。
佐竹寺で9人に増えた一団が、もとの道を天神林町
の途中まで戻り、二つの三差路を西から北に進んで
白馬寺に行く。

かやぶきにトタンを被せた本堂。周囲に大きな木立
はなく開放的。サザンカが花を開き、ホトトギスもたく
さん咲いていた。庫裡(くり)の犬数匹が、にぎやかに
吠えたてる。
車の少ない2車線の車道を北へ、標識で右手の林
に上がって西山荘(せいざんそう)を目指す。広葉樹林
と赤松の混交林を行くが、なかなか出ない。
三差路を左に進むと、市営斎場横の車道に出た。
地図を確認、先ほどの三差路を右に行けばよいと
分かり、戻ってさらに三差路の先に進む。
再度三差路を左折したろうか、ふみ跡が細くなり
これも違うかと思ったら、下に遊歩道が見えた。
顔も埋まるほど伸びた熊笹の間をかき分けて遊歩
道に下った。ひと安心した同行のメンバー。

ここはもう西山荘。水戸藩主を退いた徳川光圀公
が元禄4年(1691)から亡くなるまでの10年間、
隠居生活を送った、かやぶき屋根の西山御殿と邸内
を回る。
谷間にある邸内は、松、モミジ、梅、ツツジなどの
豊かな木々と三つの池をめぐらしている。

現在の建物は文政2年(1819)の再建というが、草
の伸びたかやぶき屋根や土壁が周囲の木々に溶け
こみ、落ち着いたたたずまいを見せている。

かやぶきの守護宅資料室で、ここで編纂(へんさん)
した「大日本史」原稿など黄門様ゆかりの資料を見て、
これもかやぶきの通用門を出た。
小さい流れ沿いに梅園の続く公園の東屋(あずまや)
で休憩、Sさんがいつものようにコーヒーを湧かして
くれた。
公園の出口では、水戸市から歩いてきた「水戸黄門
様漫遊ウオーク」の一行、数10人がゴールし、盛大な
歓迎を受けていた。
国道293号に向かう三差路に、寒桜が小さい花を
開いていた。次の三差路を右折、南に上がり、色づく
桜と芝生に覆われた西山公園に入る。
義公廟の前から急階段を下り、公園下を北に進ん
で、16時51分、今日の宿、まんだらじ旅館に着いた。
まんだらじ館の夕食メニュー。

(天気 曇り、歩行 21人、距離 8㎞、地図(1/2.5万)
常陸大田、歩行地 常陸太田市)