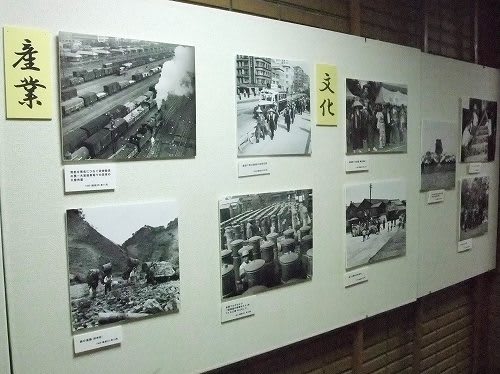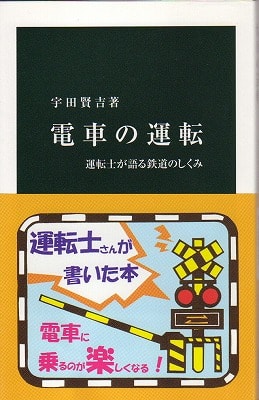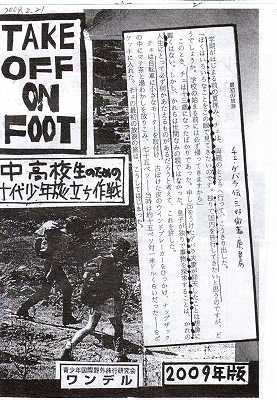2009年2月28日(土)

地図愛好グループの例会で、東京・奥多摩の日の出町を訪ねた。
集合は、JR五日市線の武蔵増子(ますこ)駅に10時。
まず、駅の近くにある三角点を探すことにする。駅から線路沿いを
東に向かい、踏切を渡って線路際の畑道を少し進む。

畑の隅に、177.1mの四等三角点があった。

ここからは360度の展望が良い。企画者のNさんにもらって地図で、
周辺の三角点のある地点を皆で同定し合う。
次に2台の車に分乗して、西北西の日の出団地南側の稜線にある
279.1mの三角点を目指す。だだ、ここは最近の地形図からは抹消
されていることを私は前日把握していたので、無いはずだが一応確認
することにした。
戸建て住宅が整然と並ぶ日の出団地の西端まで行き、横沢東尾根
と呼ぶそばの稜線を南東に上がる。写真は、稜線からその団地を見下
ろしたところ。

一帯は、横沢入里山保全地域になっていて、稜線に遊歩道がついて
いる。
そのピークが、279.1m三角点の位置だが、やはり三角点の痕跡
は見つからなかった。

車で都道185号を少し北上し、平井にある秋川霊園の一角で昼食と
する
都道184号を西へ、萱窪交差点から秋川街道を坂本まで進み、都道
251号に入る。北大久野川沿いの集落には梅の木や梅林が多く、見ご
ろ花があちこちで見られた。
標識に従い、次第に人家の少なくなった細道を上がって行くと、集落の
尽きたところに中曽根・レーガン会談で知られた日の出山荘があった。

もとは中曽根康弘元首相の別荘だが、平成18年(2006)11月11日に
中曽根氏から日の出町に寄贈され、1年後の平成19年の同日から日米
首脳会談記念館として公開されている。

建物は3棟あり、青雲堂と呼ぶかやぶき屋根の建物は、昭和58年
(1983)11月11日到着したレーガン大統領夫妻に、いろりを囲んで
中曽根首相が抹茶をたててもてなしたところ。

その先の天心亭では、昼食後、中曽根首相とレーガン大統領が日米
友好協力、世界の安全保障について首脳会談(ロン・ヤス)会談を行っ
たという。

一番奥の書院(上)には、レーガン大統領夫妻の写真をはじめ、ここ
を訪れたゴルバチョフ元ロシア大統領ほか各国の来賓や、中曽根首相
の写真、自筆の書、各国首脳からの贈答品などが展示されていた。
これは、1996年5月27日、韓国の全斗煥大統領から贈られた半鐘。

ひととおり見て回った後、記念撮影をする。今日の参加者は、カメラ
を入れて10人だった。

広い邸内の一角で紅梅が満開、入口付近にはフクジュソウがたくさん
咲いていた。

ちなみに日の出山荘の入館料は、一般200円、65歳以上と高校生
100円、中学生以下無料。休館日は月、火(祝日の場合は翌日か翌々
日)、開館は10時~15時30分(入館受け付15時まで)である。
再び車に分乗し、武蔵増子駅と武蔵五日市駅の中間、JR五日市線
の線路の北側にある古寺、大悲願寺へ。草創は鎌倉時代とのこと。ここ
は、あきる野市になる。
堂々たる楼門(仁王門)は、安政6年(1859)の再建。天井には、梵
字を囲んで草木の花が描かれ、左手の袖天井には、みごとな雲龍図が
描かれていた。

楼門を入った正面にあるのが「無畏閣(むいかく)」とも呼ばれる観音堂。

寛政6年(1794)の建立で、最近大規模な修復工事が行われ、屋根下
の彫刻も鮮やかな彩色が復元されている。

堂内には、国指定重要文化財の「木造伝阿弥陀如来及び脇侍、千手
観世音菩薩・勢至菩薩座像」が安置されているという。
観音堂の右手にある本堂は、元禄8年(1695)の建築。特に内部は
建築当初の姿をよく保っていて、方丈系本堂建築としては、この地方の
代表的な建物のひとつらしい。

境内には、安永9年(1780)に建築の中門(朱雀門)、あきる野市
保存樹のサルスベリの古木、四国八十八か所お砂踏み霊場など、見
るべきものが多い。
余談だが、この大悲願寺には、第2次世界大戦末期の昭和19年
(1944)晩秋、新宿、中村屋の創立者・相馬愛藏と良(国光)夫妻が
離れの一棟に疎開したという。
当時ほかに、本堂には世田谷区の疎開児童が100人ほど、観音堂
には陸軍の衛生班など、多数の住人がこの寺にいたことが、臼井吉見
の大河小説「安曇野」に記されている。
15時近く、JR五日市線の終点・武蔵五日市駅に着き、解散となった。
地図愛好グループの例会で、東京・奥多摩の日の出町を訪ねた。
集合は、JR五日市線の武蔵増子(ますこ)駅に10時。
まず、駅の近くにある三角点を探すことにする。駅から線路沿いを
東に向かい、踏切を渡って線路際の畑道を少し進む。

畑の隅に、177.1mの四等三角点があった。

ここからは360度の展望が良い。企画者のNさんにもらって地図で、
周辺の三角点のある地点を皆で同定し合う。
次に2台の車に分乗して、西北西の日の出団地南側の稜線にある
279.1mの三角点を目指す。だだ、ここは最近の地形図からは抹消
されていることを私は前日把握していたので、無いはずだが一応確認
することにした。
戸建て住宅が整然と並ぶ日の出団地の西端まで行き、横沢東尾根
と呼ぶそばの稜線を南東に上がる。写真は、稜線からその団地を見下
ろしたところ。

一帯は、横沢入里山保全地域になっていて、稜線に遊歩道がついて
いる。
そのピークが、279.1m三角点の位置だが、やはり三角点の痕跡
は見つからなかった。

車で都道185号を少し北上し、平井にある秋川霊園の一角で昼食と
する
都道184号を西へ、萱窪交差点から秋川街道を坂本まで進み、都道
251号に入る。北大久野川沿いの集落には梅の木や梅林が多く、見ご
ろ花があちこちで見られた。
標識に従い、次第に人家の少なくなった細道を上がって行くと、集落の
尽きたところに中曽根・レーガン会談で知られた日の出山荘があった。

もとは中曽根康弘元首相の別荘だが、平成18年(2006)11月11日に
中曽根氏から日の出町に寄贈され、1年後の平成19年の同日から日米
首脳会談記念館として公開されている。

建物は3棟あり、青雲堂と呼ぶかやぶき屋根の建物は、昭和58年
(1983)11月11日到着したレーガン大統領夫妻に、いろりを囲んで
中曽根首相が抹茶をたててもてなしたところ。

その先の天心亭では、昼食後、中曽根首相とレーガン大統領が日米
友好協力、世界の安全保障について首脳会談(ロン・ヤス)会談を行っ
たという。

一番奥の書院(上)には、レーガン大統領夫妻の写真をはじめ、ここ
を訪れたゴルバチョフ元ロシア大統領ほか各国の来賓や、中曽根首相
の写真、自筆の書、各国首脳からの贈答品などが展示されていた。
これは、1996年5月27日、韓国の全斗煥大統領から贈られた半鐘。

ひととおり見て回った後、記念撮影をする。今日の参加者は、カメラ
を入れて10人だった。

広い邸内の一角で紅梅が満開、入口付近にはフクジュソウがたくさん
咲いていた。

ちなみに日の出山荘の入館料は、一般200円、65歳以上と高校生
100円、中学生以下無料。休館日は月、火(祝日の場合は翌日か翌々
日)、開館は10時~15時30分(入館受け付15時まで)である。
再び車に分乗し、武蔵増子駅と武蔵五日市駅の中間、JR五日市線
の線路の北側にある古寺、大悲願寺へ。草創は鎌倉時代とのこと。ここ
は、あきる野市になる。
堂々たる楼門(仁王門)は、安政6年(1859)の再建。天井には、梵
字を囲んで草木の花が描かれ、左手の袖天井には、みごとな雲龍図が
描かれていた。

楼門を入った正面にあるのが「無畏閣(むいかく)」とも呼ばれる観音堂。

寛政6年(1794)の建立で、最近大規模な修復工事が行われ、屋根下
の彫刻も鮮やかな彩色が復元されている。

堂内には、国指定重要文化財の「木造伝阿弥陀如来及び脇侍、千手
観世音菩薩・勢至菩薩座像」が安置されているという。
観音堂の右手にある本堂は、元禄8年(1695)の建築。特に内部は
建築当初の姿をよく保っていて、方丈系本堂建築としては、この地方の
代表的な建物のひとつらしい。

境内には、安永9年(1780)に建築の中門(朱雀門)、あきる野市
保存樹のサルスベリの古木、四国八十八か所お砂踏み霊場など、見
るべきものが多い。
余談だが、この大悲願寺には、第2次世界大戦末期の昭和19年
(1944)晩秋、新宿、中村屋の創立者・相馬愛藏と良(国光)夫妻が
離れの一棟に疎開したという。
当時ほかに、本堂には世田谷区の疎開児童が100人ほど、観音堂
には陸軍の衛生班など、多数の住人がこの寺にいたことが、臼井吉見
の大河小説「安曇野」に記されている。
15時近く、JR五日市線の終点・武蔵五日市駅に着き、解散となった。