関東百駅巡礼歩行などで知った、所沢市の I さんが関わっておられる、「所沢山里
探訪会」と「NPO秩父まるごと博物館」主催の催ししに参加した。
9月26日(日)10時に西武秩父駅前に集合し、地図と見どころの解説の記された
資料をもらい、10時19分に出発した。
土産店や飲食場所などの並ぶ仲見世通りを抜けて、秩父鉄道御花畑駅西側の踏
切を渡る。まずは秩父三十四観音第十一番慈眼寺(じげんじ)のそばの交差点へ。
寺の前を南北に走る通りは、かつて地蔵川が流れていて、慈眼寺の地蔵堂は川沿
いにあったという。現在、川は暗渠(あんきよ)になっているようだ。

道路沿いの地蔵堂や、精巧な木彫の施された慈眼寺本堂↑、薬師堂などを見る。
経蔵には、一切経(いっさいきょう)が1600巻余りが収蔵された、六角形の大きな
輪堂があり、参拝者が押すと回転するようになっていた。
すぐ先左手に、埼玉県秩父地方庁舎がある。秩父地方は、江戸時代には「忍(おし))
藩秩父領」と呼ばれ、ここに代官所があり、明治、大正時代には、秩父郡役所があっ
たとのこと。庁舎の看板の下に、郡役所の写真が掲示されていた。
上町一丁目交差点を左折して県道73号へ。北側の矢尾百貨店は、もと矢尾商店と
いい、創業者は滋賀県日野町の大橋喜兵衛で、江戸時代の店員は、全員近江から
の単身赴任者だったという。
矢尾百貨店と道路を挟んで南側に、「松本教室」の看板の上がる古い建物があり、
中に入って見せてもらう。もとは旅館だった建物で、2階に上がると、学習塾に使われ
ている教室が4室ほどあり、中庭を挟んだ南側の広い敷地には、2棟の蔵や木造の
住居、井戸などが残っていた。

旅館だった建物の内部は吹き抜けになっていて、太い柱や梁(はり)、2階の回廊
などの黒ずんだ木材が歴史を感じさせ、和紙で作られた長い行灯(あんどん)が吊さ
れていて、穏やかな光を放っていた。

この建物は、国登録有形文化財となっている。
県道を西に進むと、右手に木造3階の大きな建物がある。「三階松本」と呼ばれ、
秩父の代表的な養蚕農家だった、同姓の松本家のもの。蚕の飼育を増やすに従い、
2階屋では狭いので3階に増築したのだという。

県道を400mほどで、秩父往還は右手の細い通りへ。市立図書館北の四差路際
に、小さい庚申堂があった。大正時代、この付近に伝染病がはやったとき、庚申様を
粗末にしているといわれ、ここに祭ったものらしい。

秩父二中の横を回り、押堀川の大門橋を渡る。急坂を上がると、金仙寺(こんせん
じ)への長い参道の前に出る。金仙寺は橋久保大膳守の館跡といわれ、西は荒川
の断崖、北は押堀川の深い谷に囲まれた要害の地。秩父七福神布袋尊の寺だが、
時間の関係で境内には入らなかった。
広い墓地の西に回ると、甲州武田家二十四将の一人、原隼人の墓がある。もとは
秩父二中前にあったが、校庭の拡張の際に朝礼台の下になり、校長や生徒に墓の
たたりといわれる病気が出て、この地に移して供養したという。

近くの畑付近からは、石灰岩採掘で大きく姿を変えた、武甲山北面が望まれる。

少し先の新興住宅地の北に、草に覆われた小さい丘があり、上に小さい祠(ほこ
ら)が見える。狐塚古墳と呼ばれ直径は24mあり、秩父地方では大きい円墳とか。

昔この付近は「金泉寺原」と呼ばれ人家も無く、この塚に住み着いていた狐に、よ
く化かされたという。
県道209号を横断し、影森中の正門前へ。1991年、当時の影森中の校長・小嶋
登作詞、音楽教師・坂本浩美作曲の「旅立ちの日に」は、現在、小中高の卒業式で、
全国で最も広く歌われる卒業式の歌。

校庭にある歌碑を見せてもらい、そばにいた男子生徒にお願いしたら、2人で歌っ
てくれた。
学校の先で右折、柳大橋に下る車道との交差点に、元禄時代(1688~1704)
の「二十六番道」と記された秩父札所の道標が残っていた。

同じ時代の道標は、現在30基ほどあるという。
細い甲州道をさらに進み、国道140号を横断する。ウッディコイケという木材加工
工場の横を通過し、影森駅前からの車道と合する交差点際に、地像堂があった。
「延命地蔵堂」と記され、この地に接する4耕地を代表する旧家4家の地蔵だった
とのこと。下の写真は、地蔵堂の手前の秩父往還をふり返ったもの。

旧家の残る宮本町の家並みを抜け、国道との合流点に近い台地上にある、諏訪
神社に12時45分に入り、境内で昼食とする。
諏訪神社は、創立は不明だが天正5年(1577)の古い棟札が残り、「信玄焼」と
呼ばれる武田群の戦火にあった後に再建されたという。

社殿横に樹齢600~700年、樹高40m、ご神木のスギの大樹があり、境内は
たくさんのスギに囲まれていた。
境内には、秩父地方の農村歌舞伎舞台の典型的なものの一つという木造の舞台
もあるが、現在は公演は困難になっているという。
国道に下って浦山口駅への道を入ると、不動名水と呼ぶ豊富な湧水が流れ落ち
ている。

そばに不動堂があり、武甲山塊の地中深くから湧出したもので、古くから住民の
生活や旅人ののどを潤したと記されていた。飲んでみると、そう冷たくはないが、ま
ろやかな味わいだった。
再び国道に戻る。久那橋への三差路際には、「左三峯山道 左廿八番道」と記さ
れた自然石の道標が立つていた。
秩父鉄道の線路を越える手前には、「列士鈴木安吉碑」が立つ。秩父事件の際、
首領宮川安五郎を捕らえたため、戸長役場から金一封を賜った記念碑で、書は右翼
の大物、頭山満によるもの。
秩父鉄道を越え、右手の旧道に入るあたりで浦山川が迫り、樹間はるか下に深い
流れが、上流正面には、浦山ダムの堰堤(えんてい)が望まれる。

秩父市に合併した旧荒川村に入り、花盛りのソバ畑が増える。昨日今日、近くで
「新そばまつり」を開催中というので回ってみた。

大きな変電所の北側に、花盛りの大規模なソバ畑が広がる。その周囲にテントが
たくさん並んでいたが、期待のソバはすでに売り切れ。売れ残っていた地元産品な
どを眺めて、しばし休憩する。
その先の国道には、左側に新しい歩道が設けられていた。秩父鉄道が国道と交差
する近くに、即道(そくどう)神社(右)と薬師堂(左)の小さい社が並んでいた。

「即道」とは、元禄の頃に出家した人だが、奇人として数々の逸話が残っていると
いう。
即道神社の中にある爪彫石は、即道が富士山から袂(たもと)に入れて持ち帰った
もので、刻まれた文字は即道が爪で刻んだものとか…。薬師堂内には、即道が彫っ
たという木造薬師如来像が安置されていた。
秩父鉄道の線路沿いを進み、武州中川駅に寄る。再び国道に出て荒川総合支所
の手前で右に入る旧道へ。旅館だったという坂口屋の先で左へ急カーブして、細道
を抜けて国道に戻る。
小さい流れの先、右手下にも薬師堂がある。ここにも、即道が彫った、木造の薬師
如来立像が安置されている。お堂の横のヒガンバナが、見ごろになっていた。

国道の改良で自動車通行禁止となった、旧国道の安谷橋を渡り、ゴールの秩父鉄
道武州日野駅に15時42分に着いた。
道すじにに残る数々の建物や、遺跡、道しるべ、社寺などについて、詳しい説明を
していただきながら歩き、秩父往還・甲州道を知る大変よい機会となった。
(天気 晴後曇、参加 13人、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 秩父、歩行地
秩父市、歩数 18,000)





















































































































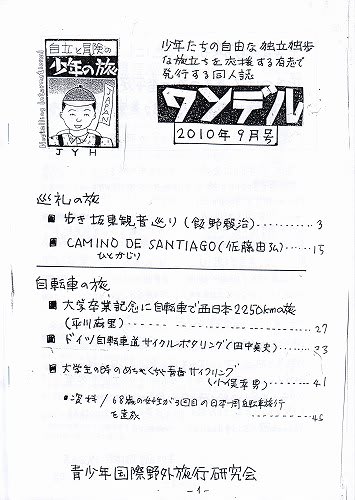
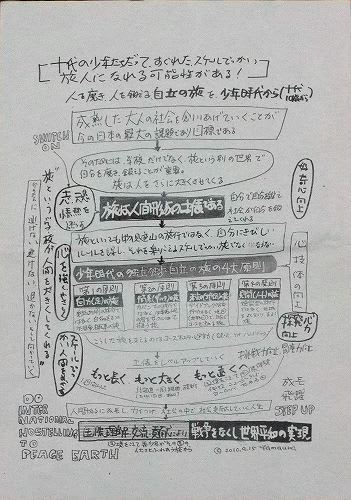
 。
。



















