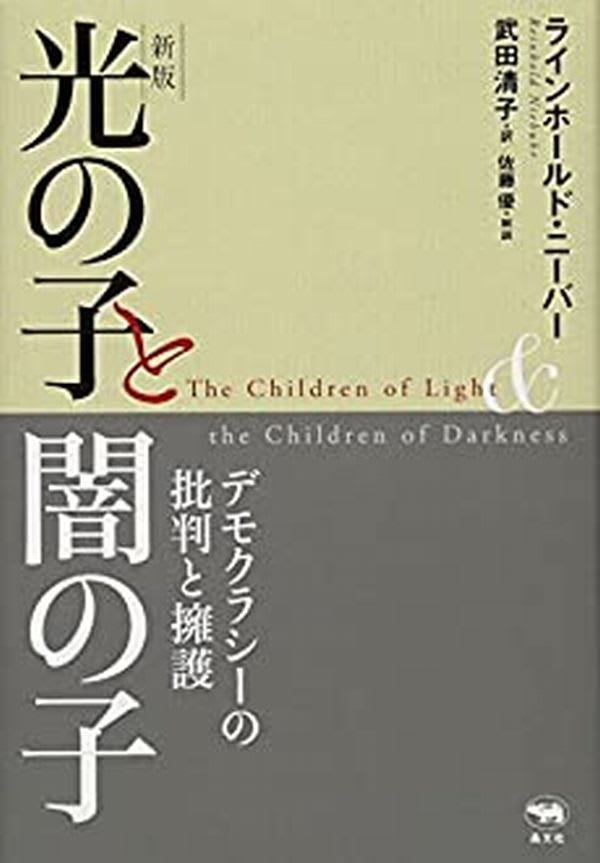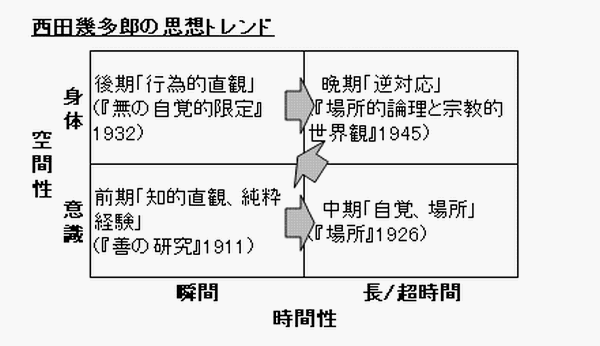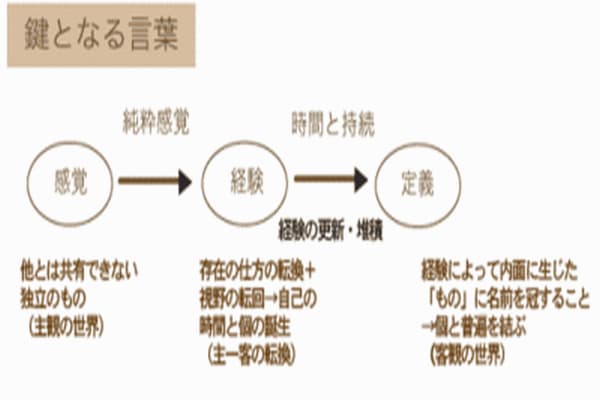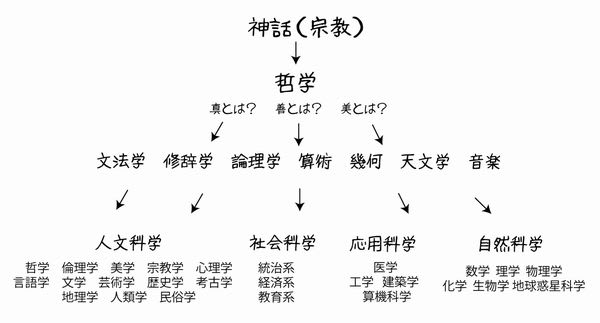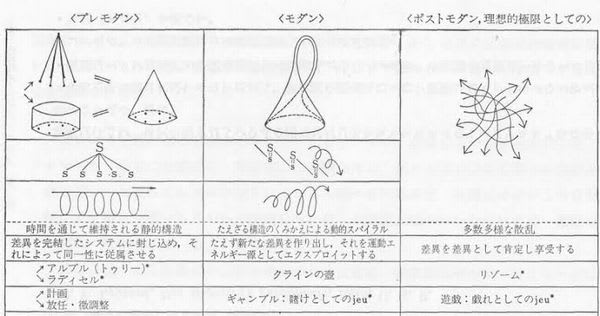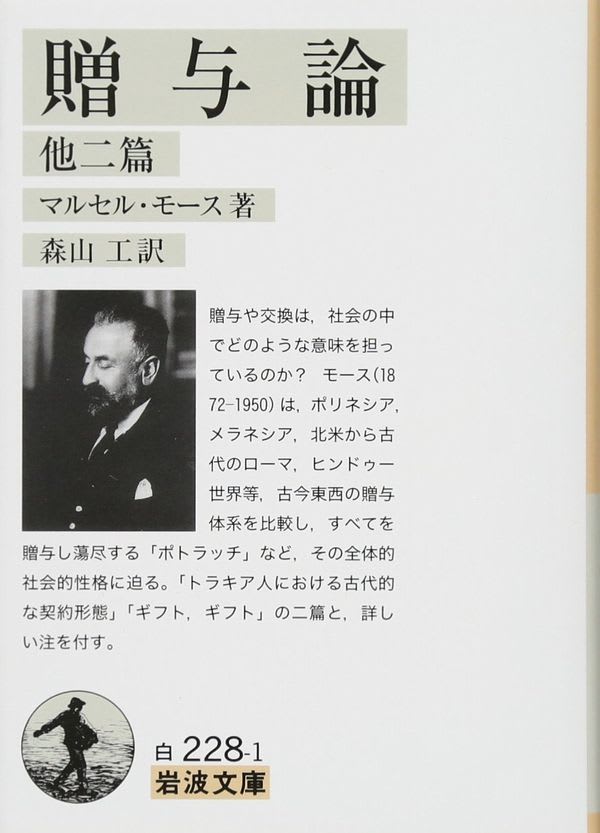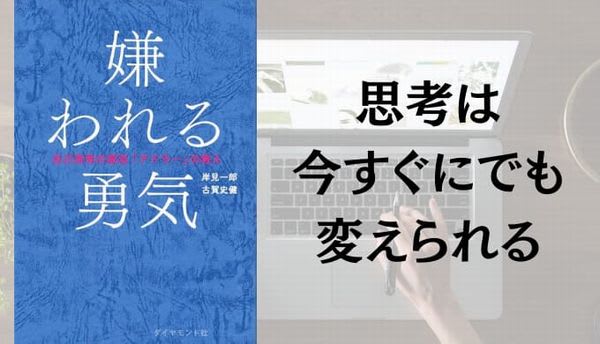🌸『魔の山』23(生きることを考える)
☆私自身、すぐ忘れますが,書いている時
*間違かも知れませんが、それなりに少し理解出来ているつもりです?
☆肉体に死が追るほど豊かになりゆく精神世界
☆生きていくことの不条理さ
☆「いかに生きるか」という問いへ開かれる
☆「いかに生きるか」という問いへ開かれる
☆決闘を回避した者に浴びせかける
*思慮深い、穏健な思想に対して「卑怯者!」という絶叫
*絶望的な方法で、問題を破滅的に「打開」しようとする
*欲動が投げ掛ける、暗く、激しい愚弄と挑発の声である
☆著者、トーマス・マン
⛳『魔の山』著者トーマス・マンのプロフィール
☆マンが『魔の山』の着想を得たのは、病身の妻を見舞いに行った先
⛳『魔の山』著者トーマス・マンのプロフィール
☆マンが『魔の山』の着想を得たのは、病身の妻を見舞いに行った先
*サナトリウムの見舞いより執筆をスタート
☆『魔の山』は、ドイツを代表する教養小説として筆頭にあげられる
☆『魔の山』は、ドイツを代表する教養小説として筆頭にあげられる
☆ドイツは、第一次世界大戦という世界戦争を経て
*西洋文明の没落の危機に瀕していた
☆ドイツでは、思索を通して自己形成を行う潮流が起こっていた
☆主人公の青年の生き方
*思索を通じて人間性を深め、これからの世界で
*「人間はどう生きるべきか」の問いに直面するドイツ市民へ
*大きな影響を与えた
⛳『魔の山』の概要
☆サナトリウムを見舞いに訪れたカストルプ(主人公)
*自身も結核に侵されていることを知る
*その後の7年間をサナトリウムで過ごす
☆サナトリウム内部での暮らしを通し
*世界各国から集まるさまざまな思想やバックボーンの持ち主たち
*世界各国から集まるさまざまな思想やバックボーンの持ち主たち
*仲間交わるカストルプは、次第に思索を深めていく
*そうした精神の出会いは、新たな局面へと展開していく
☆第一次世界大戦が勃発した
*カストルプは出征のためにサナトリウムを去る
*当時、結核は死の病であった
*戦争もまた、死が常に隣人となる経験である
*当時、結核は死の病であった
*戦争もまた、死が常に隣人となる経験である
☆生まれた以上逃れがたい「死」というものが肉体に間近に迫る
☆カストルプの精神は思索の世界を葛藤する
*葛藤の景色を豊かなものにしていった
☆世界大戦を生き延びた人々の多く
*カストルプの精神のに、自身の姿を重ねた
⛳『魔の山』でマンの描いた物語世界
☆マンが抱えていた「自分はどう生きるか」
*個人としての悩みから人間全体に向けた
*「どう生きるか」という普遍的な問いかけた
☆この作品は今もなお「教養小説」とまで呼ばれている
☆世紀をまたぎ読み継がれている
☆答えのない問いを問い続ける知的体力
☆答えのない問いを問い続ける知的体力
*それが、教養の正体である
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
⛳出典、『世界の古典』

『魔の山』23(生きることを考える)