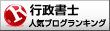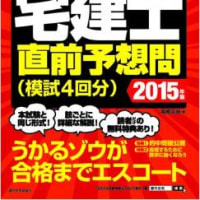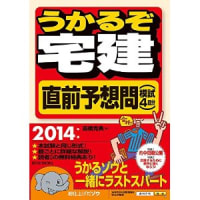今回は、11条です。地代等増減請求権です。
この請求権は、試験ではよく借家関係ででますが、借地の地代でも同じ内容ですから、ここで学習します。
民法には、特に賃料については規定ありません。
それは、賃料は国から強制されて決めるものではなく、当事者の合意で自由に決めないとマズイと思っているからです。
資本主義社会のルールですね。
では、条文を見てみましょう。
・・・・・・
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
・・・・・・
長いですが、意外と簡単です。
では、なぜこのような条文ができたかです。
まず1項をもう一度読んでみてください。
ここで言っていることを自分なりの表現で表すといいでしょう。
それは、賃料については、本来合意で決めるのだけど、これを決めたのは、もう30年前のことだよね。
そのときの賃料と今の近隣の賃料とは地価が上がって、釣り合っていないんだ。
そこで、賃貸人は、賃借人に賃料の変更を求めたんだけど、応じてくれないんだ。本来は合意で賃料を決めるんだからね。
でも、やっぱり不公平だよね、事情が変わっても変更できないのは・・・。
そこで、本当におかしかったら、一方的に賃料を変更できる権利を認めてもいいし、むしろそれが公平だよね。
ということで、1項の「地代等増減額請求権」つまり一方的に形成できる権利を規定したのです。
つまり、相手方の同意がいらない制度です。
もちろん、もともと増額する権利を認めない旨の特約があれば、できません。
一方、減額しない特約は、ここから解釈してできませんね。この法律の趣旨である、借主保護から見てもそう思いますね。
では、ここまでの知識を得たところで、もう一度条文の1項を読み返してみると、非常によく分かるでしょう。
最初に見たときには、長いし、難しそうだし、いやだなあ、と思った方も、食わず嫌いだと言うことで、やはり積極的に条文をこれからも読んでみてください。
では、チョットながくなったので、今回はこれで休憩しましょう。
続きは、また次回で・・。
つづく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

この請求権は、試験ではよく借家関係ででますが、借地の地代でも同じ内容ですから、ここで学習します。
民法には、特に賃料については規定ありません。
それは、賃料は国から強制されて決めるものではなく、当事者の合意で自由に決めないとマズイと思っているからです。
資本主義社会のルールですね。
では、条文を見てみましょう。
・・・・・・
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
・・・・・・
長いですが、意外と簡単です。
では、なぜこのような条文ができたかです。
まず1項をもう一度読んでみてください。
ここで言っていることを自分なりの表現で表すといいでしょう。
それは、賃料については、本来合意で決めるのだけど、これを決めたのは、もう30年前のことだよね。
そのときの賃料と今の近隣の賃料とは地価が上がって、釣り合っていないんだ。
そこで、賃貸人は、賃借人に賃料の変更を求めたんだけど、応じてくれないんだ。本来は合意で賃料を決めるんだからね。
でも、やっぱり不公平だよね、事情が変わっても変更できないのは・・・。
そこで、本当におかしかったら、一方的に賃料を変更できる権利を認めてもいいし、むしろそれが公平だよね。
ということで、1項の「地代等増減額請求権」つまり一方的に形成できる権利を規定したのです。
つまり、相手方の同意がいらない制度です。
もちろん、もともと増額する権利を認めない旨の特約があれば、できません。
一方、減額しない特約は、ここから解釈してできませんね。この法律の趣旨である、借主保護から見てもそう思いますね。
では、ここまでの知識を得たところで、もう一度条文の1項を読み返してみると、非常によく分かるでしょう。
最初に見たときには、長いし、難しそうだし、いやだなあ、と思った方も、食わず嫌いだと言うことで、やはり積極的に条文をこれからも読んでみてください。
では、チョットながくなったので、今回はこれで休憩しましょう。
続きは、また次回で・・。
つづく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では、また。
 | 2017年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ) |
| 高橋克典等 | |
| 住宅新報社 |
 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |