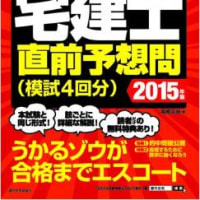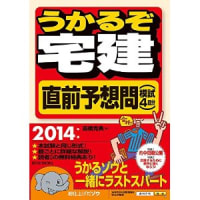すき間時間でR2年行政書士試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問35・特別養子・・・。
最後の問題です。特別養子の改正点があったので、出題されたのでしょう。
その点は、出題されてませんが・・・。
養子となる者の年齢の817条の5(改正)
1 817条の2に規定する請求の時に15歳(以前は6歳)に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が15歳(以前は8歳)に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
・・・・・
問35 民法 親族
特別養子制度に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア.特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。
イ.特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。
ウ.すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。
エ.特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。
オ.特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。
1.ア・ウ 2.ア・オ 3.イ・ウ 4.イ・エ 5.ウ・オ
・・・・・
肢アですが、誤りですね。
普通養子は、合意ですが、この特別養子は、家庭裁判所がイニシアティブをもって、一定の要件があるときは、養親となる者の請求により、「実方の血族との親族関係が終了」する縁組を成立させることができます。
子供のために、特別養子縁組は、家庭裁判所において審判の確定により成立し、効力を生ずるわけです。 実父母からの請求ではできないとわかりましたか。
ここから組合せですから、肢1と2が消去できます。
肢イですが、正しいですね。
養親となる者は、「配偶者のある者」でないとダメです。
さらに年齢については、原則的には25歳に達しない者は、養親となることができません。しかし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していなくても、その者が20歳に達しているときはokです。
そうすると、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならないということになります。
イが該当する、肢3か4になります。肢5は消去できます。
肢ウは、誤りです。
改正点の一部です。普通養子は15歳以上でできますから、特別養子は15歳未満となります。
しかし、養子となる者が15歳に達している場合もありますから、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならないことにしています。
通常は15歳に達していない場合ですから、その者の同意は不要です。すべてではありません。
肢ウが×と自信をもって判断できれば、肢3(肢5も)消去でき、この段階で肢4が正解となります。
肢エですが、正しいです。
これが普通養子と特別養子の違いですから、絶対に覚えている点です。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了します。
特別養子縁組は、その成立により、従前の親子関係等を終了させる縁組であり、特別養子縁組成立後は、実父母の相続人となる資格が当然に失われます。
一方、普通養子は、実父母の相続人にもなれるのですね。二重取りできます。
肢オですが、誤りです。
特別養子縁組の解消は、簡単には認められません。
認めるのは、養子の利益のため特に必要があると認めるときで、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。
それは、①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。かつ、②実父母が相当の監護をすることができること、の両方を満たしていることです。
養親からの請求ではできないことがわかりましたか。
でもちょっと困るのは、①には該当するが、②には該当しない場合は解消できず、どうすればいいんでしょうか。かわいそうですもんね。そういう問題が実務ではあります。
本肢は、①または②となっている点で、一応誤りとわかるでしょう。
では、また。

 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

最後の問題です。特別養子の改正点があったので、出題されたのでしょう。
その点は、出題されてませんが・・・。
養子となる者の年齢の817条の5(改正)
1 817条の2に規定する請求の時に15歳(以前は6歳)に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が15歳(以前は8歳)に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3 養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
・・・・・
問35 民法 親族
特別養子制度に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア.特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。
イ.特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。
ウ.すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。
エ.特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。
オ.特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。
1.ア・ウ 2.ア・オ 3.イ・ウ 4.イ・エ 5.ウ・オ
・・・・・
肢アですが、誤りですね。
普通養子は、合意ですが、この特別養子は、家庭裁判所がイニシアティブをもって、一定の要件があるときは、養親となる者の請求により、「実方の血族との親族関係が終了」する縁組を成立させることができます。
子供のために、特別養子縁組は、家庭裁判所において審判の確定により成立し、効力を生ずるわけです。 実父母からの請求ではできないとわかりましたか。
ここから組合せですから、肢1と2が消去できます。
肢イですが、正しいですね。
養親となる者は、「配偶者のある者」でないとダメです。
さらに年齢については、原則的には25歳に達しない者は、養親となることができません。しかし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していなくても、その者が20歳に達しているときはokです。
そうすると、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならないということになります。
イが該当する、肢3か4になります。肢5は消去できます。
肢ウは、誤りです。
改正点の一部です。普通養子は15歳以上でできますから、特別養子は15歳未満となります。
しかし、養子となる者が15歳に達している場合もありますから、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならないことにしています。
通常は15歳に達していない場合ですから、その者の同意は不要です。すべてではありません。
肢ウが×と自信をもって判断できれば、肢3(肢5も)消去でき、この段階で肢4が正解となります。
肢エですが、正しいです。
これが普通養子と特別養子の違いですから、絶対に覚えている点です。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了します。
特別養子縁組は、その成立により、従前の親子関係等を終了させる縁組であり、特別養子縁組成立後は、実父母の相続人となる資格が当然に失われます。
一方、普通養子は、実父母の相続人にもなれるのですね。二重取りできます。
肢オですが、誤りです。
特別養子縁組の解消は、簡単には認められません。
認めるのは、養子の利益のため特に必要があると認めるときで、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができます。
それは、①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。かつ、②実父母が相当の監護をすることができること、の両方を満たしていることです。
養親からの請求ではできないことがわかりましたか。
でもちょっと困るのは、①には該当するが、②には該当しない場合は解消できず、どうすればいいんでしょうか。かわいそうですもんね。そういう問題が実務ではあります。
本肢は、①または②となっている点で、一応誤りとわかるでしょう。
では、また。

 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |