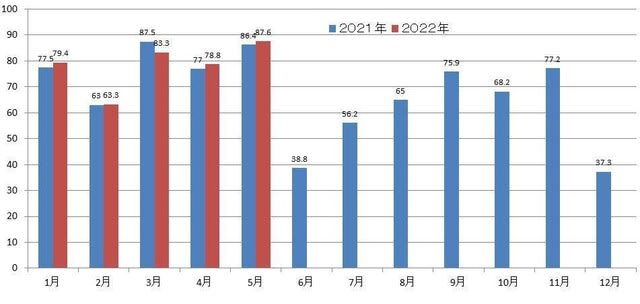前回は、2017年の春闘の際、連合と経団連はともに少子高齢化・人口減少を逆手にとってイノベーションと生産性向上で日本経済を元気にしようという提言をしたこと、しかし政府は森友と加計にかまけていて労使の発言にはまったく関心を示さず、せっかくのチャンスを逃してしてしまったことを書きました。
安倍政権は「決める政治」をモットーに、何でも自分で決めてやるのがいいと思っていたようでした。しかしその結果がアベノミクスの失敗、日本経済の停滞を生み、残ったのは日銀の異次元金融緩和だけで、それが今の円安につながるという殆ど実りのないものになってしまっているという事のようです。
もうアベノミクスも廃物でしょうし、この際2017年の労使の提言を改めて思い起こし、日本経済を支える産業界の代表である労使の意欲を汲み直し、政府は、労使が共通に持つ日本経済再建の意欲とその政策立案・実行の能力に期待し、それを支える国としての環境整備を重点に、「政労使」三者協力して新しい日本経済の成長発展路線を実現する姿勢を持てば、結果は必ず出るだろうと思っている方も多いのではないでしょか。
そのために必要なことはいろいろあると思いますが、先ず一番大事なことは、国民がこれで日本も変わるなという意識を持てるようなビジョンを示すことでしょう。
「一億総活躍」の様な根っこのない「造花」ではなく、産業の原動力である「労使」という人間集団が、主体的な意思を以て基盤を担うという基礎構造があって、その上に確りした構築物を築くという国を挙げての作業の目的はこれですと国民に明示することです。
例えば、表題に挙げましたように、日本経済衰退の元凶である、2052年には日本の人口は1億人を切リ、その後8000万人なるといった悲観論を逆手にとって、30年後には、たとえ人口が1億人になっても、却って、こんなに快適で余裕のある日本社会が実現できるという目標を、政労使三者が共有し、国民の将来不安・老後不安を払拭する事でしょう。
そんな事が出来る筈がないという意見もあるでしょう。確かに、今迄の後追いのパッチワークでは絶対に出来ません。しかし考え方を変えればそれは十分可能です。
具体的に言いますと、1億総中流と言われた1980年代のGDPはやっと400兆円になったところです、今は550兆円です。消費者物価は2割弱上っていますが、GDPは4割弱増えています。そして人口は減っています。
つまり、あの頃より今の1人当たりGDPは大分多いのです。
それなのにいま日本は貧しいですね。何かおかしくないでしょうか。
答えは実は既にはっきりしているのです。原因は、格差社会化が進んだからです。政府は貧しい人、貧しい世帯を大きく増やしてしまったのです。
という事は、今でも格差社会化を是正すれば、日本は結構豊かな国なのです。
今、政府がやっていることは、格差拡大の結果生まれた貧困層を(コロナ問題もあり)何とか救おうと、赤字国債を発行して、補助金、給付金を配るといったことですが、そんな後追いの弥縫策で、格差社会が是正されることはあり得ません。
格差社会化を止め、更に是正していくには、日本経済の社会構造そのものを組み替えていかなければならないでしょう。
それには、政府は、北欧型の社会なども参考に、日本らしい再分配政策を根本的に確立する事、産業界は、これまでの非正規社員の拡大などの反省に立って、日本社会に似合う格差の少ない人事賃金制度などを労使の協力で再構築する必要があるでしょう。
日本の人口が1億人になるまでには20年あります(今の推計で)。人口は減ってもGDPは増えるでしょう。
その結果は、30年後には、余裕のある快適な社会が実現しているはずです。すべては、先ず政府があるべき本来の政策に目覚め、労使と協力していかに賢明に努力するかにかかっているという事ではないでしょうか。
安倍政権は「決める政治」をモットーに、何でも自分で決めてやるのがいいと思っていたようでした。しかしその結果がアベノミクスの失敗、日本経済の停滞を生み、残ったのは日銀の異次元金融緩和だけで、それが今の円安につながるという殆ど実りのないものになってしまっているという事のようです。
もうアベノミクスも廃物でしょうし、この際2017年の労使の提言を改めて思い起こし、日本経済を支える産業界の代表である労使の意欲を汲み直し、政府は、労使が共通に持つ日本経済再建の意欲とその政策立案・実行の能力に期待し、それを支える国としての環境整備を重点に、「政労使」三者協力して新しい日本経済の成長発展路線を実現する姿勢を持てば、結果は必ず出るだろうと思っている方も多いのではないでしょか。
そのために必要なことはいろいろあると思いますが、先ず一番大事なことは、国民がこれで日本も変わるなという意識を持てるようなビジョンを示すことでしょう。
「一億総活躍」の様な根っこのない「造花」ではなく、産業の原動力である「労使」という人間集団が、主体的な意思を以て基盤を担うという基礎構造があって、その上に確りした構築物を築くという国を挙げての作業の目的はこれですと国民に明示することです。
例えば、表題に挙げましたように、日本経済衰退の元凶である、2052年には日本の人口は1億人を切リ、その後8000万人なるといった悲観論を逆手にとって、30年後には、たとえ人口が1億人になっても、却って、こんなに快適で余裕のある日本社会が実現できるという目標を、政労使三者が共有し、国民の将来不安・老後不安を払拭する事でしょう。
そんな事が出来る筈がないという意見もあるでしょう。確かに、今迄の後追いのパッチワークでは絶対に出来ません。しかし考え方を変えればそれは十分可能です。
具体的に言いますと、1億総中流と言われた1980年代のGDPはやっと400兆円になったところです、今は550兆円です。消費者物価は2割弱上っていますが、GDPは4割弱増えています。そして人口は減っています。
つまり、あの頃より今の1人当たりGDPは大分多いのです。
それなのにいま日本は貧しいですね。何かおかしくないでしょうか。
答えは実は既にはっきりしているのです。原因は、格差社会化が進んだからです。政府は貧しい人、貧しい世帯を大きく増やしてしまったのです。
という事は、今でも格差社会化を是正すれば、日本は結構豊かな国なのです。
今、政府がやっていることは、格差拡大の結果生まれた貧困層を(コロナ問題もあり)何とか救おうと、赤字国債を発行して、補助金、給付金を配るといったことですが、そんな後追いの弥縫策で、格差社会が是正されることはあり得ません。
格差社会化を止め、更に是正していくには、日本経済の社会構造そのものを組み替えていかなければならないでしょう。
それには、政府は、北欧型の社会なども参考に、日本らしい再分配政策を根本的に確立する事、産業界は、これまでの非正規社員の拡大などの反省に立って、日本社会に似合う格差の少ない人事賃金制度などを労使の協力で再構築する必要があるでしょう。
日本の人口が1億人になるまでには20年あります(今の推計で)。人口は減ってもGDPは増えるでしょう。
その結果は、30年後には、余裕のある快適な社会が実現しているはずです。すべては、先ず政府があるべき本来の政策に目覚め、労使と協力していかに賢明に努力するかにかかっているという事ではないでしょうか。