27日(土)。わが家に来てから今日で2096日目を迎え、米議会が24日開いた公聴会で、司法省の内情を知る内部告発者が、トランプ大統領の元側近への求刑を軽くするよう検察官に求めたり、環境規制に慎重なトランプ氏が不満を漏らした翌日に自動車の燃費規制の調査を命じたりしたとして、バー司法長官を相次いで糾弾した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

アメリカの三権分立を守るためには高いバーを乗り越えなければならないようだ





昨日、夕食に「肉じゃが」を作りました やや味が濃いめでしたが、美味しかったです
やや味が濃いめでしたが、美味しかったです






昨日午後7時からサントリーホールで 東京交響楽団 第681回 定期演奏会 を聴きました 私が生のコンサートを聴くのは、3月21日に旧東京音楽学校奏楽堂で開かれたトリオ・アコードによる「ベートーヴェン『ピアノ三重奏曲 全曲演奏会 Ⅲ』以来なので97日ぶり、オーケストラのコンサートは2月28日に すみだトリフォニーホールで開かれた新日本フィルの「ルビー・シリーズ定期演奏会」以来なので実に119日ぶりです
私が生のコンサートを聴くのは、3月21日に旧東京音楽学校奏楽堂で開かれたトリオ・アコードによる「ベートーヴェン『ピアノ三重奏曲 全曲演奏会 Ⅲ』以来なので97日ぶり、オーケストラのコンサートは2月28日に すみだトリフォニーホールで開かれた新日本フィルの「ルビー・シリーズ定期演奏会」以来なので実に119日ぶりです 4か月もの間オケのコンサートを聴かなかったのはこの30年間で初めてだと思います
4か月もの間オケのコンサートを聴かなかったのはこの30年間で初めてだと思います

ホール前の広場ではチラシ配布会社の人がチラシを配っていますが、いつもは厚さが1センチ位あるのが、極めて薄いです。これも今の世相を反映しています 通常は30分前開場ですが、入場時の3密を避けるため、今回は1時間前の開場となっています
通常は30分前開場ですが、入場時の3密を避けるため、今回は1時間前の開場となっています
会場ロビーに入ると手指のアルコール消毒を求められ、サーモグラフィーで熱検知を受けます 3人の担当者がモニター画面を監視しています。6月号プログラムはテーブルから自分で取って、チケットの半券のもぎりは自分で行います
3人の担当者がモニター画面を監視しています。6月号プログラムはテーブルから自分で取って、チケットの半券のもぎりは自分で行います ホワイエでの飲食サービスとクロークは閉鎖されており、CD等の販売もありません。場内アナウンスは、①マスクの着用・咳エチケットへの協力、②ソーシャルディスタンシングの確保、③頻繁な手洗い・消毒の励行、④ブラボーの禁止―を求めています
ホワイエでの飲食サービスとクロークは閉鎖されており、CD等の販売もありません。場内アナウンスは、①マスクの着用・咳エチケットへの協力、②ソーシャルディスタンシングの確保、③頻繁な手洗い・消毒の励行、④ブラボーの禁止―を求めています
ホールに入ると、座席は隣の席が空くように「千鳥模様配置」になっています。したがって客の入りは1000人以下です
オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの東響の編成ですが、楽員同士の距離を保つため隣席と1メートルほど離れてスタンバイしています そのため、オケの規模も弦楽が10・8・6・4・3編成で、管打楽器を入れて総勢45人の小規模編成です
そのため、オケの規模も弦楽が10・8・6・4・3編成で、管打楽器を入れて総勢45人の小規模編成です 弦楽奏者は皆 グレー系のマスクを着用しています
弦楽奏者は皆 グレー系のマスクを着用しています
あらためての咳エチケットへの協力依頼などのアナウンスに次いで、コンマスの水谷晃が登場します 一礼し、その後、オケ全体に合図して全員が立ち上がって会場に向けて一礼します
一礼し、その後、オケ全体に合図して全員が立ち上がって会場に向けて一礼します これは今までの定期演奏会ではなかったことですが、もともと東響はリハーサルの開始にあたり指揮者に一礼してから練習に入る唯一のオケなので、そこは以心伝心 すぐに反応します
これは今までの定期演奏会ではなかったことですが、もともと東響はリハーサルの開始にあたり指揮者に一礼してから練習に入る唯一のオケなので、そこは以心伝心 すぐに反応します ステージ上の東響の楽員の顔ぶれを見て、久しぶりの再会に目頭が熱くなりました
ステージ上の東響の楽員の顔ぶれを見て、久しぶりの再会に目頭が熱くなりました
プログラムは①ベートーヴェン「プロメテウスの創造物」序曲 作品43、②同「ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37」、③メンデルスゾーン「交響曲 第3番 イ短調 作品56 ”スコットランド” 」です 演奏は②のピアノ独奏=田部京子、指揮=飯守泰次郎です
演奏は②のピアノ独奏=田部京子、指揮=飯守泰次郎です 当初、ピアノ独奏はイノン・バルナタン、指揮はユベール・スダーンでしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための出入国制限により来日中止となったため、二人の代演となったものです
当初、ピアノ独奏はイノン・バルナタン、指揮はユベール・スダーンでしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のための出入国制限により来日中止となったため、二人の代演となったものです
1曲目はベートーヴェン「プロメテウスの創造物」序曲 作品43です この作品はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が、ボッケリーニの甥のサルヴァトーレ・ヴィガーノの台本に基づき1800~1801年に作曲した「序曲、序奏と16曲の管弦楽曲」から成る作品の序曲です
この作品はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が、ボッケリーニの甥のサルヴァトーレ・ヴィガーノの台本に基づき1800~1801年に作曲した「序曲、序奏と16曲の管弦楽曲」から成る作品の序曲です
黒のマスクを着用した飯守泰次郎がマグマ大使のような足取りで指揮台に向かい、演奏に入ります 冒頭こそアインザッツの若干の乱れを感じましたが、そんなことは大した問題ではありません
冒頭こそアインザッツの若干の乱れを感じましたが、そんなことは大した問題ではありません 久しぶりにオーケストラの生の音を聴いて、弦楽器と管・打楽器の音が溶け合って身体に浸み渡ってくる感覚を思い出しました
久しぶりにオーケストラの生の音を聴いて、弦楽器と管・打楽器の音が溶け合って身体に浸み渡ってくる感覚を思い出しました このコンサートに懸ける東響の気迫が感じられる集中力に満ちた演奏でした
このコンサートに懸ける東響の気迫が感じられる集中力に満ちた演奏でした
2曲目はベートーヴェン「ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37」です この曲はベートーヴェンが1800年から1803年にかけて作曲、1803年4月5日にアン・デア・ウィーン劇場でベートーヴェン自身のピアノ独奏と指揮で初演されました
この曲はベートーヴェンが1800年から1803年にかけて作曲、1803年4月5日にアン・デア・ウィーン劇場でベートーヴェン自身のピアノ独奏と指揮で初演されました 第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「ラルゴ」、第3楽章「ロンド:アレグロ」の3楽章から成ります
第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「ラルゴ」、第3楽章「ロンド:アレグロ」の3楽章から成ります
ブロンズ系の華麗な衣装を身に着け、白のマスクを着用した田部京子が登場しピアノに向かいます 飯守氏の指揮で第1楽章が開始されますが、この曲はまだモーツアルトの影響下にあり、序奏が長く、ヒロインのピアノはなかなか出てきません
飯守氏の指揮で第1楽章が開始されますが、この曲はまだモーツアルトの影響下にあり、序奏が長く、ヒロインのピアノはなかなか出てきません その後、決然と田部の独奏が入ってきます。正統派という言葉を思い浮かべます
その後、決然と田部の独奏が入ってきます。正統派という言葉を思い浮かべます 奇をてらったところは一切ありません。カデンツァが素晴らしかった
奇をてらったところは一切ありません。カデンツァが素晴らしかった 第2楽章は冒頭のピアノによるモノローグがしみじみと心に沁みました
第2楽章は冒頭のピアノによるモノローグがしみじみと心に沁みました 第3楽章のロンドは一転、軽快で楽し気な楽想で、盤石なオケに支えられた田部の演奏は力強くも美しい演奏でした
第3楽章のロンドは一転、軽快で楽し気な楽想で、盤石なオケに支えられた田部の演奏は力強くも美しい演奏でした 演奏後、大きな拍手の中、田部と飯守は握手のジェスチャーをしてお互いの健闘を讃えました
演奏後、大きな拍手の中、田部と飯守は握手のジェスチャーをしてお互いの健闘を讃えました 鳴りやまない拍手に、田部はメンデルスゾーンの「無言歌集」第2集から「ベネツィアの小舟」をエレガントに弾き、プログラム後半に繋げ、再び大きな拍手を浴びました
鳴りやまない拍手に、田部はメンデルスゾーンの「無言歌集」第2集から「ベネツィアの小舟」をエレガントに弾き、プログラム後半に繋げ、再び大きな拍手を浴びました
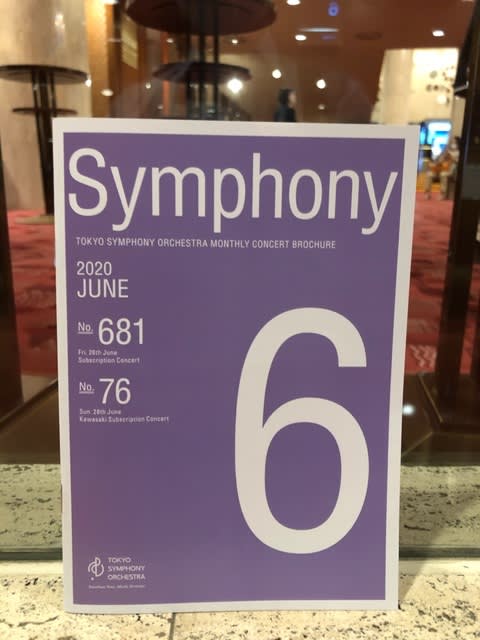
プログラム後半はメンデルスゾーン「交響曲 第3番 イ短調 作品56 ”スコットランド” 」です この曲はフェリックス・メンデルスゾーン(1809‐1847)が1829年から1842年にかけて作曲し、1842年3月3日にライプツィヒでメンデルスゾーン指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演されました
この曲はフェリックス・メンデルスゾーン(1809‐1847)が1829年から1842年にかけて作曲し、1842年3月3日にライプツィヒでメンデルスゾーン指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演されました 第1楽章「アンダンテ・コン・モト~アレグロ・ウン・ポコ・アジタート」、第2楽章「ヴィヴァーチェ・ノン・トロッポ」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ・ヴィヴァ―ティッシモ~アレグロ・マエストーソ・アッサイ」の4楽章から成ります
第1楽章「アンダンテ・コン・モト~アレグロ・ウン・ポコ・アジタート」、第2楽章「ヴィヴァーチェ・ノン・トロッポ」、第3楽章「アダージョ」、第4楽章「アレグロ・ヴィヴァ―ティッシモ~アレグロ・マエストーソ・アッサイ」の4楽章から成ります
飯守氏の指揮で第1楽章に入りますが、序奏部はメンデルスゾーンが20歳の時にスコットランドを訪れた際に、女王メアリー・スチュアートに想いを馳せてスケッチした12小節のコラールが採用されています 物悲しい旋律が会場を支配します。第2楽章は冒頭の吉野亜希菜のクラリネット独奏が冴えていました
物悲しい旋律が会場を支配します。第2楽章は冒頭の吉野亜希菜のクラリネット独奏が冴えていました 第3楽章は第1ヴァイオリンを中心とする弦楽アンサンブルが素晴らしい
第3楽章は第1ヴァイオリンを中心とする弦楽アンサンブルが素晴らしい 第4楽章は後半でのホルンを中心とするブラスセクションの分厚い演奏が印象的でした
第4楽章は後半でのホルンを中心とするブラスセクションの分厚い演奏が印象的でした また、全楽章を通じて、コンマスの水谷晃の渾身のリードが光りました
また、全楽章を通じて、コンマスの水谷晃の渾身のリードが光りました
終演後、水谷の合図でオケ全体で客席に一礼し、舞台袖に引き上げました メンバー全員が舞台から去っても拍手が鳴りやまず、飯守氏と水谷氏がカーテンコールに応えました
メンバー全員が舞台から去っても拍手が鳴りやまず、飯守氏と水谷氏がカーテンコールに応えました
代演となった飯守氏と田部さん、そして東京交響楽団の素晴らしいコンサートを聴くことができ、生きている喜びをあらためて感じました この日のコンサートは、東京交響楽団にとってコロナ禍明けの特別な演奏会になったと思いますが、それと同時に、聴衆の一人として、私にとっても忘れられない特別なコンサートになりました
この日のコンサートは、東京交響楽団にとってコロナ禍明けの特別な演奏会になったと思いますが、それと同時に、聴衆の一人として、私にとっても忘れられない特別なコンサートになりました
しかし、感傷に浸ってばかりはいられません 入場者を半分に制限することは赤字を意味します
入場者を半分に制限することは赤字を意味します いつまでもソーシャルディスタンシングを採りながらコンサートを続けていくことは出来ません
いつまでもソーシャルディスタンシングを採りながらコンサートを続けていくことは出来ません 全てのオーケストラにとって大きな悩みの種であると同時に、乗り越えなければならない高いハードルです
全てのオーケストラにとって大きな悩みの種であると同時に、乗り越えなければならない高いハードルです 私はこれからも東京交響楽団の会員をやめません。頑張って乗り越えて欲しいと思います
私はこれからも東京交響楽団の会員をやめません。頑張って乗り越えて欲しいと思います
















