7日(日)。昨夜、NHKのニュース7を観ていたら、ダニエル・バレンボイムがウィーン・フィルを指揮ぶりしてモーツアルト「ピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.537」を演奏するシーンが映し出されました 続いてベートーヴェン「交響曲第5番ハ短調」の冒頭部分が放映されました
続いてベートーヴェン「交響曲第5番ハ短調」の冒頭部分が放映されました アナウンスによると、聴衆は定員の20分の1以下の100人限定で、かなり余裕のある座席配置になっていました。3か月ぶりに 不完全ながら、いよいよウィーンが動き出しましたね
アナウンスによると、聴衆は定員の20分の1以下の100人限定で、かなり余裕のある座席配置になっていました。3か月ぶりに 不完全ながら、いよいよウィーンが動き出しましたね
さて、話は変わりますが、昨日の朝日朝刊のコラム「ことば/サプリ」が「スピリッツ」について解説していました 校閲センター・上田氏の解説を超訳すると、
校閲センター・上田氏の解説を超訳すると、
「新型コロナウイルス対策で使われる消毒用アルコールが品薄となり、代替品として、各地の酒造業者がアルコール濃度の高い『スピリッツ』の製造に乗り出している スピリッツは、大麦やブドウなどの醸造酒を加熱し、蒸発した成分を取り出す『蒸留』という工程を経てつくるお酒のこと
スピリッツは、大麦やブドウなどの醸造酒を加熱し、蒸発した成分を取り出す『蒸留』という工程を経てつくるお酒のこと ウォッカ、ジン、ラム、テキーラが4大スピリッツとされる。英語の spirit(s) には、蒸留酒の意味のほかに、『魂、霊、精神』の意味がある
ウォッカ、ジン、ラム、テキーラが4大スピリッツとされる。英語の spirit(s) には、蒸留酒の意味のほかに、『魂、霊、精神』の意味がある なぜお酒を指すようにもなったのか。堀田隆一・慶応大教授(英語史)によると、spirit の語源はラテン語の「息」。肉体に生命を吹き込む息が、同様に精神も吹き込むと考えられていた。一方、酒は新約聖書の記述に由来するものとして、西洋の諸言語で『生命の水』と呼ばれてきた。さらに、中世に錬金術師の実験により蒸留技術が生まれると、蒸留酒は『生命、精気を帯びた物質』として捉えられ、スピリッツと呼ばれるようになったと考えられる
なぜお酒を指すようにもなったのか。堀田隆一・慶応大教授(英語史)によると、spirit の語源はラテン語の「息」。肉体に生命を吹き込む息が、同様に精神も吹き込むと考えられていた。一方、酒は新約聖書の記述に由来するものとして、西洋の諸言語で『生命の水』と呼ばれてきた。さらに、中世に錬金術師の実験により蒸留技術が生まれると、蒸留酒は『生命、精気を帯びた物質』として捉えられ、スピリッツと呼ばれるようになったと考えられる 」
」
得体のしれない果実を原料にして前例のないスピリッツを作ろうとする進取の精神を「フロンティア・スピリッツ」と言う ウソですけど
ウソですけど
ということで、わが家に来てから今日で2076日目を迎え、フェイスブック社のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者は5日、黒人男性の暴行死事件に関するトランプ大統領の「略奪が始まれば銃撃も始まる」という投稿を容認し、社内外から強い批判を浴びたことを踏まえ、国家による武力行使などにまつわる投稿への規制を見直すと表明した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

言論の自由をはき違えたトランプから反撃があるだろう 今後 本気度が試される





ほぼほぼ1年ぶりくらいにタワーレコード新宿店に行きました これまで控えていたのは、コロナのせいだけではなく、ただ見るだけと心に誓って出かけるのに、いつの間にか何枚か買って帰ってくるのが常だったからです
これまで控えていたのは、コロナのせいだけではなく、ただ見るだけと心に誓って出かけるのに、いつの間にか何枚か買って帰ってくるのが常だったからです しかし、今回はあるCDを買うという明確な目的をもって出かけました
しかし、今回はあるCDを買うという明確な目的をもって出かけました JR新宿駅東南口すぐ近くのタワーレコードが入居するビルの10階に行ってみたら、以前クラシックとジャズのCD売場だったフロアはLPレコード売場に変身していました
JR新宿駅東南口すぐ近くのタワーレコードが入居するビルの10階に行ってみたら、以前クラシックとジャズのCD売場だったフロアはLPレコード売場に変身していました クラシックに限らずあらゆるジャンルのLPレコードが売られていました。LPのリバイバル・ブームが続いているようです
クラシックに限らずあらゆるジャンルのLPレコードが売られていました。LPのリバイバル・ブームが続いているようです 誘惑の危険を感じたので、レコードを見ないで9階まで戻ったら やっとクラシック・コーナーを発見しました
誘惑の危険を感じたので、レコードを見ないで9階まで戻ったら やっとクラシック・コーナーを発見しました 以前はフロアの半分を占めていたのに、今はほんの一角に押し込められている感じです
以前はフロアの半分を占めていたのに、今はほんの一角に押し込められている感じです クラシック人口は増えるどころか減っているのだろうか、と心配になりました
クラシック人口は増えるどころか減っているのだろうか、と心配になりました
今回の目的はテオドール・クルレンティス指揮ムジカエテルナによるモーツアルトの歌劇『フィガロの結婚』のCDを買うことです このCDを買おうと思ったキッカケは、最近読んだ加藤浩子著「オペラで楽しむヨーロッパ史」の「あとがき」に「これは革命の音楽だ。2014年の秋、テオドール・クルレンティスが指揮する『フィガロの結婚』のCDを聴いた瞬間、『フィガロの結婚』という作品を取り囲む景色が一変した
このCDを買おうと思ったキッカケは、最近読んだ加藤浩子著「オペラで楽しむヨーロッパ史」の「あとがき」に「これは革命の音楽だ。2014年の秋、テオドール・クルレンティスが指揮する『フィガロの結婚』のCDを聴いた瞬間、『フィガロの結婚』という作品を取り囲む景色が一変した 本書の直接的な出発点はそこにある。あの時、モーツアルトの三大オペラを『フランス革命』という視点から見直したいという考えが芽生えたのだった」と書かれているのを読んだことです
本書の直接的な出発点はそこにある。あの時、モーツアルトの三大オペラを『フランス革命』という視点から見直したいという考えが芽生えたのだった」と書かれているのを読んだことです

オペラのオーソリティに1冊の本を書こうとまで思わせた演奏とはどんなものか、それを知りたくてテオドール・クルレンティス指揮ムジカエテルナによるモーツアルト『フィガロの結婚』のCD(3枚組)を買う決心をしたのです ちなみに歌手陣は一人も知りません
ちなみに歌手陣は一人も知りません

すぐ近くにあった『ドン・ジョバンニ』(3枚組)の歌手を見たら、昨年11月の新国立オペラ『椿姫』でタイトルロールを歌ったギリシャ生まれのソプラノ、ミルト・パパタナシュがドンナ・アンナを歌っているので、これも買うことにしました 
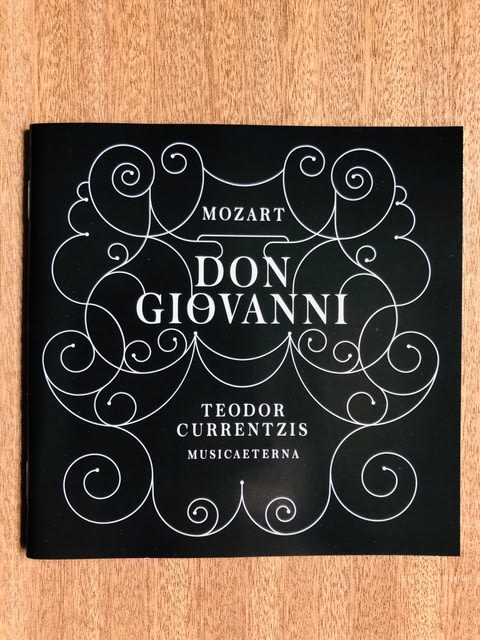
また、『レクイエム』も近くにあったので、思わず買ってしまいました

ほら、こうやって3枚買うつもりが、いつの間にか7枚も買っている だからCDショップに行くのはいやなのです
だからCDショップに行くのはいやなのです





テオドール・クルレンティスはギリシャ生まれ。1990年代はじめにサンクト・ペテルブルク音楽院で指揮法を学び始めました 音楽院ではヴァレリー・ゲルギエフ、セミヨン・ビシュコフなど著名な指揮者を育てたイリヤ・ムーシンに師事しています
音楽院ではヴァレリー・ゲルギエフ、セミヨン・ビシュコフなど著名な指揮者を育てたイリヤ・ムーシンに師事しています 現在、ペルミ国立オペラ・バレエ劇場 芸術監督、アンサンブル・ムジカエテルナおよびムジカエテルナ室内合唱団(ともに2004年創設)の芸術監督を務めています
現在、ペルミ国立オペラ・バレエ劇場 芸術監督、アンサンブル・ムジカエテルナおよびムジカエテルナ室内合唱団(ともに2004年創設)の芸術監督を務めています
家に帰って、さっそくテオドール・クルレンティス指揮ムジカエテルナによるモーツアルトの歌劇『フィガロの結婚』のCDを聴いてみました
この演奏の大きな特徴は、まず第一に古楽器を使用することで、強弱が激しいメリハリのある演奏を実現していることです そして、歌手の歌うアリアはノンビブラートで歌われる一方、装飾が加えられていることです
そして、歌手の歌うアリアはノンビブラートで歌われる一方、装飾が加えられていることです これはモーツアルトの時代には普通に歌われていたことで、聴いて違和感を感じるのは、われわれが譜面通りの歌唱に慣れているからです
これはモーツアルトの時代には普通に歌われていたことで、聴いて違和感を感じるのは、われわれが譜面通りの歌唱に慣れているからです こうした一連の試みが、スピード感に溢れ、生き生きとした演奏を可能にしていると言えます
こうした一連の試みが、スピード感に溢れ、生き生きとした演奏を可能にしていると言えます
CDジャケットの解説書の中に、クルレンティスへのインタビュー「なぜこの録音が作られたか」が載っています 彼はインタビューの最後にこう語っています
彼はインタビューの最後にこう語っています
「演奏とは、1回1回 子供を孕んで産み落とすようなものでなくてはならない、というのが私の信条です 奇跡が起こるのを目の当たりにする時が来るまで、夢見ながら 待たなくてはなりません
奇跡が起こるのを目の当たりにする時が来るまで、夢見ながら 待たなくてはなりません 音楽についてはそんなふうに考えないと、音楽の一番大切な部分を見失ってしまうことになります。音楽はただの職業でもなければ再生産でもありません。音楽は使命なんです
音楽についてはそんなふうに考えないと、音楽の一番大切な部分を見失ってしまうことになります。音楽はただの職業でもなければ再生産でもありません。音楽は使命なんです 」
」
ムジカエテルナは、ダーチャ(ロシア特有の田舎の邸宅)で数日間、共同体のような生活を送ります 夜通し読書会、映画会、詩の朗読、舞踏の勉強会、ディスカッション、リハーサルや録音まで行っています
夜通し読書会、映画会、詩の朗読、舞踏の勉強会、ディスカッション、リハーサルや録音まで行っています クルレンティスとムジカエテルナの楽員たちは、このような特別な時間を共にしながら 奇跡が起こるのを待ち、その瞬間を捉えて演奏に臨み 使命を達成するのだと思います
クルレンティスとムジカエテルナの楽員たちは、このような特別な時間を共にしながら 奇跡が起こるのを待ち、その瞬間を捉えて演奏に臨み 使命を達成するのだと思います

















