あなたは羊か狼か、それとも牧羊犬か?
極限状況では心と身体になにが起きるのか?はたして人間は人を殺せるようになるのか?
戦闘の心理と生理について徹底的に研究した衝撃の問題作
名著『戦争における「人殺し」の心理学』待望の続編!
今度は、戦闘の心理と生理について学問的に研究していきたい。名をつけるとすれば「戦闘学」ぐらいだろうか。ジョージ・ワシントン
は「平和を望む者は戦争に備えなくてはならない」と戒めた。これはつまり、つねに戦士が必要だということだ。すぐれた戦士、勇士と
呼べる戦士。平和戦士は戦闘について学び、それに精通しなくてはならない。消防士が火事について学び、それに精通するように。それ
が本書の目的である。人々に奉仕する戦士たちに、本書が少しでも役に立つよう祈っている(「はじめに」より)
内容(「BOOK」データベースより)
著者について
学者、著述家、軍人、講演者として国際的に活躍。人間の攻撃性および暴力・暴力犯罪の原因という分野の専門家として世界的に知られて
いる。陸軍士官学校の心理学・軍事学教授であり、また陸軍レンジャーとしての豊かな経験もある。これらをもとにして新しい科学的研究
の分野を創設し、これに「殺人学(killology)」と名づけている。この分野において著者は革命的とも言える研究をおこない、戦争におけ
る殺人、戦争の心理学的代償、世界中でいま暴力犯罪をはびこらせている「ウイルス」の根本原因、および戦時・平時における暴力被害者
の治癒について、人々の理解を深めるために多大な貢献をしている。著書にピュリッツァー賞候補ともなった『戦争における「人殺し」の
心理学』(ちくま学芸文庫)などがある。
ローレン・W・クリステンセン(Loren W. Christensen)
護身術、不良グループ、白人優越論者による犯罪、警察官の生き残り、および警察の関わる致命的武力対決の心理学的影響に関する専門家
として知られる。29年間法執行の世界に身を置いたのち、オレゴン州ポートランド警察署を1997年に退職した。米国陸軍憲兵としてベトナ
ムで3年間勤務したこともある。警察による腕力および武力の使用に関する専門家として、州および連邦の裁判で証言している。著書に
{Deadly Force Encounters: What Cops Need to Know to Mentally and Physically Prepare for and Survive a Gunfight}(『致命的
武力対決――心身ともに銃撃戦に備え、生き残るために警官が知っておくべきこと』)[共著]など多数。
翻訳:安原和見(やすはら・かずみ)
1960年鹿児島県生まれ。東京大学文学部西洋史学科卒業。主な訳書にH・ストリーバー『2012』、T・ジェリッツェン『外科医』、
D・アダムス『銀河ヒッチハイク・ガイド』、D・グロスマン『戦争における「人殺し」の心理学』などがある。

















































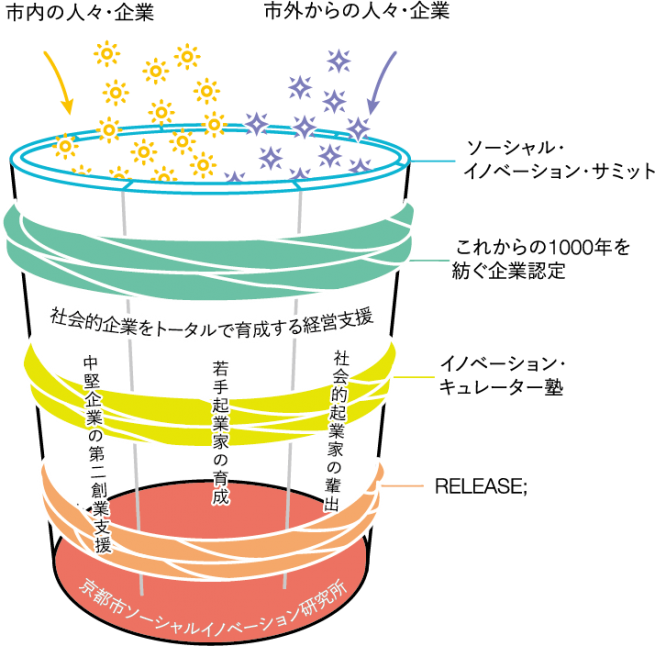

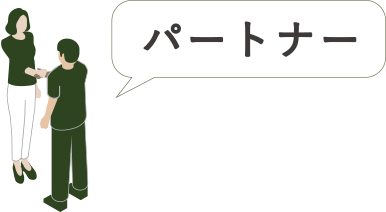
勉強になりました。
前作とは、そういう意味で、戦闘を乗り越えるためにどのような準備やアフターケアをしたら良いか書かれた本である。
多くの参考文献が記載されているが、その多くが邦訳されていないのが残念。
一応、職業的に武力を用いる必要のある人々の為のマニュアル本として書かれた「戦士学」の本なのだが、別に銃をぶっ放したり殴ったり蹴ったりすることとは無縁の生活を送っている読者にとっても、得るところは多々ある様に思う。これを「戦場」と限定せず、切迫する危険に直面したり高ストレス状況下で何かをしなければならなくなった場合、人間の心-身に何が起こるかを解説したものだと読み替えれば、事件だけではなく事故や災害等に見舞われた人々やその救助活動に従事する人々、緊張を強いられる職場で作業をしなければならない職業の人々等にとっても有益な知見が幾つもある。阪神大地震等の経験を通じて、被災後の被災者達の心のケアに関しては日本でもノウハウの蓄積が進んでいるとは聞くが、被災「中」のことも含めてパニクらずに済む方法を総合的に解説してくれる啓蒙書を誰か書いてくれないものだろうか?
私は著者の、ひたすら戦士を賛美する立場には賛同するものではないが(前著でも気になったが、現場で戦う人間が自分の行為の正当性を確信する必要があるのは理解出来るが、世界中に火種をバラ撒いて回っている張本人の一人に国際テロの脅威がどうのと説かれたくはない)、「理解は力」と云うその姿勢は共感出来る(その力がどういった目的でどう使われるか、と云うことは別問題としても)。事例の取り上げ方が一方的で比較群が皆無だったり、具体的なデータを基にした論証が屡々省略されていたりと、若干なりとも自分の頭で検討してみたい読者には些か物足りない部分もあるが、いざと云う時の心構えをしておきたいと望む読者であれば、本書を読むことは決して無駄にはならない筈である。
そして本書は、もっとカバーする範囲を広げて、兵士だけでなく警察等の命に関わる仕事をしている人達が、実際に人間に向けて銃を発砲しないといけないとき、逆に相手から発砲されるときにどのような反応を取るのかを心理学や生理学から説明している。
本書は前著とは違い、読者として兵士や警察等を想定しており、これらの職業についている人達が実際に戦場に出たり銃撃戦を経験したときに起こる現象(例えば時間が流れるのを遅く感じたりとか、記憶が飛ぶとか、大小失禁等々)は誰にでも起こりうることであり、正常な反応だということを予め理解しておいて欲しいというのが目的のようである。
したがって、一般読者向けに書かれていた前著と違い、本書ではところどころ一般読者が置き去りにされる箇所があるが、前著を興味深く読めた人であればそんなに問題無いのではないかと思う。
ハードカバー600ページ超というボリュームで、全編にわたって賛成できるかと言えばアメリカと日本の(また実際に軍人である著者と一般読者との)価値観の違いによって難しいが、前著と同じく興味深く読めた。
一応『戦場における「人殺し」の心理学』の続編という位置づけのようなので、前著を未読の方は先にそちらを読んでおいた方が良いと思われる(ただ、本文中に簡単に内容の説明があるのでそこまで順番に気をつかわなくても大丈夫)。
リファレンス解説書です。私の考えでは、誰にもで役に立ちます。
何名かの方も気づいている様ですが、戦場という異常な環境下における書き方をしては居ますが、人の死に関する
機会というのは現代社会では確実に増えているのです。
例えば、目の前での交通事故死・殺人などの犯罪・介護による肉親の死。
そうした誰にでも充分にありえる機会を柔軟に克服する為にも、こうした極論を事前に抑えて理解しておく必要が
是非にもあると思っています。
実例で言えば、目の前で苦しむ末期癌の肉親に対して延命処置を望むのか望まないのか、冷静な判断を下す事は
できますか?延命をすれば患者の命は伸びるが、苦しみをも続ける事になる。反して、延命を希望しなければ
患者を助けるという言い方が出来る一方で、悪く言うと自分が死刑判決をしたような後悔に襲われるかもしれません。
こうした決断には残念ながら誰もが遭遇する可能性があるのです…
能動的な殺人だけをついつい見がちになりますが、必然的・受動的な殺人にいきなり遭遇して自分のコントロールに
後になって苦しむよりは事前に紙上だけでも知識を押さえておく必要があると思います。
実際に私は介護で眼前にて身近な人の死に向かいつつあるので、姉妹本の 戦争における「人殺し」の心理学 (ちくま学芸文庫)
と共に自身・家族のメンタル・コントロールにこの本を役立てています。
倫理の問題は聖書では無秩序な暴力は戒めているが、国家からの使命により正当な理由がある場合には聖書は暴力ではなく正義と定義していることで兵士を説得する。極度の緊張状態については、近年模擬弾による練習で被弾の痛みを経験しながら戦闘を続行し任務遂行訓練をすることで緊張耐性ストレス耐性を養うことで解決する。
警官の業務も同様であり被疑者の犯罪行為に対する発砲は暴力ではなく正義であり、正義を実践するために実践同様の状況で緊張耐性訓練により任務遂行力の強化を図っている。
帰還兵や犯人射殺景観の心理面での事故対策が昨今重要な課題となっている。トラウマやPTSDは極度の緊張と敵や味方の死への直面と言った複数の過度のストレスが同時に発生し、精神面の整理ができずに長期にわたり殺戮現象の再現が発生する精神疾患であり、カウンセラーを通じて精神疾患防止策がとられている。
昨今の認知心理学の精神状態解明はかなり進んでおり、どのような事象が脳のどの部分にどのような障害を齎し、精神障害記憶の定着防止をどのように実現するかがかなり高確率で実現できるほど解明されている。
戦争や犯罪はないにこしたことはないが、著者が前半部分で指摘している通り青少年への暴力映像の過剰刺激で、暴力に対する罪悪認識が希薄化し無差別殺人等の凶悪犯の低年齢化が問題となる中、ゲーム業界はロビイストを使いゲームと犯罪の関連を否定し解決に至らない。
犯罪やテロとなる危険因子が一定割合で発生する以上、特殊部隊や警官の正当防衛は必須の防衛手段であり、高確率で適正に発動され、執行官の精神疾患を防止するプログラムの確実化が今後も進展されなければならない。