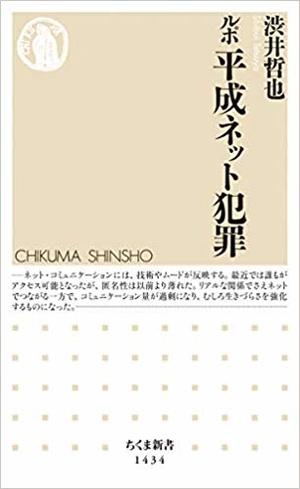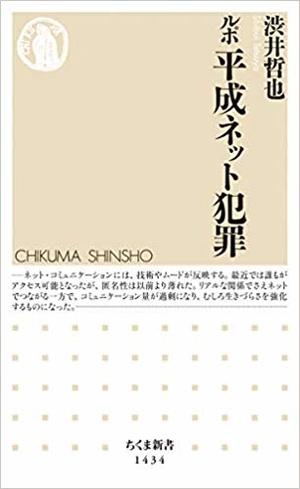事件殺人事件容疑者
渋井哲也
平成29年(2017年)10月、神奈川県座間市のアパートの一室で、若い男女9人の遺体が見つかった。逮捕された男は白石隆浩、逮捕当時27歳。ツイッターで自殺願望者に言葉巧みに近づき、自室に連れ込む手口だった。
レイプと所持金を奪う狙いがあったと、のちに供述している。
世間を恐怖に陥れたこの事件は、猟奇的殺人として海外メディアも報じた。そんな事件から、まもなく丸2年を迎える。
本稿は、容疑者・白石隆浩と面会をした、ジャーナリスト・渋井哲也によるものだ。
電車とバスを乗り継いで、東京・立川拘置所に行くと待合室でずいぶんと待たされた。面会室に行く前に、ペンとノート以外の荷物をロッカーにしまう。20分ほど待っただろうか、私の順番がきた。金属探知機を通り、「9番」の面会室のドアを開ける。数分ほどすると、白石隆浩被告が目の前に現れた。
「こんにちはーぁ」
白石被告は黒のジャージを着て、無精髭(ひげ)をはやしていた。神奈川県座間市のアパートの一室で、ツイッターで知り合った男女9人(うち7人は自殺願望があった)を殺害し、その遺体を遺棄した事件の被告人だ。逮捕時、報道で流された顔写真よりもややふっくらしている。その挨拶の仕方から、おどけたような振る舞いに見えた。
「ナンパ」という言葉に笑顔
私は自己紹介をし、持参した大学ノートに名前を書き、透明のアクリル板に押しつけた。面会希望のとき、名前を書いているので、初めて見る名前ではないはずだが、一度、手紙を出していることを伝えると、男は考え込んだ。
「うーん、手紙が多すぎてあまり覚えていない。あの、ネットナンパについて書いていた? あ、思い出しました」
私は当初、白石は“ネットナンパ師”ではないかと思っていた。ネット・コミュニケーションの経験と、事件取材などを経て、死にたい感情を持っている女性をナンパするのは比較的、たやすいのではないかと感じていた。自殺やメンタルヘルスをテーマにしたコミュニティーでは、ユーザー同士は心理的距離が近くなる。こうした特性を利用するナンパ師もいると聞く。
白石は、ナンパというワードが出たせいか笑顔になった。その表情は、9人を殺害し、死体を損壊した犯人と、同一人物であるとは思えない。それだけに、ただただ、事件のことを聞きたいという衝動に駆られる。
しかし事件のことを聞きたければ、お金を要求してくる、という報道がされている。そんな人間が、ストレートに話を聞いても答えるはずもない。私は、事件そのものを聞けない制約を持ちながら、いかに事件の周辺部を聞き出すかを考えていた。
男がどのようにインターネットを使ってきたのかを聞き、事件について考えようと思った。拙著『ルポ 平成ネット事件』(ちくま新書)を書くことを前提とした取材のためだ。
ネットナンパは17歳から
白石がケータイを持ち始めたのは中学2年生のころだったという。このときからインターネットを始めた。今の時代、特に早いほうではない。
白石容疑者、中学の卒業アルバムより
すべての写真を見る
「自分で欲しいと言ったわけではないです。塾へ行くときに、親から持たされたんです」
その後、親から与えられたケータイで、さまざまなネットサービス、電子掲示板やチャットを使っていく。そしてツイッターとの出会う。白石が事件で利用していたのは、主にツイッターだった。いつから使うようになったのか。
「風俗の斡旋をしていたときに、これは使えるなと思った。相性というよりも集まりがいい。仕事を求める人からの反応がいい。DM(ダイレクトメッセージ)でも“仕事がしたい”とくる。これは犯罪に使えるなと思ったんですよ」
では、いつからネットナンパを始めたのだろうか。
「17歳からですよ」
「コツはあるの?」
「叩き上げですね。数打つことですよ。お互いに写真を見せ合ったりしていたんです。もう慣れていましたね」
ナンパをするとき、何かゴールを設定していたのだろうか。
「そのときどきで目標を持っていましたね。エッチしたいだけか、それとも、(風俗店など斡旋〈あっせん〉をする)仕事なのか……。あ、仕事とナンパだけか」
彼の表情、そこになんの後悔も感じられない。むしろ、懐かしんでるような話し方だ。
スカウトマン時代、白石容疑者を危険視するツイート
ネットからの出会いが恋愛に発展することはよくある。かつて『ウェブ恋愛』(ちくま新書)でも書いたが、特に共通の趣味や話題があれば、壁は低くなる。しかし白石は、ネットでの出会いで恋愛に発展したことはないと話す。逮捕されたとき、「付き合っていた」という女性がいたことには、「嘘だ」と言いきった。
「元カノとかって嘘ですよ。だって6年間、付き合っている人がいないですから。テレビで証言をしていた女は、あれはやり捨てただけ。一緒にいていい女はいないです」
有料面会「なんでも聞いてください」
その後、「ネットで出会った人数」や「アカウントはいくつなのか」、「『首吊り士』というアカウントは、なんと読むのか(くびつり・ざむらい、と呼ぶ人もいたために、確認したかった)などの質問には、「それは有料です」と答えるだけだ。
ここまできて“無料で聞ける質問”は、ほとんどなくなってきた。意図的に、白石が少しだけ答えて、その後の回答は有料としているのではないかとも思っていた。だとすれば、私は、白石に誘導されているようなものだ。しかし、事件への興味から「まだ話したい」「まだ知りたいことがある」とも思ったのも事実だった。
面会時間の終了が近づき、拘置所職員が合図をした。そして、白石を面会室から連れ出そうとする。そのとき白石が言った。
「これ以上、話を聞きたければ、有料です。もし、希望するなら時間をとります。手紙よりも電報のほうが早いので、スケジュールを書いておいてください。そうすれば、その日は空けておきますので」
さすがナンパ師。人の心を動かす戦術を知っているのだろう。そのため、私は「もっと話を聞きたい」という感情に、強く支配された。
拘置所から出るときに、私はお金を払うべきか悩んだ。すでに出版社の中には、有料でインタビューしている雑誌もあったが、まだまだ聞きたいことはたくさんある。
裁判が始まり白石が“証言”をしたとしても、本当のことを話すかはわからない。それ以前に、傍聴希望者が多いことが想像でき、抽選に当たるかどうかもわからない。ならば、一度だけでも事件の詳細を聞きたい。
葛藤の末、私は事件の話を聞くことし、拘置所の近くにあるコンビニで現金を引き落とし、再び、拘置所へ戻って白石から提示された額を差し入れした。そして帰宅後、次の面会日を書いた電報を送ることにした。
座間9人殺害事件 現場アパート前の警察車両は増え、捜査員は慌ただしく動き回った
それから約2週間が経過し、私は再び、立川拘置所へと向かった。
このときは面会室「3番」に通された。ほどなくして白石が現れ、彼は開口一番、「なんでも聞いてください」と言った。
事件の本題に関する詳しいやりとりは、拙著『ルポ 平成ネット犯罪』に記しているが、いちばん印象に残っているのは、白石はアカウントを5つ持っていたというが、もっとも女性の反応がよかったのが「@死にたい」だったということだ。自殺を考えている人は、話を聞いてほしいという心理があるからだろう。
いくつものアカウントを使って、自殺をしたい人とつながった白石だが、本人は、少なくとも事件を起こす前、自殺願望はなかったという。被害者に「一緒に死のう」などと言ったのは、あくまでも誘い出す手口だった、ということだ。
「自殺は考えたことはないですね。あるとすれば逮捕後。厳しい時期があったので頭をよぎったんです。でも、立川(拘置所)に移って環境が改善されたんです。ごはんも美味しいので、今は大丈夫です」
警察の取り調べの中で、「厳しい」と感じるときがあり、自殺を考えたということか。事件で逮捕され、勾留されていれば、心情的にネガティブになることはあるだろう。しかし、自殺が頭をよぎるほどの圧迫を感じることはめったにないはずだが、起こした事件の大きさを考えるとしかたない。
有料面会「なんでも聞いてください」
その後、「ネットで出会った人数」や「アカウントはいくつなのか」、「『首吊り士』というアカウントは、なんと読むのか(くびつり・ざむらい、と呼ぶ人もいたために、確認したかった)などの質問には、「それは有料です」と答えるだけだ。
ここまできて“無料で聞ける質問”は、ほとんどなくなってきた。意図的に、白石が少しだけ答えて、その後の回答は有料としているのではないかとも思っていた。だとすれば、私は、白石に誘導されているようなものだ。しかし、事件への興味から「まだ話したい」「まだ知りたいことがある」とも思ったのも事実だった。
面会時間の終了が近づき、拘置所職員が合図をした。そして、白石を面会室から連れ出そうとする。そのとき白石が言った。
「これ以上、話を聞きたければ、有料です。もし、希望するなら時間をとります。手紙よりも電報のほうが早いので、スケジュールを書いておいてください。そうすれば、その日は空けておきますので」
さすがナンパ師。人の心を動かす戦術を知っているのだろう。そのため、私は「もっと話を聞きたい」という感情に、強く支配された。
拘置所から出るときに、私はお金を払うべきか悩んだ。すでに出版社の中には、有料でインタビューしている雑誌もあったが、まだまだ聞きたいことはたくさんある。
裁判が始まり白石が“証言”をしたとしても、本当のことを話すかはわからない。それ以前に、傍聴希望者が多いことが想像でき、抽選に当たるかどうかもわからない。ならば、一度だけでも事件の詳細を聞きたい。
葛藤の末、私は事件の話を聞くことし、拘置所の近くにあるコンビニで現金を引き落とし、再び、拘置所へ戻って白石から提示された額を差し入れした。そして帰宅後、次の面会日を書いた電報を送ることにした。
それから約2週間が経過し、私は再び、立川拘置所へと向かった。
このときは面会室「3番」に通された。ほどなくして白石が現れ、彼は開口一番、「なんでも聞いてください」と言った。
事件の本題に関する詳しいやりとりは、拙著『ルポ 平成ネット犯罪』に記しているが、いちばん印象に残っているのは、白石はアカウントを5つ持っていたというが、もっとも女性の反応がよかったのが「@死にたい」だったということだ。自殺を考えている人は、話を聞いてほしいという心理があるからだろう。
いくつものアカウントを使って、自殺をしたい人とつながった白石だが、本人は、少なくとも事件を起こす前、自殺願望はなかったという。被害者に「一緒に死のう」などと言ったのは、あくまでも誘い出す手口だった、ということだ。
「自殺は考えたことはないですね。あるとすれば逮捕後。厳しい時期があったので頭をよぎったんです。でも、立川(拘置所)に移って環境が改善されたんです。ごはんも美味しいので、今は大丈夫です」
警察の取り調べの中で、「厳しい」と感じるときがあり、自殺を考えたということか。事件で逮捕され、勾留されていれば、心情的にネガティブになることはあるだろう。しかし、自殺が頭をよぎるほどの圧迫を感じることはめったにないはずだが、起こした事件の大きさを考えるとしかたない。
「人間をバラしたことがある人はわかると思う」
白石が殺害したのは男女9人だが、実際、会ったのは13人だったという。つまり、4人は殺害しなかった。何か「基準」のようなものがあるのだろうか。
「4人のうち1人は男性。お金もなさそうだった。もう1人は、事件を起こした8月から9月まで付き合っていました。部屋にクーラーボックスがあったのを見て逃げ出した女性もいました。残りの1人は10日間だけですが、一緒に住んでいました」
白石は、ネットで知り合った人とは恋愛関係になっていないと最初の面会で言っていた。矛盾する証言ではないかと考えたが、もしかすると、付き合っていただけ、一緒に住んでいただけで。恋愛とは別なのか。ここはあとで気がついた点で、短い面会時間で確認できなかったことを後悔している。
事件後、白石は警察に見つからないようにさまざまな工夫をしていたという。これまでの殺人事件で犯人が逮捕されたタイミングを調べあげ、一定の知識を身につけていた。
「それぞれの事件発覚に該当しない方法を実行しようと思ったんです。携帯電話は長い間、放置しないと警察は位置情報を特定できない。このことは、前回に逮捕されたとき、刑事に教わったんですよ」
送検時、両手で顔を隠し最後まで顔を見せなかった白石容疑者
すべての写真を見る
白石は事件前、ソープランドへの斡旋の疑いで逮捕、起訴され、執行猶予判決が下された過去がある。そのときの取り調べて、犯罪のヒントを得てしまったのだ。警察の事情聴取で“ヒント”を得ることはよくある。自殺未遂者を救済したあとで、医師や警察官が、リアルな自殺方法を教えてしまうこともあるくらいだ。
この、座間9遺体事件の取材で「男に猟奇的な面があり、バラバラにしたあと、食べたのではないか」という情報を耳にした。もしこれが事実であれば、人肉を食べた事件として、さらに異常性が増す。そして衝撃度も変わる。不謹慎ながらも、あえて、白石にその点を問いただした。するとこんな答えが返ってきた。
「食べていないですよ」
そして、笑いながら、こうも言った。
「(あなたは)人を殺したことないでしょ。人間をバラしたことがある人はわかると思うが、人は臭いです。食べる気にはならないです。食欲がわくにおいではないです」
事件が発覚して10月末で2年になる。
SNSで知り合い、自殺願望の女性を殺害するという類似の事件は、今年の9月にも東京・池袋で起きたばかりだ。しかし多くの人間からすれば、すでに終わった事件で、記憶から忘れ去られた事件でもある。日常で、この事件について話をする機会は、さらになくなってきているのが現実だ。
最後の質問として、自分の家族や被害者遺族に何か言うことはないかと聞いた。
「家族に対しては、『ごめんなさい』かな。いや、違うな。『もう忘れてください』かな。もう会うこともないだろうし。被害者遺族にも忘れてください、ですね」
事件を記憶し、この事件から得られる教訓は何か。個人レベルでも、家族レベルでも、地域や職場レベルでも、それぞれの立場で何ができるのかは考えてほしい。
渋井哲也(しぶい・てつや)◎ジャーナリスト。長野日報を経てフリー。東日本大震災以後、被災地で継続して取材を重ねている。『ルポ 平成ネット犯罪』(筑摩書房)ほか著書多数。