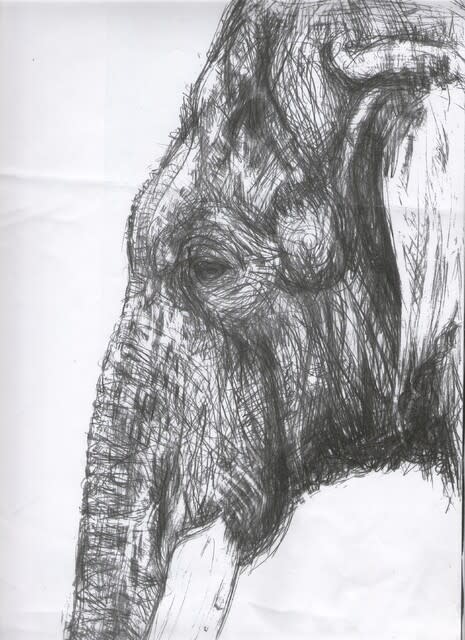
今日の「 お気に入り 」は 、昨日のつづきで 、ほんの50年ほど前の 中国 で約10年間 続いた
「 文化大革命 ( Cultural Revolution ) 」についての 、筆者が知っても 、「 役に立たないムダ知識 」。
インターネットのフリー百科事典 「 ウィキペディア 」日本語版に掲載されている 、「 文革 」
の10年についての厖大な量の記事のうち 、冒頭の解説 と 、「 概要 」と 、「 『 文革評価 』のうち
『 後の中国共産党の対応 』」 の部分だけ 、ひとくさり 。
中国現代史 の おさらい に 。
忘れたいけど 、備忘のために 、あらすじだけでも 、覚えとこ 。
ここから引用はじめ 。
「 文化大革命( ぶんかだいかくめい )とは 、中華人民共和国で 1966年 から 1976年 まで続き 、
1977年 に 終結宣言 がなされた 、中国共産党中央委員会主席毛沢東 主導 による文化改革運動
を装った 毛沢東 の 奪権運動 、政治闘争 である 。全称は 無産階級文化大革命( 簡体
字 : 无产阶级文化大革命 、繁体字 : 無產階級文化大革命 )、略称 は 文革( ぶんかく ) 。
名目は『 封建的文化 、資本主義文化 を批判し 、新しく 社会主義文化を創生しよう 』という
文化の改革運動だった 。実際は 、大躍進政策 の 失敗 によって国家主席の地位を 劉少奇 党副主席
に譲った 毛沢東共産党主席 が 自身の復権を画策し 、 紅衛兵 と呼ばれた 学生運動 や 大衆 を
扇動 して 政敵を攻撃 させ 、失脚に追い込む ための 官製暴動 であり 、中国共産党内部 での
権力闘争 だった 。それを 毛自身が スチューデント・パワー や ベトナム戦争 への反戦運動など
に沸騰する世界と巧みに結びつけた 。それにより 毛沢東自身の著書『 毛主席語録 』は三十カ国
以上に翻訳される 大ベストセラー となり 、世界に 農本思想的 な『 毛沢東思想 』を強く印象づけ 、
各国の知識人や フランスの五月革命 などの政治・社会運動 、対抗文化 にも大きな影響を与えた 。
文化大革命終結後の1978年 、鄧小平 は 中国の新しい 最重要指導者 となり 、文化革命に関連
する 毛沢東主義の政策 を 徐々に解体 した 。また 鄧小平 は 、文化大革命によって疲労した中国
経済を立て直すために 、 改革開放 を 開始 することによって 市場経済体制への移行 を試みた 。
合計すると 、文化大革命 での 推定死者数 は 数十万人から2000万人 に及ぶ 。北京の『 赤い
八月 』、広西虐殺( カニバリズム )と 内モンゴル人民革命党粛清事件 といった 大量虐殺 と
共食い も 特定の地域で発生した 。文化大革命 の最中 、『 板橋ダム決壊事故 』も発生した 。 」
「 概 要
当時の中華人民共和国の経済は大躍進による混乱ののち 、党中央委員会副主席兼国家主席に就任して
実権を握った( 実権派 と呼ばれる ) 劉少奇 や 鄧小平 共産党総書記 が、市場経済 を 部分的 に導入し
( このため 、実権派 はまた 走資派 とも呼ばれた ) 回復しつつあったが 、毛沢東 はこの政策を 、
共産主義 を 資本主義的に修正するもの として批判していた 。『 中国革命は、( 劉 や 鄧 のような )
走資派 の 修正主義 によって 失敗の危機にある 。修正主義者 を批判・打倒せよ 』というのが毛沢東
の主張であった 。そのころ 、毛沢東 を支持する 学生運動グループ がつくられ 、清華大学附属中学
( 日本の高校に相当 )で 回族 ( イスラム教を信仰する中国の少数民族 )の 張承志 によって 紅衛
兵 と命名された 。
毛沢東 の 腹心 の 林彪 共産党副主席 は 指示を受け 、紅衛兵 に『 反革命勢力 』の批判や打倒を扇動
した 。実権派 や 、その支持者 と 見なされた 中国共産党の幹部 、知識人 、旧地主の子孫など 、反
革命分子 と 定義された層 はすべて 熱狂した紅衛兵の攻撃と迫害の対象となり 、組織的・暴力的な
吊るし上げ が 中国全土で横行した 。劉 や 鄧 が失脚したほか 、過酷な糾弾や迫害によって多数の
死者や自殺者が続出し 、また 紅衛兵 も派閥に分れて抗争を展開した 。さらに旧文化であるとして
文化浄化の対象となった貴重な文化財が甚大な被害を受けた 。
紅衛兵の暴走は 毛沢東 にすら制御不能となり 、毛 は1968年に 上山下郷運動( 下放 )を主唱し 、
都市の紅衛兵 を 地方農村に送りこむことで収拾を図る 。その後 林彪 は 毛 と対立し 、1971年9月
毛沢東暗殺計画 が 発覚 したとされる 事件 が起き 、飛行機で国外逃亡を試みて事故死する( 林彪
事件 ) 。林彪 の死後も『 四人組 』を中心として文革は継続したが 、1976年に 毛沢東 が死去 、
直後に 四人組が失脚 して 、文革は終息した 。
犠牲者数については 、中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議( 第十一屆三中全会 )に
おいて『 文革時の死者40万人 、被害者1億人 』と推計されている 。しかし 、文革時の死者数
の公式な推計は 中国共産党当局の公式資料には存在せず 、内外の研究者による調査でも40万人
から2000万人以上と諸説ある 。大革命によって 、1億人近くが何らかの損害を被り 、国内の
大混乱と経済の深刻な停滞をもたらした 。一方で 毛沢東 は 大躍進政策 における 自らの失策 を
埋め合わせ 、その絶対的権力基盤を固め 、革命的で カリスマティックな存在を内外に示した 。
より市場化した社会へと向かおうとする党の指針を 、原点の 退行的な『 農本的主義 』へと押し
もどし 、ブルジョワの殲滅を試みた 。また大学と大学院によるエリート教育を完全否定したため 、
西側諸国の文化的成熟度から後退し 長期にわたる劣勢を強いられることになった 。
鄧小平 率いる 改革派 が政権を握ったことにより 段階的な 毛沢東主義の解体 が始まる 。1981年 、
中国共産党 は 文化大革命 が『 中華人民共和国の創設以来 、最も厳しい後退であり 、党 、国家 、
そして国民が被った最も重い損失を負う責任がある 』と宣言した 。 」
( 中 略 )
「 後の中国共産党の対応
1981年6月に 第11期6中全会 で採択された『 建国以来の党の若干の歴史問題についての決議
( 歴史決議 )』では 、文化大革命は『毛沢東が誤って発動し 、反革命集団に利用され 、党 、
国家や各族人民に重大な災難をもたらした内乱である 」として 、完全な誤りであったことが
公式に確認された。
毛沢東 についても 、『 七分功 、三分過 』という 鄧小平の発言 が 党の見解 だと受け止めら
れている 。一応教科書にも取り上げられるが 、中華人民共和国 は 現在も実質上の言論統制下
にあるため『 林彪 、四人組 が 共産党 と 毛沢東 を利用した 』という記述にとどまった 。
2006年5月 、文化大革命発動から40周年を迎えたが 、中国共産党 から『 文化大革命に関し
ては取り上げないように 』と マスコミに通達 があったために 、中華人民共和国内では一切
報道されなかった 。このように『 文化大革命 』に関しては 中華人民共和国内のマスコミに
とって触れてはいけない 政治タブー の一つ となった 。
2012年3月15日 、重慶で文革時代を肯定する『 唱紅 』運動を展開していた 薄熙来 が失脚
した( 薄熙来事件 )。これについて 、それに先立つ 3月14日 、全人代閉幕後の記者会見
の席上で 温家宝 首相 は 、薄 を批判するために『 文化大革命 の過ち と 封建的な影響は
完全には払拭できていない 。政治改革を成功させないと歴史的悲劇を繰り返す恐れもある 」
と文革を引き合いに出した 。
2016年 は 文革50周年であり 、各地で様々なシンポジウムが催されたが 、中国では文革
に関する研究会は開けず 、6月24日から6月26日にかけて カリフォルニア大学リバーサイド
校 において 、宋永毅( カリフォルニア大学ロサンゼルス校 )主催 の『 中国 と マオ主義者
の遺産 - 文革50周年 国際シンポジウム 」が開催された が 、その席上で ペリー・リンク
( プリンストン大学 )は 、『 アメリカで南北戦争のシンポジウムができないことがある
だろうか 。アメリカ人がわざわざ北京に避難して開催するようなことはあり得ない 』と 、
アメリカに傷痕を残した歴史的内戦 を 例に挙げて 、文革に関する研究会 が 開けない中国
の現状を批判した 。
2018年11月 、文化大革命特有の『 楓橋( フェンチャオ )』( 村全体が反革命的と見なさ
れた人物を公然と批判する行為 )が突全(ママ) 、復活していたことが報じられた 。ただし 、
今回の行為が 単発的だったのか 、この革命特有の文化的な流儀に対して新たな形で関心が
寄せられていることを示唆しているのかは不明である 。
( 後 略 )
」
引用はここまで 。
引用してない部分にとても重い内容を含む記事です 。
「 集団ヒステリー 」は 、「 人類の 痼疾 」 。
どこの国の 、いつの時代にもある 、おぞましい「 黒歴史 」 。
50年後「 14億共同富裕 」「 14億総中流 」なるのかどうか 。
その頃 、東方の 島国 ジパング は 「 一億総中流 」か 「 五千万総貧困 」か 。
「 文革 」を経て 、彼の国の政権は 、「 少数民族 」にせよ 、「 防火長城 」にせよ、
体制維持 には 、これしかないと 、自信 、確信 を もって 、臨んでいるさまが見て取れます 。
いつだったか 、寝床でまどろむ中 、早朝のラジオ番組の締めくくりに 、どこかの誰かが
「 宜候 ( ヨーソロー ) 、野郎ども 、港に別れを告げろ !」なんて 言ってたような 。
天気もいいし 、寝床に別れを告げて 、久しぶりに 、選挙 にでも いってみるか ・・・
あっ 、今日じゃない 、いつだっけ 。。






























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます