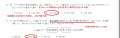この7月期に行われた陸技の試験問題が公表されているので
早速、日本無線協会のサイトで見てきました。
やはり難しくなっている気がする。
確かに半分くらいはまだ過去問で見た覚えのある図などもあるけど
わたしが今受けても陸技に受かる気がしない。
デジタル系の問題では、JKフリップフロップも出題されていたな。
(一陸技も二陸技も出題されていた)
どちらかというと情報処理技術(の中でもハード系)の試験では
ある問題だとは思うけど、無線技術でFF?(上級アマもそうだが)
と思うところはある。
問題で目に留まったのはイミタンスチャートというもの。
スミスチャートとアドミタンスチャートを重ね合わせたものらしい。
私もスミスチャートしか知らなかったので、6年前ぐらいにこの問題が
出ていたらおそらく正解できてないわ。
工学Aのほうでの地デジの問題むずそうなあったな。
OFDM変調方式の等化等・・・ってやつ。
工学基礎ではΔ-Y変換とブリッジ回路の合わせ技の問題もあったし、
私が合格した6年前よりは確実に難しそう。
最後に、テレビ放送マニアとして知っておきたい問題

ガードインターバル
この仕組みのおかげで、同一の周波数(同一物理チャンネル)で放送ができている。
(ちなみに、正解番号は3)
早速、日本無線協会のサイトで見てきました。
やはり難しくなっている気がする。
確かに半分くらいはまだ過去問で見た覚えのある図などもあるけど
わたしが今受けても陸技に受かる気がしない。
デジタル系の問題では、JKフリップフロップも出題されていたな。
(一陸技も二陸技も出題されていた)
どちらかというと情報処理技術(の中でもハード系)の試験では
ある問題だとは思うけど、無線技術でFF?(上級アマもそうだが)
と思うところはある。
問題で目に留まったのはイミタンスチャートというもの。
スミスチャートとアドミタンスチャートを重ね合わせたものらしい。
私もスミスチャートしか知らなかったので、6年前ぐらいにこの問題が
出ていたらおそらく正解できてないわ。
工学Aのほうでの地デジの問題むずそうなあったな。
OFDM変調方式の等化等・・・ってやつ。
工学基礎ではΔ-Y変換とブリッジ回路の合わせ技の問題もあったし、
私が合格した6年前よりは確実に難しそう。
最後に、テレビ放送マニアとして知っておきたい問題

ガードインターバル
この仕組みのおかげで、同一の周波数(同一物理チャンネル)で放送ができている。
(ちなみに、正解番号は3)