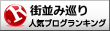植田次期日銀総裁の所信聴取が、きょう国会でありましたが、きょうはそれとは関係なく某エコノミストの方のセミナーに参加させていただきました。
とかいいながら、書いたメモをオフィスに忘れてきてしまいましたが、大まかな流れは覚えています。割と旗幟鮮明な方で、「ここには日銀OBや関係者の方もたくさんおられるので、お聞き苦しいところがあるかと思いますが」とか言いながら、黒田日銀時代の金融政策をボコボコにぶった切っておられました。
曰く、患者に対して誤った診断をしたものだから、処方箋が役に立たないばかりか、副作用ばかり出るようになった。
議論としてはそれほど特別なものでもありません。中央銀行は景気が過熱して、インフレがひどくなったら利上げをして鎮静化をはかる。景気が冷え込んだら利下げをする。下げる方向には限界があり、今はマイナス金利もあるがそれでも-2%位が限界だそうですが、量的緩和、さらにYCC(長期金利の調整)までやったが、インフレ目標は達成できなかった。
昨年になってようやく2%を超えるインフレにはなったたけど(今日のニュースでは1月のCPIが4.2%になったとのこと)、これはコスト・プッシュ型で何と言ったかな、インハウスインフレ?、ようするに国内の景気が良くなったからではない。
日本の企業は付加価値を増やすということができずにいた。利益が増えないから賃金も上がらない(2000年を100とすると2021年は96.1。アメリカは160ぐらい。欧州も150ぐらいだったかな)。欧米ではコスト上昇を価格に転嫁して、人件費の上昇もそこで吸収された。日本の企業はそれができなかった。
では、どうしたらよいか?となるが、この辺になるとやや鋭さを欠いて、人々が、値段が高くても欲しくなるような、付加価値の高い商品(サービス)開発を、と。
だからそれはなんなんだ、という話ですが。
いくつか、面白い論点がありました。
MMT(現代貨幣理論)批判をしていました。前にもここで書きましたが、国家には通貨主権(自国内で通貨を流通させる権利)がある。財源は枯渇することはなく、債務不履行に陥ることもない、というものです。
余談ですが、某政党がこの理論をそのまま政策として主張している、という話も以前しましたが、最近はその支持者の方がいくつかのキーワードを切り取ってSNSで主張したりしてますね。あれ、ちゃんとわかってて言ってるのかなとか、思ったりします。多分初期の共産主義とかも、こんな感じで(資本論とかの)一部の言葉を教条化して、広がっていったのかなと、ふと思いました。
講師の方は、これまで国債が実質的に償還されたことは一度もない、と言います。発行された国債は、利払いと償還のために、新たに国債を発行して払っている。
よく、次世代に負担を先送りする、というけれど、次世代の人たちも負担をするわけではない。ただ単に、債務がどんどん膨らんでいく。
そもそも(日本)国家は既に債務超過に陥っている(665兆円と聞きました)。
我々は銀行に預金をしている。銀行は預かったお金を債務として持っているが、その裏付けとして国債を持っている。その国債を発行した国は、債務の裏付けとなるものを持っていない。
つまり、われわれの預金の裏付けとなる資産はなにもない。国家としての信用とか、まさか国がなくなることはないという思い、ぐらいしかない。
このセミナーではいろいろな方が講師として登壇されます。過去にはリフレ派の方もいらしたし、その反対の方もおられました。
色々なものの見方を知ることはとても勉強になります。個人的には全面的に賛成とは言えないのですが、そうはいっても理路整然と反論するだけの知見はもってはいません。。
たとえ話としても完全ではないのですが、鍋に具材を入れて煮込み、カレールウを入れたとします。塊状のルウなので、底に固まったまま沈んでいる。それでは困るので、水をどんどん足していく。いくら水を足してもかき回さないとカレーにならない。それに、あまり水を入れちゃうとスープカレーを通り越して味が薄くなってしまう。日銀は水を入れることはできるけど、それしかできない。誰かがお玉でかき回さないといけないのに、だれもそれはしていないのですよね。