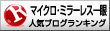ちくま書房 2022年
小泉氏の著作を読むのはこの1年で3冊目だ。おおもとはウクライナ戦争にあるわけだから、1年前のことがなければご縁がなかったことになるが、一般の人向けに書かれたこの方の文章はとても分かりやすく、勉強になる。
本書は2022年9月の時点でまとめられている。戦争は今でも継続中であり、まもなく、来週には開戦後1年を迎えることで何らかの変化が起きるかもしれないが、とにかくここまでの状況を整理することに、本書は役に立つと思う。
小泉氏は今回の戦争を第二次ロシア・ウクライナ戦争と呼んでいる。第一次は2014年に発生したロシアによるクリミア半島の強制併合と、東部ドンバス地方の紛争を示す。そのうえで、今回の事態の発端として2021年春からの情勢を概観している。
詳細は本書を読んでもらった方が早いが、個人的に印象に残った点だけ抜き出すと、この時期、ロシアは米政権の動きをにらみながら行動していた、という視点だ。21年春にも演習名目によるロシア軍のウクライナ国境付近での集結が見られた。このときはまもなく集結が解かれ、6月にはバイデン大統領とプーチン大統領との対面会談が開かれている。
小泉氏はこれを、ロシアが米新政権に対し牽制をしかけたもの、と説明している。
トランプ前政権はロシアにとっては便利な存在だった。
トランプ氏はロシアに対し非常に甘く、いわゆるロシアンゲート疑惑についても記者会見で「プーチンは介入していないと言ってるんだから、自国の情報機関よりもプーチンの言い分を信じる」と発言したそうだ。同席していた米官僚はあまりの屈辱に非常ベルを鳴らして会見を中止させようとすら思ったそうだ。
他方、バイデン政権の対露政策は就任時点では未知数だった。
ゼレンスキー大統領(小泉氏は呼称のウクライナ語読み統一に多少の躊躇を示しながらも、本書ではゼレンシキーと呼んでいる)は、当初はロシアに対してひじょうに敵対的というわけではなかった。むしろクリミア問題等に対しては消極的で、対ロ交渉においても終始主導権をとることができずにいた。
ゼレンスキー氏が「化けた」のは、ロシアの攻撃が始まった直後の対応だ。
閣僚たちと共にキーウの街頭に立ち、スマホで自撮りをしながら「私も閣僚たちもここにいる。我々は断固として戦う」と宣言したのだ。
今日我々が抱く、ゼレンスキー氏の戦時リーダー的な姿は、ここから始まっている。
当初は、我々も記憶にも鮮明に残っている通り、ウクライナが攻撃に持ちこたえるとは、ほとんどの人が思っていなかった。アメリカはゼレンスキー氏に極秘ルートによる亡命を提案した(ゼレンスキー氏は「必要なのは弾薬で、亡命ルートではない」と答えたという)。
「非常に影響力のある欧州某国」駐在のウクライナ大使が同国の外相に支援を求めたところ、「48時間以内にすべてが終わるというのに、なぜ貴国を助けないといけないのか」と言われたという。
レズニコフ国防相はベラルーシを通じてショイグ露国防相の、(ウクライナに)降伏を勧めるというメッセージを受け取った。
レズニコフの答えは「ロシアの降伏なら受け入れる」であったという。
(↑かなり好きなエピソードです)。
プーチン氏の当初の意図は、これも良く知られていることだが短期間に現政権を瓦解させ、親露寄りの政権を打ち立てることにあっただろう、とされる。ウクライナの政権内部、官庁や情報機関などにもロシアの息のかかった人物が配置されていた。また、キーウ近郊のアントノワ空港はロシア軍空挺部隊により攻撃を受けた。
しかし、内通者たちは戦争がはじまると皆逃げ出してしまい(しかるべきポストの人物がいなくなることによる混乱はあったかもしれないが)、期待したような役目は果たさなかった。空港もウクライナ軍の激しい抵抗を受け、制圧作戦は失敗に終わる。
結果としてキーウ攻略はならず、露軍は撤退を余儀なくされる。
撤退後、ブチャの大虐殺が明るみになる。ちょうど、第4回の停戦交渉が始まった頃だ。停戦交渉はこれを機に停滞してしまう。
この大虐殺について小泉氏は、これまでのロシアの非人道行為をよく知っているにもかかわらず、たとえナイーブと言われようと「非常にショックを受けた」という。
・・殺害されたブチャの住民たちは、戦闘の巻き添えになったわけではない。のちにジャーナリストたちが明らかにしているように、ブチャの占領自体はほぼ無血で行われたものの、虐殺、性的暴行、略奪はその後に始まったのである。そこには何の軍事的合理性もなかった。(中略)ブチャやその他多くの占領地域(ロシア軍の戦争犯罪はブチャに限られたものではなく、むしろ氷山の一角であった)における振る舞いは、どう考えても「悪」と呼ぶほかないだろう。 (電子版のページ119-120/219)
ここでは開戦前夜、初期の状況を中心に拾い書きしたが、小泉氏の専門家としての本領はこの戦争をどう捉えるべきか、という考察にある。
技術的にはドローンの利用など、新しい面もあるが、戦争の性質としてはには80年前の独ソ戦からあまり変わっていない、古典的な戦争となっている。
クラウゼヴィッツの戦争論から戦争の本質を説き、古典的な貴族同士の争い(互いに犠牲を抑え、小規模な勝利を重ねて相手の消耗を図った)から、ナポレオンによる戦争概念の更新(国民皆兵制度による大規模動員、国王の軍隊から国民国家の大衆による、自国の危機に対し自発的に戦う「獰猛な戦争」への変化)について解説をする。ウクライナの国民は自国への侵略者に対しこれを撃退すべきだという、シンプルな意思で結束している。
ゼレンスキーは国民に結束を呼び掛け、国際社会にロシアへの非難とウクライナへの共感を呼び掛けた。
かつてヒズボラは圧倒的な戦力差を持つイスラエルに対し、小回りのきく軍事機構と小規模戦闘を繰り返し、それを情報空間に拡散(市民が殺傷されているニュースが流されることで、イスラエルの権威を毀損させる)手法を取り、イスラエルの軍事意図をくじいた。いわばハイブリッドな、現代的な戦争の手法ともいえる。
但し、これには限界があると小泉氏も認める。この手法が功を奏するには相手がある程度民主的な政体を持っている必要があるからだ。
長すぎて書評としてはあまり褒められたものではないが、やはりご一読をお勧めしたい。
ところで、本書のあとがきの最後に関係者への謝辞と執筆年月、自署名が書かれているが、執筆年月がなぜか2020年9月になっている。。ちょっと珍しい校正ミスですね。。