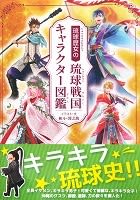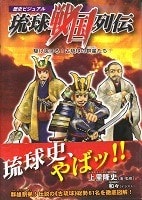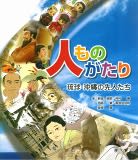首里城再現儀式「百人御物参」より
琉球の神女・ノロさんたちが頭に差している簪を
「金カブ(キンカブ)」と言います。
王国時代のものがいくつか残っていて
博物館などで実物を見ることができるのですが、
この金カブ、よーーーーく見ると
頭の丸い部分に穴が開いているんですね。
そして、モノによってはそこから針金のようなものが
ぴょこっと飛び出た状態のものも…。
(嵐山昌さんのツイートで気づかされました)
…なんだこれは!?
おそらく茎と呼ばれる棒部分とくっつけるための
構造上のなにかだろう…けど
どういうこと???

いや…でも茎の根元に
針金をぐるぐるして固定している様子は見られない…

いや、でもこれではしっかりとは固定できないだろう…。
そんなこんなで金カブの構造にアンテナを立てたまま
しばらくの時が過ぎたある日…
『首里城研究 No5』に収録されている
「金属文化の素描~神女の簪について(1)~」(粟国恭子)に
構造上の記述を発見!
それらを参考に更に分解して絵にしてみたのがこちら。

※針金の長さなどは分かりやすく図解するために誇張しています。
つまり、
巻き付けて、引っ張って、はめる
ということらしい。
また、お気づきのように金カブの中は空洞です。
私は持ったことはないのですが
見た目の印象よりはだいぶ軽いようですね。

金カブを前から挿すか、後ろから挿すか、
というのは色々説がありますが
空洞で軽いのであれば
後ろから挿しても落ちないですね。
(でも私は見た目のバランス的に前から派。↑モデル:百十踏揚)