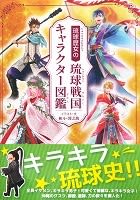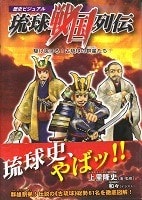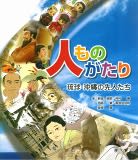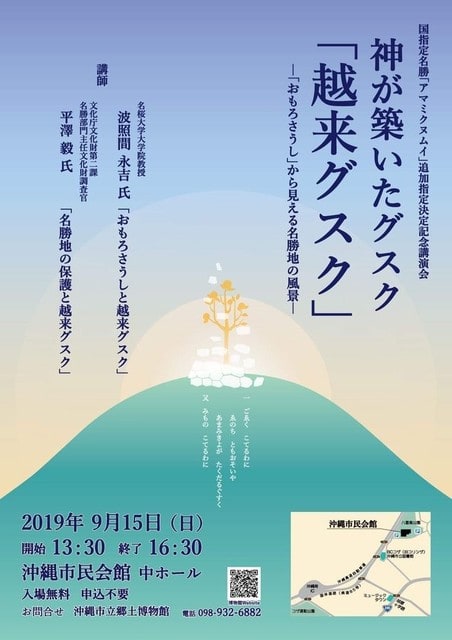
先日、
『神が築いたグスク「越来グスク」』の講演会がありました。
これは、越来グスクが国の名勝「アマミクヌムイ」に
追加登録されたことを記念してのもの。
“アマミクに関連する御嶽として”
としか説明がなかったので
…ん!?越来グスクとアマミキヨにどんな関係が!?
と頭の中が「????」だらけになりました。
(ワタシは)越来グスクとアマミキヨの関連は
これまで聞いたことがなかったし、
越来グスクの石碑や、沖縄市教育委員会の説明版、
沖縄市立博物館の越来グスク展のパンフレット、
沖縄市の歴史を描いたコザ十字路の大壁画(および解説パンフ)にも
アマミキヨとの関連記述は一切なかったから。
もちろん私の知識不足もありましょうが、
これらを鑑みると
少なくとも沖縄市はこれまで越来グスク↔アマミキヨを
推して(重要視して)いなかった、とは言えるでしょう。

その後、沖縄市立図書館で追加指定に関連してのパネルが設置され↑
その中で「おもろさうし」に
「(越来グスクは)アマミキヨがつくったグスク」
という記述があることを知りました。
なるほど!おもろさうしか!
アマミキヨと史跡の関係といえば琉球七御嶽だけど、
おもろさうしに越来グスクの記述があったとは知らなんだ。
史書には七御嶽の記述だけで
越来グスクはないものね。
しかし、
なんで沖縄市は今までこの部分を一切紹介してこなかったんだ????
全然周知されていないのに、何でいきなり追加指定????
越来グスク、破壊されまくってて全然グスクとしての面影ないけどいいの????
と疑問でもあり、
全くなにもわからなかったので
勉強しに行ってきました。
+
前半は追加指定の根拠となった
「越来のおもろ」についての解説。
講師は以前、
勝連・阿麻和利をおもろをテーマにした講演会を拝聴したこともある
波照間永吉先生。
ごゑく こてるわに
ゑのち ともおそいや
あまみきよが たくだる ぐすく
越来 小照る曲(曲輪)に
命 とも襲いは
アマミキヨが 工たるグスク
「おもろさうし2-74」
これが件のおもろ。
越来の曲輪、城壁の曲線、つまりグスクそのものを讃え、
“この素晴らしいグスクはアマミキヨが造ったグスクです”
と神をたたえ、祭祀を行っていたようです。
ほほ~~~~
越来をたたえるおもろは17首あり
その中からいくつかを読み解いていきました。
私にとって越来のおもろと言えば
「鷲の嶺」のおもろ。
ごゑく世のぬしの
わしのみね ちよわちへ
いみやからど ごゑくは
いみきや まさる
越来の世の主様が鷲の嶺においでになりまして
今からこそ越来は イミキは勝るのです。
「おもろさうし2-79(39)」
イミキの意味は諸説あるようですが、
講師の波照間先生によると
イミキは「お神酒」、
お神酒は米が原料のため、米の豊かさ、つまり五穀豊穣では、
とのこと。
でも、実は私が衝撃だったのは、このイミキではなく
「鷲の嶺」の部分。
鷲の嶺は越来のグスクのある嶺、
ひいては越来グスクそのもの
という解釈を以前本で読んでいたので、
(越来世の主が、鷲の嶺(≒越来グスク)に来て(就任して)、
今こそ越来は豊かになるのだ)
こんな意味だと思っていたのです、
が、
鷲の嶺はグスクとは別にあるらしい!!
なにーーーーっ!!!???

沖縄市立郷土博物館学芸員さんによると
越来グスクから1キロ東に行った、
現・宮里小学校のところらしいです…。
(今はその面影はまったくないとのことでしたが…)
つまり、
〝越来世の主が鷲の嶺に出かけて行って”
という、巡行の様子とな。
わーお、マージーかーーーーーー。

グーグルマップ地形図で見てみる。
越来グスクの東に宮里小学校(下線部)。
更にその東に海。
(鷲の嶺から海をみるおもろもある)
地形図で見ると
確かに高台になっている地形が続いている(灰色部分が斜面)。
昔は山々が連なっていて、
この一部分が
いわゆる「鷲の嶺」
だったのだろうか?
キラキラ本の擬人化・越来グスクは
鷲の嶺≒越来グスクの解釈でかいてたんで(澪之助作)
違うとなるとちょっとショック…。
それとも、どっちの解釈もありなのか?
ともあれ、
鷲の嶺≒越来グスクのある嶺≒越来グスク
とは言い切れないことを学びました
(長くなったのでつづく)
*オマケ*
郷土博物館のスタッフ紹介ページイイね!
皆めちゃ楽しそう(笑)
市立図書館が(元)コリンザに移転してから
あの建物訪れてないけど、
階下の図書館が空いて
郷土博物館はなにか変わったのかな。
そのうち再訪しようかな。
*特別講座開催のお知らせ*
ボーダーインク×桜坂劇場(桜坂市民大学)特別講座 (10/2 和々)