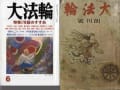大法輪という雑誌がある。「仏教の知恵を現代に生かす総合誌」とある。創刊は昭和9年。戦時中の休刊があるから、今年で72巻を数える。仏教雑誌の老舗の老舗である。と言うよりも他にこれといった雑誌は仏教にはない。それぞれ宗派や宗教団体が自分の所の布教誌として発行しているものくらいだ。だから、この大法輪という雑誌は私たちにとって貴重な存在なのだ。
私も至らぬ乍ら原稿をこれまでに何度かご掲載いただいている。大学で仏教を学んだわけでもない。ただ独学してきただけなのに、他の優秀な学者さんたちに混じって原稿を寄せるのも申し訳ないと思っている。実は、今出ている6月号にも、「ガンを患ったNさんからの手紙」と題する小文をご掲載いただいている。勿体ないことだ。
ところで、今私の手元に、この大法輪誌の創刊号がある。昭和9年10月1日発行。ここ國分寺の先々代泰雄師が購入し秘蔵されてきたものだろう。表紙には、国宝信貴山縁起の一部、「剣の護法飛行の図」が描かれている。醍醐天皇の病を癒したという首の輪に沢山の剣を吊した剣の護法が法輪を転じつつ剣を光らせ信貴山から内裏へ飛行する光景を写したものだという。
法輪とは、お釈迦様の教えのことで、衆生の迷妄を碎破することが車輪転じて瓦礫を砕くようだとの例えから法輪と名付けられた。法輪は、仏教のシンボルであり、軸から出た八つの棒が車輪を支えていることから、四聖諦とともに教えの根幹をなす八正道を意味する。
創刊号には、加藤拙道、高楠順次郎、武者小路実篤など蒼々たる顔ぶれが執筆されている。萩原井泉水の名も見える。荒井寛方画伯の絵も巻頭を飾る。また沢山の小説に加え、今も連載する短歌や俳句のコーナーもこの当時からあった。
創刊の辞に、「時は正に非常時、国運進展せんとて、東亜の新黎明に、警鐘が鳴る。思想問題に、国防問題に、農村問題に、生活問題に、その徹底せる解決を求めんとするの声は、喧々囂々として耳を聾するばかりである。しかも国民は、今なお統一ある帰趨を見出し得ない。そは何故か、真の信念なき為である。
この時にあたりて、仏降誕二千五百年をむかう。大聖釈尊の教法、そはこの無明の長夜を彷徨する大衆に、与えられたる唯一の大燈炬ではないか。ここに於いて、『大法輪』は正法を大衆に伝うべき使命をもって、創刊せられたのである」とある。
時代の雰囲気が醸し出す意気込みが感じられる素晴らしい「創刊の辞」ではないかと思う。時代に対する憂いが現代にも通じるのではないかと読んでいて思った。時あたかも改憲が叫ばれ、自衛隊という軍隊が海外に派兵される時代だ。民営化という名のアメリカ式システムへの移行が粛々と進められ、全てのものがアメリカンナイズされて、物事の判断思考基準、より所、真実と思えるものを失っている時代なのではないか。
今こそこの創刊の辞にあるような志を多くの人たちと共にしたい。そうあらねば手遅れになるのではないか。仏教の心が生きていた古き良き日本の心を枯渇させることのなきよう、益々大法輪誌には気を吐いて欲しい。定期購読をお勧めする。
私も至らぬ乍ら原稿をこれまでに何度かご掲載いただいている。大学で仏教を学んだわけでもない。ただ独学してきただけなのに、他の優秀な学者さんたちに混じって原稿を寄せるのも申し訳ないと思っている。実は、今出ている6月号にも、「ガンを患ったNさんからの手紙」と題する小文をご掲載いただいている。勿体ないことだ。
ところで、今私の手元に、この大法輪誌の創刊号がある。昭和9年10月1日発行。ここ國分寺の先々代泰雄師が購入し秘蔵されてきたものだろう。表紙には、国宝信貴山縁起の一部、「剣の護法飛行の図」が描かれている。醍醐天皇の病を癒したという首の輪に沢山の剣を吊した剣の護法が法輪を転じつつ剣を光らせ信貴山から内裏へ飛行する光景を写したものだという。
法輪とは、お釈迦様の教えのことで、衆生の迷妄を碎破することが車輪転じて瓦礫を砕くようだとの例えから法輪と名付けられた。法輪は、仏教のシンボルであり、軸から出た八つの棒が車輪を支えていることから、四聖諦とともに教えの根幹をなす八正道を意味する。
創刊号には、加藤拙道、高楠順次郎、武者小路実篤など蒼々たる顔ぶれが執筆されている。萩原井泉水の名も見える。荒井寛方画伯の絵も巻頭を飾る。また沢山の小説に加え、今も連載する短歌や俳句のコーナーもこの当時からあった。
創刊の辞に、「時は正に非常時、国運進展せんとて、東亜の新黎明に、警鐘が鳴る。思想問題に、国防問題に、農村問題に、生活問題に、その徹底せる解決を求めんとするの声は、喧々囂々として耳を聾するばかりである。しかも国民は、今なお統一ある帰趨を見出し得ない。そは何故か、真の信念なき為である。
この時にあたりて、仏降誕二千五百年をむかう。大聖釈尊の教法、そはこの無明の長夜を彷徨する大衆に、与えられたる唯一の大燈炬ではないか。ここに於いて、『大法輪』は正法を大衆に伝うべき使命をもって、創刊せられたのである」とある。
時代の雰囲気が醸し出す意気込みが感じられる素晴らしい「創刊の辞」ではないかと思う。時代に対する憂いが現代にも通じるのではないかと読んでいて思った。時あたかも改憲が叫ばれ、自衛隊という軍隊が海外に派兵される時代だ。民営化という名のアメリカ式システムへの移行が粛々と進められ、全てのものがアメリカンナイズされて、物事の判断思考基準、より所、真実と思えるものを失っている時代なのではないか。
今こそこの創刊の辞にあるような志を多くの人たちと共にしたい。そうあらねば手遅れになるのではないか。仏教の心が生きていた古き良き日本の心を枯渇させることのなきよう、益々大法輪誌には気を吐いて欲しい。定期購読をお勧めする。