

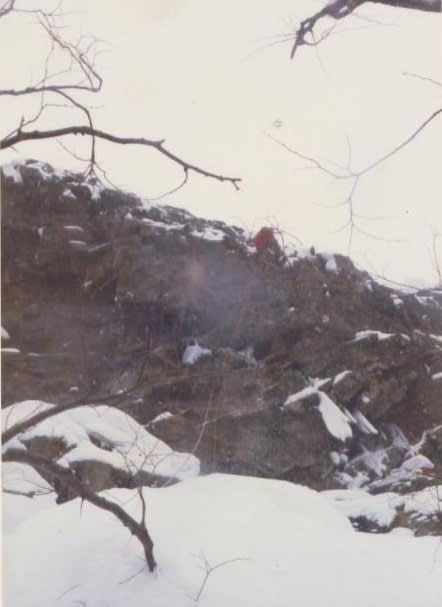







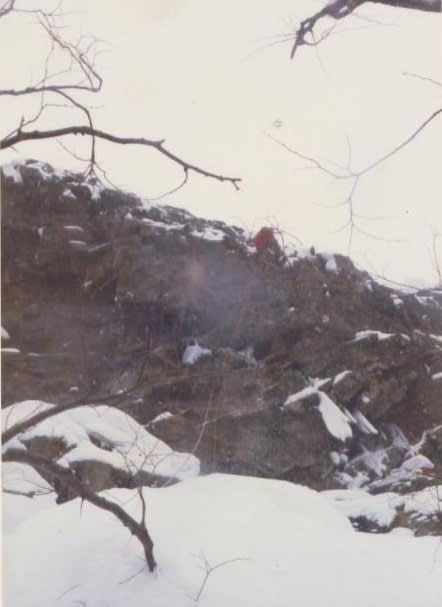







【中央ルンゼ幻の初登攀】
1966年9月に実質的な中央ルンゼ初登攀が成されたが、実は1年前の1965年に意外なもう一つの初登攀が成されている。この登攀は記録には残っていないようだが、S氏によるとルートは中央ルンゼの風の踊り場より左側のフェースに取り付き、直上してから上部のハング帯下のバンドを右にトラバースし、中央ルンゼ核心部の垂壁部付近を突破してブッシュ帯に到達している模様です。
このパーティーは1965年の秋の呉田豊誠氏ら(仙台高校山岳部OB おろおろ会)で、現在では登られる事の無い幻のルートにより、中央ルンゼが攻略されたと見る事も出来ます。このルートの詳細は解りませんが、個人的な意見としては1977年7月にかつて自分がトレースした、ダイレクトルート上部のラインと重なっているのではないかと思っています。(途中で残置ハーケンは無かった)当時このルートを登って上部のハング帯に達したとき、中央ルンゼ方向に走るバンドには古びた鉄カラビナが有り、どうしてこんな所に有るのか不思議に思ったことがあった。なお、西川山岳会パーティーが昨年初登攀したルート「天の川」は一部ここと重複すると思われます。
叉はあまり現実的ではないと思うが、1972年9月に初登攀されている左削壁ルート(相沢昌一氏パーティー)を辿った可能性も有り得ます。以前、相沢氏に聞いた話によると、左削壁ルートには既に残置ハーケンが有った模様で、いったい誰が残したものかは解らなかったそうです。

黒伏山南壁 中央ルンゼ核心部の周辺
この方は衝立岩の雲稜第2ルート?を初登攀直後に再登するほどの実力者で、S氏によると当時この方に肩を並べる人は誰も無かったらしい。片手懸垂をこなしかつバランス感覚は抜群で、現在のフリークライマーに通じようなセンスと能力の持ち主だった模様です。しかし、彼は意外とこのルートに対しての執着心はあまり無かったようで、その後山頂のピナクルを目指す事も無く、また、冬季の登攀を試みようとする事もなかった。
【中央ルンゼ冬季の初登攀】
この中央ルンゼの初登攀を逃してしまい、悔しい思いで次の目標を冬期登攀に向けた人がいた。もちろん当時地元の山岳会で冬季登攀を行っている人は無く、首都圏のエキスパートでも一の倉沢レベルの冬季登攀者は数少なかったと思われるが、1968年12月に意欲的な第1回目の試登を行っている。このメンバーの一人が時々登場するS氏らで、1969年12月の第2回目試登記録が宮城教育大学WV部会報に載っている。この時は正月の寒波に見舞われ、分厚い氷と猛烈なチリ雪崩の攻撃にに会い、3人テラスに到達しただけで敗退したとある。この時はチリ雪崩と共に落下する氷にヘルメットが割れてしまい、次回からはヘルメットを2重に被る有様だったそうです。
しかし、この2回目の試登の時、黒伏山南壁の冬季初登攀を目指し、遅れてやって来たもう一つのパーティーがあった。このパーティーは、当時「渓谷登攀」というネーミングで岩と雪に記録投稿を重ねる県内の雪沓(ずんべ)山の会 で、以外にも目標は中央ルンゼには無く、3人テラスから左側のブッシュ帯に取り付き、ほぼブッシュ通しに山頂のピナクルを目指すものだった。ある意味では意欲的な冬季のルート開拓ともいえるが・・・。自分も一度無雪期にこのルート?を登った事があるが、残置ハーケンを3本確認しただけで殆どは垂直の木登り状態だった。
1970年12月、3度目の完登を目指してやって来たのは、仙台山岳会の創設者の今泉均氏、会員の佐々木祐二氏(S氏)、小坂勇二郎氏、土居忠氏の4名だった。しかし、キビタキの池に到着してみると意外なデポ品が有り、雪沓山の会のメンバーが今年もやって来る事をはじめて知った。ここで初登攀争いに火がついた様で、何が何でも最初にピナクルに立ちたいという思いだった様です。
12月29日に猛烈なチリ雪崩と氷の落下の中を直上ルートに取き付き、垂み入り口の難しい氷壁を突破してフィックスを伸ばし、困難な核心部を攻略して31日の真夜中に今泉氏、佐々木氏、小坂氏の3名が山頂のピナクルに達した。遅れてやって来た雪沓山の会のメンバー4名も1970年1月1日の翌日山頂に立ち、2本のルートからによるほぼ同時の初登攀がなされた。
登攀の様子はかなり苦戦した様で、夜間にはトップがアイゼンの火花を散らしながら墜落していったそうです。当時の写真を見ると頼りないチェスとハーネスに身を預け、軍手を絞りながら氷を叩き落して少しずつ攀じ登り、全身ずぶ濡れの様にして山頂に至った様子が伺えます。なお、この会のリーダーだった今泉均氏はその後1972年、当時は未踏峰だった、ネパールヒマラヤのランタン・リ(7205m)の単独試登を試み、帰らぬ人となりました。 合掌。


故 今泉均氏 佐々木祐二氏


3人テラス下? 核心部取り付きの雪壁
【黒伏山南壁メモリアルアルバム】
1974年12月30~1975年1月4日 海外登山研究会 9名
ヒマラヤ遠征のトレーニングの為に中央ルンゼを登攀。核心部上部までトップを勤めたが、遅れてフィックスロープを上ってきたメンバー3名とチェンジさせられ、冬季第3登を逃してしまった悔しい山行。20歳で最年少メンバーだったが、その後冬季の中央ルンゼをトライするすきっかけを失ってしまった。
当時は肩がらみで確保していた為、トップを確保しているザイルから水が流れ、左腕から入って右腕から流れていって全身ずぶ濡れとなった。緊張する場面ではトップを確保する間は手が離せず、小便も垂れ流しにていた事も良く覚えている。意地でもトップを続けるべきだったと後悔しているが、その当時はまだまだ未熟でのんびりタイプの新人。後で、中途半端な山行は一生の後悔を残すと知った次第です。


南壁をバックに 核心部上部までのルート工作
1977年1月 坂野 土居
1976年7月に開拓したダイレクトルートの冬季登攀を目指し、赤い大ハングを越えて下部岩壁を登り切ったが、結局上部ルートは手付かずのままの敗退。大ハングでは2mにも及ぶツララをたたき落しながら越えたのが印象的だった。まだまだ実力不足でクライミングへの強い意志もなく、その後このルートを試みようとする闘志もあまり沸かなかった。
この時、中央ルンゼに取り付いた仙台RCCパーティー(鈴木氏ら)がワンプッシュで完登し、冬季第4登を果たして明暗を分けた。この頃から関心事は何となくヒマラヤへ。


赤い大ハングをリードする 雪にべったりと覆われた黒伏山南壁
1993年12月30日~1994年1月3日 遠藤 遊佐 大石 坂野
冬季のダイレクトルートに遠藤さんと同行させてもらい、4ビバーク5日間を費やしてようやく完登。自分の出番は無かったが、ようやくこのルートにけじめが付いた様でそれなりには満足。これが最後のクライミングとなり、その後この世界に戻る事はなくなった。


風の踊り場付近で遠藤さんと共に 核心部へ至る雪壁
※黒伏山南壁ダイレクトルート冬季初登攀
平成4年12月30日~平成5年1月3日
先日、偶然にも出てきた黒伏山の登攀記録を転載させて頂きます。このルートの初登攀については当時を物語る方が少なく、その他の記録もあまり残っていない。S氏によれば、当時山形大学山岳部パーティーなども先行して核心部に肉薄していた様だが、核心部を攻略したと言う様子は伺えなかった様です。現在の中央ルンゼの核心部を始めて突破し、初めて山頂のピナクルに達したのはこのパーティーではないか思われます。
この記録のわずか1週間後にS氏がこのルートを完登したが、ピナクルに立ってみると空き缶に両氏の名前が入った紙切れが有り、まさか既にトレースされているとは思いもよらずがっかりした様です。この文面からすると少し強引に登ったような感もありますが、40年以上も前の当時はフリーと人工の区別は有ったにせよ、「フリークライミング」と言う概念は存在せず、手段を論議する以前に情熱がそれをうわまったと言えるでしょう。この結果、既に三原ルートが存在したとは言え、この南壁の実質上の初登攀ともいえると思います。
なお、このル初登攀者はルート名を「鈎状クーロアール」と命名し、確かに自分が現役の頃にはこの名称が使われていた。後で改名された「中央ルンゼ」は確かに解りやすい名称だが、この「鉤状クーロアール」こそもっと尊重されるべきルート名だったと思います。
「山想 六十一号」より転載させて頂きました。、
「黒伏山岩壁鉤状クーロアール登攀」
昭和41年(1966年)9月16~18日 個人山行
高橋二義 武田捷
私が黒伏山に始めて取り付いたのは昨年(S40年10月)で、このときは図?の三人テラスまでしか登る事は出来なかった。(山想60号22ページ参照)しかし、そのとき以来、この大きな岩壁は頭の中から離れた事は無かった。黒伏山岩壁を完登したい。これは私ばかりではなく、三年前朝日岳で遭難死した故二瓶昇氏とザイルを組んで、取り付き点より三人テラスまでの直登ルートを開拓した高橋の希望でもあった。そして黒伏の岩と斗い完登は果たせなかったが、その核心部である中間のフェースと上部の垂壁スラブを落とす事が出来た。以下はその時の記録である。
9月16日 晴れ
黒滝手前の橋の所から小型トラックに便乗しこれで1時間稼げた。昼食を取り、取り付き点に向かう。このあたりは今伐採作業が行われており、チェーンソーの音がひっきりなしに聞こえてくる。この伐採地より壁を見上げて写真を撮る。改めて壁の大きさに感心する。
1P目はトップ高橋で登攀開始。1より小さなリッジに取り付くとすぐフェースになり、残置ハーケンを頼りに直上すると小さいハングとなり、アブミ一個をそこに置いて行ってもらう。昨年だいぶ苦労させられた所だ。ハングを越した所よりジェードルとなり、レイバックで二米ほど登り2のスタンスに着く。ハーケンや食料の入ったザックは重く呼吸が荒くなる。
2P目は2よりフェースクライミングとなり、ここはフリーで登る。途中つま先が入るような小さなフットホールドに足を掛け、ブッシュをつかんで静かに立ち上がる所があるが、このピッチでは一番嫌な所である。ここを越して5m程登ると、三原ルートと合いする所が三人テラス3.である。
時間はまだ少しあるが、後はビバークプラッツが無いのでここでビバークする事にする。3人が腰を下ろす事が出来る程の広さである。ハーケンを4本打ち体を確保する。セーターを着たりヤッケを被ったりしてやっとビバーク体制に入る。美しい星空だ。面白山、蔵王産山、寒風山、白ヒゲ山、仙台カゴなどが黒いシルエットとなって浮かび出てくる。
【タイム】 仙台7:30 ~原宿 9:15~黒滝下10:20~コース入り口10:50~昼食11:00~11:30~取り付き点13:30~三人テラウ16:00~ビバーク体制完了19:00
9月17日 高曇り 午後時々通り雨
昨夜は2時間毎に目を覚ます。腰掛けたままで寝るのはそうらくなものではない。明け方はだいぶ冷える。北面白山と蔵王にレンズ雲が発生しているが、今日一日降らなければ完登は出来そうだ。ビスケットとソーセージ、それにチーズで朝食を済ませて登攀開始。ここから二人とも未知のルートである。
5よりフェースを登りだす。残置ハーケンがルートを指示してくれる。トップの高橋に「ザイルいっぱい」と声をかけると、あと2m程でテラスが有るというのでビレーを外して登りだす。二人共にビレー無しで登りだすし、小さな草付きテラス4で一緒になる。上はハングだで残置ハーケンが4本ある。ここでザックを下ろし、アブミ2個を使ってこのハングを越すと小さなスタンスがある。?ここまでザックを引き上げる。
ここから傾斜が緩くなり上はスラブになる。5より?まではツルベ式に登る。残置ハーケンが1本有り、7~8は見たところ易しそうだが、取り付いてみると意外に悪く、逆層なので登りにくい。この付近で高橋が頭部を赤く着色したカシ木のクサビを拾う。アンダーホールドでトラバースぎみに登ると、まだ新しいシャモニー製ハーケンが1本入っている8。ここからいよいよこのルートの核心部である。
8より外傾バンドが有り、これにルートを求める。残置ハーケンが2本有り1本を回収する。またここに非常に古い黒く錆びたカラビナが一個残置されてあったので、これも記念に回収してくる。このバンドの切れたところに残置ハーケンが一本入っており、ここから先はまだ人間の手の触れていない処女岩壁になる。見上げるとこれではちょっと取り付く気にはなれない。しかし、我々は登り始める。
上が垂壁となり、トップで登るのは高橋のバランスのよさが物を言う。だがバランスの良さだけではどうする事も出来なくなり、ハーケンを打ち始める。完全な人工登攀となり、ハーケンの連打と吊り上げである。「登っていい」と声がかかって登っていってみると、スタンスが有ると思っていたらアブミに乗って確保している。まったく悪い所だ9.。このピッチでハーケン8本を使用し、うち1本を回収する。
9より岩が大きくなり、しかも垂壁。その上ハーケンが入らず、高橋がきわどいバランスで登って行くがだいぶ苦しいようだ。しかしハーケンをやっと一本打ち込みほっとした時、右の方の壁(赤いハングの右の方と思う)からものすごい音を残して落石があった。我々の所まで地鳴りのような振動を感じる。時計を見たら16:00だった。下では伐採作業をしている人達からやたらとコールが掛かる。心配してくれているのだろう。さらに登ってジッヘルポイント10を見つける。しばらくぶりでまともに立っていられる場所である。このピッチでハーケン5本を使用。
10より一ピッチがこのルート登攀のカギと思われる垂直のスラブがある所なのだ。いくら良く見てもリスなど無い。そこで埋め込みボルトを取り出す。このピッチ下5mが2段の垂壁、その上2mがハング、そして3mの垂直スラブと続いている。埋め込みボルトを1本打ち込んで左に2mトラバースしてハーケンを打ち、このスラブを突破する。ボルトに大きな手拭を付けて記念に残す。ラストの武田が登る時にはもう暗くなり、ヘッドライトをつけて行動する。二人が一緒になったのは19:00だった。もう行動するのは危険なので、ここでビバークとする11.。
ハーケンの効く様なリスが無いので埋め込みボルトを一本打ち、これに二人の体を吊り、あまり効かないハーケン3本にザイルをクモの巣のように張りめぐらし、アブミに乗ってクモの巣の中に入った。苦しいビバークだった。苦しいのは我慢できるが、雨だけは降らないでくれと、それだけを祈って寝る。
【タイム】 登攀開始6:55~ビバーク地19:30~ビバーク体制完了22:00
9月18日 終日雨
2時頃より雨が降り出したが4時に朝食。あまり寒いのでメタ1個を焚く。この雨の中の登攀は危険だが、ここまで登ってしまった現在、降りるより登る方がむしろ安全と意見が一致する。登攀準備をしている時、武田がうめ込みボルト1本とジャンピング一本の入っているビニール袋を落としてしまう。こんな時のボルト1本は貴重なものだ。疲労の為注意力が鈍ってしまったのだろうか。
11より12まではフェースのコンタクトラインを登り、12より右側のブッシュに入る。ハーケン2本を使用。しかし、このブッシュの中でも傾斜がきつく、コンティニュアスで登るに苦労した。やっと稜線に出て登攀終了。稜線どうしに左側のピナクルに登り、堅い握手を交わす事が出来た。
下りは疲れている為アップザイレンで降りるのは止め、て、、裏側のブッシュを下る事にする。伐採用の飯場にたどり着く頃にはもう足が変になり、何度ひっくり返ったことか解らない。飯場で3日ぶりに温かい味噌汁とご飯をご馳走になり、やっと一息つくことが出来た。この飯場より入を通り野川に出て、野川からバスで原宿まで行く。パンツまで濡れてしまったので下着を買い、メタを焚いてズボンを乾かす。仙台行きのバスが来た。
【タイム】 登攀開始7:00~左側ピナクル10:30~伐採飯場13:30~14:30~入15:30~野川16:15~31原宿16:41~18:06~仙台19:31.
【付記】
ヘ締め手の計画ではビバーク1回で登るつもりだったが、サポートなしの登攀だったので重量がかさみ、ザックの吊り上げなどで時間が意外とかかった。それに途中からの雨の為、最後の2ピッチをブッシュ帯に逃げねばならなかったのは残念だ。しかし、例え天候が良かったとしても、我々の残り少なくなった装備(ハーケンなど)でこの上のピッチをこなせたかどうかは疑問である。終始トップで奮闘した高橋には敬意を表すると共に、二人で過ごした苦しい、しかも充実感溢れた、虚偽や偽装や虚栄などの入り込む隙間など無い、厳しい自然の中の3日間は、我々の美しい思い出となって生き続ける事だろう。なお、前号では「正面クーロアール」と呼称したが、「鈎状」に改めた。その方がこの岩場の形状からいって適切で有ろう。
【登攀用具】
ナイロンザイル9mm 編み 30m 黄色
〃 30m 赤 ドッペルで使用
〃 8mm 撚り 30m 赤 ザック吊り上げ用
ハーケン 計 60本 使用 36本 (ただし確保用は含まず)
カラビナ 24個 (内ゼルプスト用4個)
埋めこみボルト 3本 (使用 2本)
ジャンピング 1式
アブミ 2段 5個
〃 3段 1個
ハンマー 2丁
ヘルメット 2個 etc


先日の月曜日、休日出勤ですっかり予定が狂ってしまい、あまりにも午後からの暇をもてあましてしまい、ついつい久しぶりにS氏の携帯を鳴らしてみたら、夕方自宅に出頭せよとのお仰せ。その用件とは、日本山岳会の会報「山岳」を処分するので21冊を持って帰れというもの。もちろん断る理由などは無く、有りがたく自分でもあまり持っていない蔵書の一つにに加えさせてもらった。S氏がどういう訳で日本山岳会宮城県支部に在籍していたのか知らないが、会報の「山岳」には興味が有ったのでありがたく頂だいした。
今はまったく山を離れているS氏だが、飯豊連峰、黒伏山、利尻山の話になるとそのボルテージは高まってくる。現役山屋のような輝く眼差しからは熱い思いが伝わってくる様で、中途半端に終わってしまった自分とはまるで別人の様だった。40年以上も前のアルパインクライミング不毛の東北で、元祖山フリーターを自認する様な経歴を持ち、山が全てという極道の様な世界にいた方だが、当時は先鋭的な首都圏の山屋との交流など皆無のようで、むしろその事が創造的な登山を促したのかも知れない。
当日は中央ルンゼの話を聞きたくて伺った訳だが、意外な収穫があって面白かった。S氏の奥さんが名門山岳会の仙台山想会に在籍していた事は知っていたが、奥さんとの話のやり取りの中で、中央ルンゼの登攀記録らしい会報を持っていると言う、まったく意外な話が飛び出した。S氏もダンナのはずがこの話は初めての様子で、探し出してきた「山想61号」(昭和41年10月20日刊)を開いて共に驚いてしまった。この古びた会報には「黒伏山岩壁鈎状クーロアール登攀」、昭和41年9月16~18日(個人山行)という記録が載っていた。
このパーティーは当時仙台山想会の高橋二義氏、武田捷氏の2名。この両氏が実質上の初登攀者だとは聞いていたが、これこそ黒伏山南壁中央ルンゼの初登攀記録だった。まさか記録が残っているとは思わなかったが、中央ルンゼは我々東北のクライマーには思いで深いルートだけに、、その開拓期の様子が明らかになる事は嬉しい。
続く

すっかり山から遠ざかってしまい、暇な毎日をダラダラと過ごしている日々ですが、昔の山の先輩筋のS氏から突然電話がかかって来た。暇だったら明日の夕方、仙台の文化横丁まで出て来いとのお達しで、特に用事も無い身の上なので思わず「ハイ承知」と返事をした。
実はこの方はとんでもない酒豪の人で、山岳会に在籍していた頃には「酒の嗜み」を死ぬほど叩き込まれた方。かつて仙台の国文町でサシで呑んでいた時には、胃液を出し切ってからもハシゴを強いられた思い出が有り、どちらかと言うと恐怖感さえ伴う人。しかし「岩と雪」の希少本を多量に譲り受けた関係上、断る理由など無くノコノコど出かけた。
S氏今では私と違って潔く山からは遠ざかり、青森あたりでブリのルアー釣りを極めた名人の様な人。かつて素晴らしい登山歴を持ちながら、すっかり山を廃業出来る潔さには何か尊敬出来る興味深い人でも有る。でも今回は是非聞いてみたかった事が有った。酔っ払う前にメモを取っておいた理由は、S氏が黒伏山南壁 中央ルンゼ開拓の頃を知る人で、殆ど知られていない初登攀争いの張本人だったからである。
中央ルンゼルートは今や全国的にメジャーなルートとなり、首都圏からも多くのクライマーを迎える東北では異色の人気ルートとなっている。確かにあのブッシュだらけの壁に刻まれた一本の急峻なルンゼは、登ってみて初めて体感できる感動がある。乾いた安山岩のフリクションは抜群で、日本でも特異と思われる井戸の底の様な、美しいクーロアールを大胆に攀じて行く。全てをフリーで完登出来るクライマーは尊敬に値する。
しかしこのルートの初登攀者はいったい誰なのか?そう思った人も多いと思いますが、残念ながらその当時の記録は殆ど残っていない、いや、殆ど記録を残さなかった。現存する記録と言えるのは「日本登山大系」白水社、「日本の岩場 改訂版」白山書房、「岩と雪」山と渓谷社しかない。しかし「日本登山大系」「日本の岩場」の解説と記録には開拓期の記録はすっかり抜け落ちており、しかもそのいずれも、基本的な誤りや見過ごされた記録なども見られる。また、仙台RCC 相沢氏による、「岩と雪」の黒伏山の詳細な岩場特集が有るが、やはり肝心な開拓期の記録は無く、記述内容には正確さが足りない部分も見られる。また、この本は今となっては入手困難で、中央ルンゼを訪れる現役のアルパインクライマーには殆ど知られていない。
しかし当時の話を聞いてみると、今では有り得ない様な初登攀争いがあって、東北の片田舎であっても熱く燃えるような時代が有った様です。つまりこのルートが完登されるまで、あるいは冬季に初登攀が成されるまでのドラマが有り、知られざる多くのクライマーが活躍していた。特に冬季の初登攀はレベル的にも高く、難易度では谷川岳の冬季登攀を凌駕するレベルの記録とも言われている。
これだけ素晴らしく価値有るルートでありながら、その素性がまったく知れないと言うのは残念で、いずれ少しづつ紐解きながら明らかにしたいと思う。
結局S氏とは寿司や・ホルモン屋・高級居酒屋?・フランス料理店の4軒をハシゴさせれられ、ようやく無罪放免してもらった。


