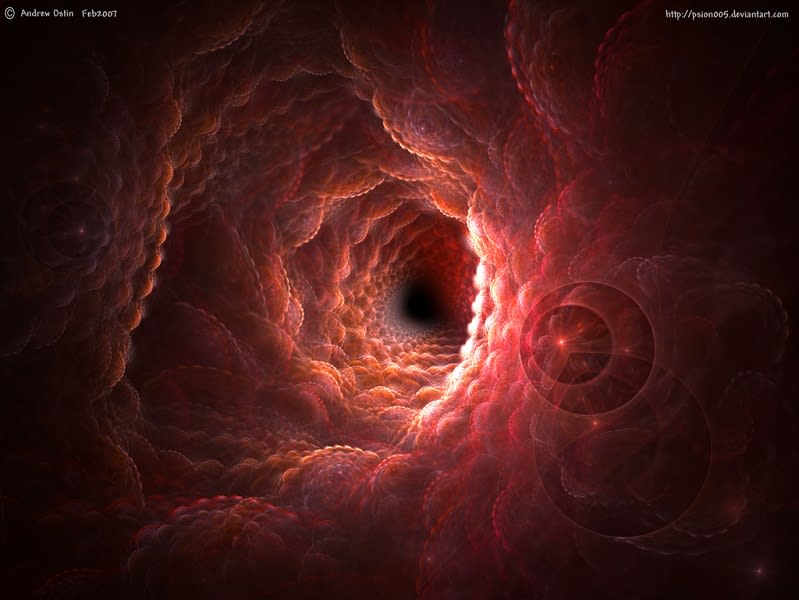(artwork/Yoko Ono)
白いカンバスのほぼ中央、横に一本の線が、細く震えときにはとぎれながら、ほぼ直線で引かれている。
無造作にフリーハンドで描かれたものか計算された線なのかはわからない。
その少し下には、
This line is a part of very large circle
の文字。
それだけだがそれだけではないものだ。
僕は同じような感覚に陥ったことが以前に或る。
言葉で表すとこんな感覚だった。
・・・この 円 には 明確 に 定義 された 中心 はあるが はっきりめにみえる 外周 はない・・。
白いカンバスのほぼ中央、横に一本の線が、細く震えときにはとぎれながら、ほぼ直線で引かれている。
無造作にフリーハンドで描かれたものか計算された線なのかはわからない。
その少し下には、
This line is a part of very large circle
の文字。
それだけだがそれだけではないものだ。
僕は同じような感覚に陥ったことが以前に或る。
言葉で表すとこんな感覚だった。
・・・この 円 には 明確 に 定義 された 中心 はあるが はっきりめにみえる 外周 はない・・。