2月24日、日本の読売新聞(関西版夕刊)に私のインタビューと、学生雷国華さんの作文要旨が載った。
記事を書いてくれたのは石塚直人記者だ。
石塚さんは、以前、このブログで紹介した現4年生の雷国華さんの作文を読んで、
何とか記事にしようと、あの読売新聞で奮闘を重ね、実現された。
記事は、石塚記者の血と汗の結晶である。
字数制限、内容制限、語彙制限を工夫と粘りで克服するその努力に、日本のジャーナリストの立ち姿が見えた。
記事を読んで、日本や中国から、コメントやメールを何通もいただいた。
さらに、何と、江西財経大学のニュースにまで、この記事が取り上げられた。
こうして、記事自体が海を渡り、中日友好の働きを担う事態となっている。
下に石塚直人記者の記事を掲載させていただく。
言葉遣いも「侵略」とか使えないので(読売だから~)、「攻め込んだ」など苦労しているのが
分かっていただけるだろう。
―――学習通じ 薄らぐ反日感情―――
学生の作文 「懸け橋」決意
領土や歴史認識を巡って日中両国間の金塗油が取りざたされる一方で、中国の大学は4割が日本語学科を擁し、日本語教育が盛んだ。学生たちは何を学び、日本とどう向き合おうとしているのか。2010年秋から江西省の江西財経大学で日本語を教えているブルーはーと(後BH;註1)さんが、冬休みで帰省した際に聞いた。 (石塚直人)
「日本語を学ぶ学生も自国を愛しており、尖閣問題での政府の対応も正しいと思っています。
でも、暴動など感情的な〈反日〉には否定的で、自分たちが両国の懸け橋になろう、
という気持ちが強いですね。」
江西財経大学は省都・南昌市にあり、中国南部(註2)の各省から成績の良い若者が集まる。
農村出身者が過半数を占め、家族の出稼ぎでようやく進学できた学生が多い。BHさんは
全学でただ一人の日本人教員。授業では、自らの米国留学体験から大量の宿題を出して
学生を鍛える。
「入学当初の日本語の知識はゼロ。それが3年生になると、一通りの文章が書けるようになります。」
全国規模の「中国人の日本語作文コンクール」(日本僑報社主催)では、
ここ3年続けて複数の上位入賞者を出した。
上達の原動力は、家族への恩返しを誓う学生たちの猛勉強。
「先生」に最大の敬意を払う中国社会の伝統もある。
入試の成績で学部・学科が振り分けられるため、他の分野が志望だった学生も多いが、
「なぜかしばらくすると日本語が好きになるんです。」
BHさんが赴任してすぐ、尖閣海域で中国漁船と会場保安庁巡視船の衝突事故が起きた。
ただ、地方の反応は比較的穏やかだったという。
「日本のアニメには夢がある。」
「友達を思う心や決してあきらめない精神にひかれる。」
と話す学生も多く、東日本大震災から1年を迎えた2012年3月11日には、
学生有志が呼びかけ、犠牲者を追悼する学内集会も開かれた。
しかし、野田前首相が尖閣諸島の国有化を宣言した同年秋には、
南昌市でも反日デモの嵐が吹き荒れ、日本語を学ぶ学生たちの心は揺れた。
「『休みで帰省しても、近所に日本語学科の学生だと名乗れない』
と作文に書いた子もいました。
もともとテレビの抗日戦争ドラマでは日本気兵が中国人を襲う映像が日常的に流れ、
『キサマ』『バカヤロー』の単語は子供でも知っていますから。」
この頃の学生の作文には、自分たちが「日本人にもいい人がいる」
と周囲を説得していくしかない、という悲壮な決意が目立った。
「日本語学科の私たちまで日本人に敵意を抱いたら、両国関係はどうなるでしょうか。」
「戦争なんか、嫌。」
卒業生からは「戦争を煽る中国人は本当に少人数で、しかも盲目的な人たち。」
というメールも届いた。
彼らは日本の平和憲法も1995年の村山談話も学校で習っていない。
BHさんは、中沢啓二の漫画「裸足のゲン」や与謝野晶子の詩「君死にたまふことなかれ」
なども教材に使い、平和を願う日本人の心を伝えた。
雷国華さん(4年)は、今年度の日本語作文コンクールに、
未来のわが子に向かって中日両国民の友情を解く文章を寄せた。=別掲=
「彼女には日本軍のために障害を負った親戚がいて、
子ども時代から日本人に反感を持っていましたが、大学で等身大の日本を学ぶことで、
〈混迷した現代も2000年の歴史のひとコマ〉と考えられるようになったんです。」
「日本は侵略戦争を謝罪していない。」
と不信感を露わにした作文を書いたことのある男子学生は、
12年春に日系企業に就職し、通訳の仕事をしている。
同年秋にはBHさんの安否を気遣う電話をかけてきて、
「反日デモの背後には貧富の差、言論の自由がないなど中国社会への不満がある。」
と話した。
「彼らは精いっぱい日本について学び、友好のために働こうとしています。
かつて中国に攻め込んだ日本人の側も、きちんと歴史を学び、
そこで学んだものを彼らと共有するべきではないでしょうか。」
―――記事ここまで―――
註1:記事には本名が載っていたがここでは当然ブログ主名に変更。
註2:厳密に言うと、南部のみならず、江西省近隣の省や、黒竜江省、吉林省、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、山西省、河北省など、学生の出身省は広範囲である。
=別掲=とある雷国華さんの作文は(実はこれが記事のメインである)、
明日、改めて全文を紹介することにして今日はこれで一旦筆を置きます、
て言うか、キーボード打ちをやめます。











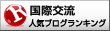



 )・・・排他的で意地悪な気持ち
)・・・排他的で意地悪な気持ち )・・・新発見の驚き
)・・・新発見の驚き )・・・羨ましい気持ち
)・・・羨ましい気持ち













