
四月並み気温との予報を聞いて爺イはのこのこと甘楽の里山巡りに
這い出すことにした。春一番を伴っていることがチョイ不安だが。
目的は延び延びになっていた「古い亀穴峠道」を地形図の破線通りに
しっかりと確認することだ。

破線の位置に行くのには幾通りもあるが、今日は始めてのルート。
甘楽町・上鳥屋の天引森林公園園地から一旦北に廻って三角点・天引
484.8mのある南北稜線に登り上げ三角点にタッチしてから
南進して亀穴峠直下の破線を目指すもの。
この複雑な稜線は数年前に下ったことはあるが登るのは初体験。
堂の入り林道と鳥屋林道の間に横たわる曲がりくねった稜線。
数多くのコブや爺イにはピークに感ずる稜線上の突起があって
乗り越しか? 迂回か? と考える里山の醍醐味十分。
吉井からR-254を西進、「金井信号」で左折して3.3K、
変則四つ角で鳥屋林道の残雪のある川筋の細道を低速で2.5K。
雪解けの森林公園園地には駐車車両なし。本日も完全な一人旅。
支度しながら西の方角を観察、この山の奥、直線距離で440Mに
南北大稜線がある筈(9.14)。

園地の裏から三角点探索の時とルートを変えて右(北)に進む。
直ぐに尾根を巻く笹原になるが、良く観察すればその下に薄い
道形が確認できる。

尾根を一つ跨ぐと山側に石垣がずっと続き、手前は平地。
どう見ても昔の生活の跡と推定できる。

石垣を乗り越えて上の林に入ると大型の石宮。銘は読み取れない。

さて、この辺から西に向かって目前の斜面の小尾根に取り付く。

一コブ越えて更に進むと見覚えのある広い場所。園地から直接西に
向かって大きな窪を登ってくると写真の左側からここに到達
するのだ(9.45)。

左目の二段構えのコブに取り付き何とか乗り切ると境界杭293。
この線は町村境界でもないのにと訝りながら西進する。

間もなく前面に小ピーク、これを越えると本格的な稜線への
斜面登りとなる。赤テープもあるので迷わず前進。

稜線が見えたが大変な急斜面だ。

下ばかり見て歩いて気が付いたら大岩の直下。これは無理だ。

周囲を観察して右(北)への獣道風の踏み跡を発見、迂回して稜線着。
左には迂回した岩の突起。三角点の右方向はこんな下り尾根。

二段のコブを下って100Mほどの崖に下る突端に三角点(10.32)。
この地は甘楽町大字天引字天引国有林、点の記を見ると堂ノ入林道の
国有林ゲートから数百㍍南から東の稜線に来るようになっている。


さて、小休止してからさっきの稜線到達点に戻る。いよいよ、南進の始まり。
直ぐに第一番の突起。さっき回避した小ピークだ。

下ったところに赤テープ、これは数年前に下ってきた時の降口。
東へ急降の踏み跡も確認できる。

二つ目はコブ、高度差は少ないので楽に突破。

三つ目はやや大きい岩峰、両側が削がれているので逃げ場は無く
頑張って直登で乗り越え。

四つ目は似たような突起だが右に曲がっているので鞍部を目指して
急斜面を恐々と迂回(11.00)。

鞍部に着いたら直ぐに五つ目の突起が目の前。息つく間もなく
右から抜ける。

六つ目は正面からピークに行き分岐を左に行ったのは良いがその先が断崖で
足が竦んで降りられない。情けなくももう一度ピークに
登り返して西尾根を下って途中からに南尾根にトラバース。
極めて危険で必死の思い。

何とか回りきって振り返り。確かにここは爺イの手に余る。

七つ目は正面突破。

八つ目は登りは軽くてピークの分岐から左へ。だが、再び断崖で
立ち往生。一旦恐怖感じた後に強行するのは危ないので
戻ってトラバース。

回りきって今度も振り返ってホントに駄目だったのかを確認。
このトラバースに大苦戦、20分も費やした(11.44)。

十歩も歩かないうちに九つ目。

手前に何かの工事用鉄くず。
こんな所で何をしたんだろうか?

こんなヤセ尾根でやれ安心と思ったら先端がストンと切れていて
再び恐怖の崖下り。もう、大分ビビって居るので過剰に反応しているのが
自分でよく分かるが進むしかない。

十個目で漸く地形図上の579M地点に掛かるが上が見えないので
ゲンナリ。

東南を見ると通称・摩利支天とか天引山と云われる699.5Mの
山が見える。未だ半分を過ぎただけなのにもう少しと元気が出る。

579M地点の長い台地を下りに掛かると二回も分岐で全て左。
綺麗に整備された杉林、今までのギスギスした緊張感が緩む。

11ヶ目はゆったりした登り。足にも負担無く気分は楽。

次の12ヶ目は岩の露出した風変わりな突起。左に行くので
頂上手前でショートカット。

新しい稜線に到着で小休止。

やがて前方に明るい視界。どうやら亀穴山(仮称)の近くに来たらしい。
ナビの電源を入れて破線位置を注視しながら進む。

広い場所に出た。藤岡境界も近く古い峠道は此処を通っている筈。

残雪があるので慎重に道形を探すと多分之というのを確認できた。
写真の雪が点々と溶けているのは動物の歩いた跡、その右に
見える微かな凹みが峠道。

この道は確実に破線通りに東に向かって尾根跨ぎに走っている。

だが、一尾根跨いで林に入ると大荒れでやや不安。

窪を廻って下ると園地からの峠道に合流。遂に古い峠道分岐を確認。

合流点の枯れ木にマークを付けた。唯の巻きつけだから数年の
後にはビニールの劣化で縮んで自然に落下するからさしたる
邪魔物ではない(13.12)。

しかし、地形図の峠道の破線がこの古い道だけなのはオカシイ。
現在、園地からの峠道は無理なく鳥屋峠に延びているし
藤岡側にある「道しるべに」にもはっきりと「新屋・天引」と
刻まれているから鳥屋峠と亀穴峠は同等に扱ってもらいたいものだ。

気温は高いが予報どおりの春一番がやってきたのか? 風も強く
なる気配なので峠には行かずにこんな大木の陰で遅い昼食(---13.33)。

休憩後、下山に掛かる。荒れた道を下ってこの沢に降り立つ。

ここからの峠道も大荒れ状態。

こんな倒木がーーと思ったら切り口からして伐採材の放置。

途中に小さな切通し、往路で見ると峠に見える。

目印の大銀杏前を通過、爺イが始めて熊に遭遇し恐怖で
固まって身動き出来なかった嫌な記憶の場所。
あれから青山山・高戸谷山・音羽山・板沢山と何回も出会っているから
今なら慌てないだろう。

峠道を少し離れたところに石宮、今日の無事を感謝。

猪のドロ場を過ぎると

間もなく園地に到着で立派な東屋(14.17)。

ややお疲れ模様の本日の爺イ。
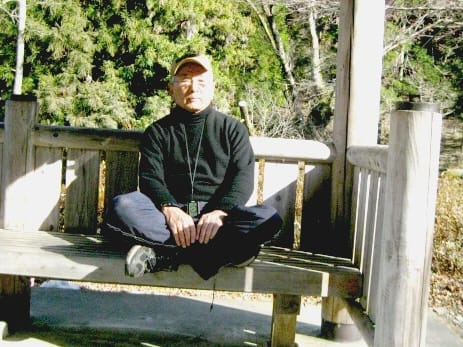

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

這い出すことにした。春一番を伴っていることがチョイ不安だが。
目的は延び延びになっていた「古い亀穴峠道」を地形図の破線通りに
しっかりと確認することだ。

破線の位置に行くのには幾通りもあるが、今日は始めてのルート。
甘楽町・上鳥屋の天引森林公園園地から一旦北に廻って三角点・天引
484.8mのある南北稜線に登り上げ三角点にタッチしてから
南進して亀穴峠直下の破線を目指すもの。
この複雑な稜線は数年前に下ったことはあるが登るのは初体験。
堂の入り林道と鳥屋林道の間に横たわる曲がりくねった稜線。
数多くのコブや爺イにはピークに感ずる稜線上の突起があって
乗り越しか? 迂回か? と考える里山の醍醐味十分。
吉井からR-254を西進、「金井信号」で左折して3.3K、
変則四つ角で鳥屋林道の残雪のある川筋の細道を低速で2.5K。
雪解けの森林公園園地には駐車車両なし。本日も完全な一人旅。
支度しながら西の方角を観察、この山の奥、直線距離で440Mに
南北大稜線がある筈(9.14)。

園地の裏から三角点探索の時とルートを変えて右(北)に進む。
直ぐに尾根を巻く笹原になるが、良く観察すればその下に薄い
道形が確認できる。

尾根を一つ跨ぐと山側に石垣がずっと続き、手前は平地。
どう見ても昔の生活の跡と推定できる。

石垣を乗り越えて上の林に入ると大型の石宮。銘は読み取れない。

さて、この辺から西に向かって目前の斜面の小尾根に取り付く。

一コブ越えて更に進むと見覚えのある広い場所。園地から直接西に
向かって大きな窪を登ってくると写真の左側からここに到達
するのだ(9.45)。

左目の二段構えのコブに取り付き何とか乗り切ると境界杭293。
この線は町村境界でもないのにと訝りながら西進する。

間もなく前面に小ピーク、これを越えると本格的な稜線への
斜面登りとなる。赤テープもあるので迷わず前進。

稜線が見えたが大変な急斜面だ。

下ばかり見て歩いて気が付いたら大岩の直下。これは無理だ。

周囲を観察して右(北)への獣道風の踏み跡を発見、迂回して稜線着。
左には迂回した岩の突起。三角点の右方向はこんな下り尾根。

二段のコブを下って100Mほどの崖に下る突端に三角点(10.32)。
この地は甘楽町大字天引字天引国有林、点の記を見ると堂ノ入林道の
国有林ゲートから数百㍍南から東の稜線に来るようになっている。


さて、小休止してからさっきの稜線到達点に戻る。いよいよ、南進の始まり。
直ぐに第一番の突起。さっき回避した小ピークだ。

下ったところに赤テープ、これは数年前に下ってきた時の降口。
東へ急降の踏み跡も確認できる。

二つ目はコブ、高度差は少ないので楽に突破。

三つ目はやや大きい岩峰、両側が削がれているので逃げ場は無く
頑張って直登で乗り越え。

四つ目は似たような突起だが右に曲がっているので鞍部を目指して
急斜面を恐々と迂回(11.00)。

鞍部に着いたら直ぐに五つ目の突起が目の前。息つく間もなく
右から抜ける。

六つ目は正面からピークに行き分岐を左に行ったのは良いがその先が断崖で
足が竦んで降りられない。情けなくももう一度ピークに
登り返して西尾根を下って途中からに南尾根にトラバース。
極めて危険で必死の思い。

何とか回りきって振り返り。確かにここは爺イの手に余る。

七つ目は正面突破。

八つ目は登りは軽くてピークの分岐から左へ。だが、再び断崖で
立ち往生。一旦恐怖感じた後に強行するのは危ないので
戻ってトラバース。

回りきって今度も振り返ってホントに駄目だったのかを確認。
このトラバースに大苦戦、20分も費やした(11.44)。

十歩も歩かないうちに九つ目。

手前に何かの工事用鉄くず。
こんな所で何をしたんだろうか?

こんなヤセ尾根でやれ安心と思ったら先端がストンと切れていて
再び恐怖の崖下り。もう、大分ビビって居るので過剰に反応しているのが
自分でよく分かるが進むしかない。

十個目で漸く地形図上の579M地点に掛かるが上が見えないので
ゲンナリ。

東南を見ると通称・摩利支天とか天引山と云われる699.5Mの
山が見える。未だ半分を過ぎただけなのにもう少しと元気が出る。

579M地点の長い台地を下りに掛かると二回も分岐で全て左。
綺麗に整備された杉林、今までのギスギスした緊張感が緩む。

11ヶ目はゆったりした登り。足にも負担無く気分は楽。

次の12ヶ目は岩の露出した風変わりな突起。左に行くので
頂上手前でショートカット。

新しい稜線に到着で小休止。

やがて前方に明るい視界。どうやら亀穴山(仮称)の近くに来たらしい。
ナビの電源を入れて破線位置を注視しながら進む。

広い場所に出た。藤岡境界も近く古い峠道は此処を通っている筈。

残雪があるので慎重に道形を探すと多分之というのを確認できた。
写真の雪が点々と溶けているのは動物の歩いた跡、その右に
見える微かな凹みが峠道。

この道は確実に破線通りに東に向かって尾根跨ぎに走っている。

だが、一尾根跨いで林に入ると大荒れでやや不安。

窪を廻って下ると園地からの峠道に合流。遂に古い峠道分岐を確認。

合流点の枯れ木にマークを付けた。唯の巻きつけだから数年の
後にはビニールの劣化で縮んで自然に落下するからさしたる
邪魔物ではない(13.12)。

しかし、地形図の峠道の破線がこの古い道だけなのはオカシイ。
現在、園地からの峠道は無理なく鳥屋峠に延びているし
藤岡側にある「道しるべに」にもはっきりと「新屋・天引」と
刻まれているから鳥屋峠と亀穴峠は同等に扱ってもらいたいものだ。

気温は高いが予報どおりの春一番がやってきたのか? 風も強く
なる気配なので峠には行かずにこんな大木の陰で遅い昼食(---13.33)。

休憩後、下山に掛かる。荒れた道を下ってこの沢に降り立つ。

ここからの峠道も大荒れ状態。

こんな倒木がーーと思ったら切り口からして伐採材の放置。

途中に小さな切通し、往路で見ると峠に見える。

目印の大銀杏前を通過、爺イが始めて熊に遭遇し恐怖で
固まって身動き出来なかった嫌な記憶の場所。
あれから青山山・高戸谷山・音羽山・板沢山と何回も出会っているから
今なら慌てないだろう。

峠道を少し離れたところに石宮、今日の無事を感謝。

猪のドロ場を過ぎると

間もなく園地に到着で立派な東屋(14.17)。

ややお疲れ模様の本日の爺イ。
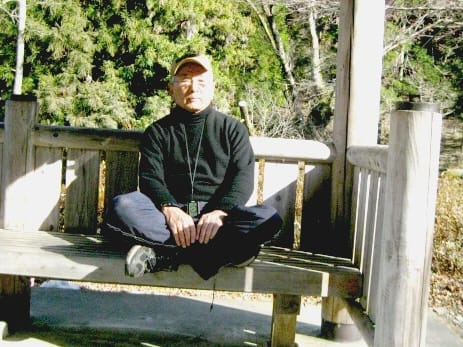

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます