4月といえば、春を呼ぶ祭り。新潟県糸魚川市一の宮にある天津神社の「けんか祭り」が有名だ。これが4月10日に行われ、午前中の神輿渡御、寺町地区、押上地区の2基の神輿がぶつかり合う「けんか神輿」で盛り上がる。そして午後は国の重要無形文化財指定の舞楽 が行われる。
今年は11日に休みが取れた。実は天津神社舞楽は2日目の午後1:00からにも、舞楽のみ行われる。1日目とは演目は同じなのだが、面や装束が異なる。2日目の方が古い形を残しているとうだ。今年は、久しぶりにそちらに行ってみることにした。
昼過ぎを目指して糸魚川に向かった。市内で昼食のために立ち寄った食事処で新聞を何気なく見ていると、やはり天津神社の祭りの記事があった。やはり春を呼ぶ祭りなのだ。
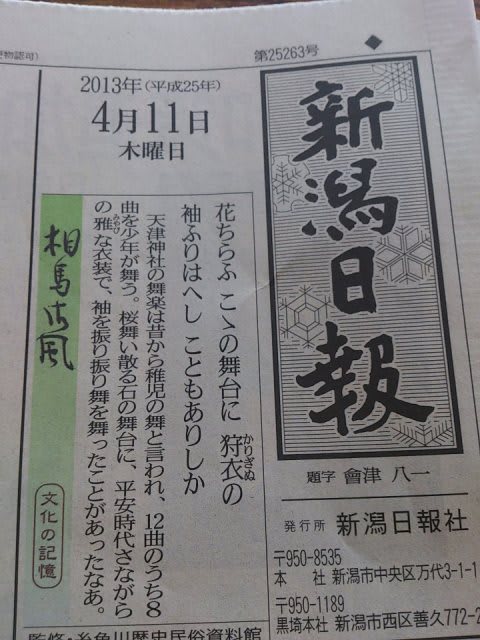

神社へは12:00を少し廻ったころだ。午前中は天気もよく安心していたが、だんだん雲行きがあやしくなってきた。この2日目の舞楽は雨天中止なのだ。祈るような気持ちで、時を待つ。
すると楽人たちの太鼓が始まった。やがて雨が落ちてきた。

心配したが、小降りにもなり、舞楽がスタートした。
まず「鉾振」。

これは舞楽では必ず、始めに舞われる。舞台を清める意味もある舞で、鉾を振る所作で知られる。1日目とは装束の色は赤系と緑系であるが、2日目は落ち着いた色合いとなっている。
続いて「安摩」。

これは、能生の舞楽 「童羅利」に似ていると言われる。確かに上半身を前に出し、両手を後方に伸ばす動作は似ている。この演目も1日目と異なり、2日目は面を着けないが、1日目は能面風の面を着ける。
続いて「鶏冠」「抜頭」「破魔弓」を省略し「児納曽利」となった。

「納曽利」とはいえ、舞楽面ではなく能面風、里神楽風なものを着けている。
続いて今回は「能抜頭」であった。

面は白い神楽風の表情、渋い色の装束だ。動きも、身体を後ろに大きく反ったり、足を大きく上げたりなど、激しい動作が印象的。

続いて「華籠」。

手には大きな牡丹を供えた仏具の散華皿を持って舞い、花びらでもまき散らすかのような所作をする。仏式の行事のようだ。

だんだん天気も下り坂。続いて「大納曽利」。

これも1日目は、青い納曽利面に牟子という帽子状の被り物をするが、2日目はシャグマといったたてがみのような被り物に、赤黒い奇怪な表情という姿。これも地方舞楽ならではの面白さだ。
しかし雨脚が強まってきた。舞手には楽人によって傘がさされた。

かなりの雨で、気温も下がってきた。がんばって舞い続けられた。
しかし雨がひどく、結局ここで終了となってしまった。最後の「陵王」も演じられなかった。残念だがやむを得ない。
「陵王」は、糸魚川では「竜王」とも呼ばれる。竜といえば、北陸地方では白山の「九頭竜権現」をイメージするが、「竜」の信仰は雨乞いにつながる。地方の舞楽では「陵王」を雨を呼ぶ竜の神様に附会されることが多い。雨が降ってしまったのだから、「陵王」の舞は要らないのだ…と自分に言い聞かせた。
最後の楽人の「ドンデンドン」の太鼓は、なかなか聴かせる。客席にいた方々も、雨にも関わらず楽舎の前に集まってきて、太鼓を見つめる。そして、かけ声をかける。何ともいい雰囲気で祭りを終えた。
また来年、天津神社へは来られるといいなと思いつつ、天津神社を後にした。
今年は11日に休みが取れた。実は天津神社舞楽は2日目の午後1:00からにも、舞楽のみ行われる。1日目とは演目は同じなのだが、面や装束が異なる。2日目の方が古い形を残しているとうだ。今年は、久しぶりにそちらに行ってみることにした。
昼過ぎを目指して糸魚川に向かった。市内で昼食のために立ち寄った食事処で新聞を何気なく見ていると、やはり天津神社の祭りの記事があった。やはり春を呼ぶ祭りなのだ。
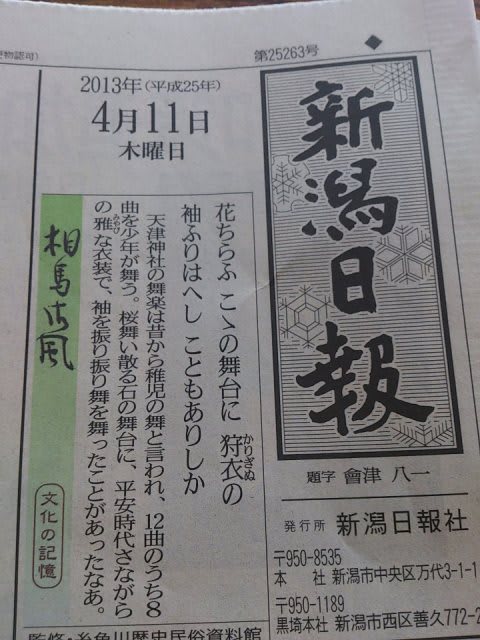

神社へは12:00を少し廻ったころだ。午前中は天気もよく安心していたが、だんだん雲行きがあやしくなってきた。この2日目の舞楽は雨天中止なのだ。祈るような気持ちで、時を待つ。
すると楽人たちの太鼓が始まった。やがて雨が落ちてきた。

心配したが、小降りにもなり、舞楽がスタートした。
まず「鉾振」。

これは舞楽では必ず、始めに舞われる。舞台を清める意味もある舞で、鉾を振る所作で知られる。1日目とは装束の色は赤系と緑系であるが、2日目は落ち着いた色合いとなっている。
続いて「安摩」。

これは、能生の舞楽 「童羅利」に似ていると言われる。確かに上半身を前に出し、両手を後方に伸ばす動作は似ている。この演目も1日目と異なり、2日目は面を着けないが、1日目は能面風の面を着ける。
続いて「鶏冠」「抜頭」「破魔弓」を省略し「児納曽利」となった。

「納曽利」とはいえ、舞楽面ではなく能面風、里神楽風なものを着けている。
続いて今回は「能抜頭」であった。

面は白い神楽風の表情、渋い色の装束だ。動きも、身体を後ろに大きく反ったり、足を大きく上げたりなど、激しい動作が印象的。

続いて「華籠」。

手には大きな牡丹を供えた仏具の散華皿を持って舞い、花びらでもまき散らすかのような所作をする。仏式の行事のようだ。

だんだん天気も下り坂。続いて「大納曽利」。

これも1日目は、青い納曽利面に牟子という帽子状の被り物をするが、2日目はシャグマといったたてがみのような被り物に、赤黒い奇怪な表情という姿。これも地方舞楽ならではの面白さだ。
しかし雨脚が強まってきた。舞手には楽人によって傘がさされた。

かなりの雨で、気温も下がってきた。がんばって舞い続けられた。
しかし雨がひどく、結局ここで終了となってしまった。最後の「陵王」も演じられなかった。残念だがやむを得ない。
「陵王」は、糸魚川では「竜王」とも呼ばれる。竜といえば、北陸地方では白山の「九頭竜権現」をイメージするが、「竜」の信仰は雨乞いにつながる。地方の舞楽では「陵王」を雨を呼ぶ竜の神様に附会されることが多い。雨が降ってしまったのだから、「陵王」の舞は要らないのだ…と自分に言い聞かせた。
最後の楽人の「ドンデンドン」の太鼓は、なかなか聴かせる。客席にいた方々も、雨にも関わらず楽舎の前に集まってきて、太鼓を見つめる。そして、かけ声をかける。何ともいい雰囲気で祭りを終えた。
また来年、天津神社へは来られるといいなと思いつつ、天津神社を後にした。















