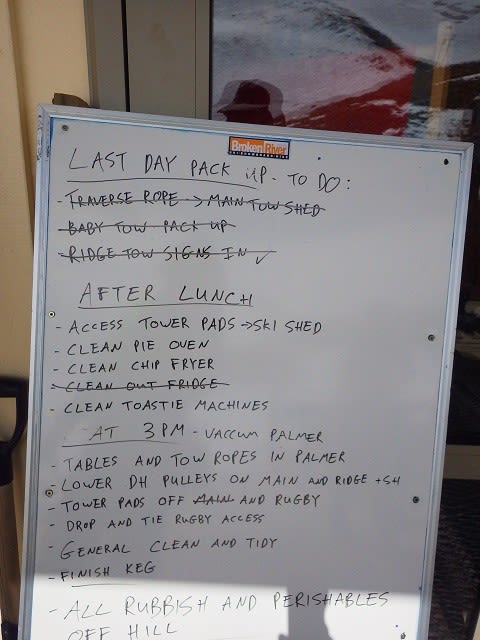クィーンズタウンから正面に見える岩山がリマーカブルズである。
これは連峰の名称で主峰はダブルコーンとシングルコーンという尖った岩山だ。
僕は15年ぐらい前にこの山に登ろうとしたことがある。
その時は岩にうっすらと雪が乗った状態で、登れることは登れるだろうが降りられないだろうな、と山頂直下であきらめた。
その時に一緒に登ったのがお馴染みトーマスである。
今回は雪がついているから、どうせなら山頂から滑っちゃおうとトーマスを誘った。
タンケンツアーズのボスのリチャードに話をすると、それなら途中まで一緒に行くということで3人で山へ向かった。
前回は一人で山へ行ったが、今回は3人。
一人で自分の世界に浸りながら行くのも良いが、気心の知れた仲間と山に行くのも良い。


リフト脇を登り、湖のそばで小休止。そして前回滑ってきたルートを登る。
サドルまで出てリチャードはそこから下り、僕とトーマスは再び登り始めた。
リチャードのスキー板は細いので、緩んだ雪に沈んでしまいそこから上へは行けない。
なので彼は一足先に降りて湖のほとりで僕達を待つ。



サドルから1時間ほどスキーで登ると頂上までの急斜の下へたどりついた。
スキーで上がれるのもここまで、ここでスキーをバックパックにつけて登る。
岩の隙間の雪がついている所を一歩一歩、両手を使いながらよじ登る。
前回、登頂を断念した場所もここだ。



急な場所を登りきると一気に景色が広がる。
眼下には真っ青な水を湛えたワカティプ湖、遠くに雪を載せた南アルプス、そして目の前にはダブルコーンが見えた。
山頂までは20mほど、両側が切り落ちたナイフリッジを行く。
一歩踏み外せば岩場を滑落するので、慎重に歩を進め山頂にたどり着いた。


地元の新聞に9歳の女の子が父親と一緒にシングルコーンを登って滑った記事があった。
世界のてっぺんにいるようだったという女の子のコメントが載っていた。
確かにここに立てばそう思うだろう。
いつも遠くから見ているダブルコーンが目の前にある。
何百回、この山を街から見上げたことだろう。
似たような景色を体験して行った気になるのと、実際に自分がその場所に立つのとでは違うものがある。
今はバーチャル・リアリティーなどというものがあるようで。色々な事柄が本物のように体験できるらしい。
だが一歩踏み間違えれば死ぬ、というようなピリピリした緊張感と同時に存在する景色の美しさは体験できないと思う。
それこそが生きる証ではなかろうか。
そして僕はそれを大切にしたい。





急な山は登るより下る方が大変である。
事故の確率が多いのも下りである。
雪がついていればスキーで下る方が歩くより安全だ。
それはスキーの技術があればの話である。
スキーの技術があっても高度にびびってしまえば普段通りに滑れなくなる。
先行した二人組はたぶん怖くなってしまったのだろう。
岩場をゆっくり三転確保の姿勢で下って行ったが、僕とトーマスは頂上からスキーで下ることにした。
二人組が下っている斜面を避け、その横の雪がついている所から下り始めた。
まっさらな斜面にスキーで踏み込むと同時に、表面20cmぐらいの緩んだ雪が足元から雪崩始めた。
雪は斜面を滑り落ち、その下の崖に吸い込まれるように消えていく。
雪が見えなくなってからもしばらくは音が続いていた。
この下には人はいないはずだよな、大丈夫大丈夫、ここは登ってくるルートじゃない、そんな想いが頭をよぎった。
雪が落ち着いてからゆっくりと下る。
斜度は50度を超えていることだろう。
雪の少ない岩場を超えればダブルコーンとシングルコーンの間のシュートが見えてきた。
ここからはお楽しみの時間だ。
斜度が急なので緩んだ雪がすぐに落ちる。
その雪に足をすくわれないように滑っていく。
すでにアドレナリンは全開、全身全霊をかけて滑る。
狭いシュートを抜け、荒れていないリップを見つけては当て込み、岩を避けながらターンを刻んだ。





湖のところまで滑るとリチャードが待ちくたびれた顔で言った。
「お前たち、よくやったな。あまりに時間がかかるから落ちたんじゃないかと、携帯に何回も電話したんだぞ」
「あ、いけねえ、携帯、車に置いて来てた」
「バカだなあ」
下までまったりと滑り、車に戻ると案の定、携帯にはリチャードからのコールがいくつも入っていた。
家に帰り、装備を干して、夕餉の支度。
トーマスは今晩泊まりなので、男二人で七輪ナイトなのだ。
シマアジの良さそうな奴があったので捌いて刺身。
アスパラのベーコン巻き、焼きナス、マッシュルーム、シマアジのあら、豚肉の酒粕と味噌漬けなどを七輪で焼く。
先ずは自慢のボヘミアンピルスナーで乾杯。
そして全黒の酒とトーマスが造った酒。
気の合う仲間と山へ行くのもいいが、気の合う仲間と七輪を囲み酒を飲むのも良い。
シングルコーンからの滑降。
50歳の節目というタイミングにあの山を滑ったことは一生ものの思い出になった。
きっとあの山を見る度に僕はこの日の事を思い出すだろう。


これは連峰の名称で主峰はダブルコーンとシングルコーンという尖った岩山だ。
僕は15年ぐらい前にこの山に登ろうとしたことがある。
その時は岩にうっすらと雪が乗った状態で、登れることは登れるだろうが降りられないだろうな、と山頂直下であきらめた。
その時に一緒に登ったのがお馴染みトーマスである。
今回は雪がついているから、どうせなら山頂から滑っちゃおうとトーマスを誘った。
タンケンツアーズのボスのリチャードに話をすると、それなら途中まで一緒に行くということで3人で山へ向かった。
前回は一人で山へ行ったが、今回は3人。
一人で自分の世界に浸りながら行くのも良いが、気心の知れた仲間と山に行くのも良い。


リフト脇を登り、湖のそばで小休止。そして前回滑ってきたルートを登る。
サドルまで出てリチャードはそこから下り、僕とトーマスは再び登り始めた。
リチャードのスキー板は細いので、緩んだ雪に沈んでしまいそこから上へは行けない。
なので彼は一足先に降りて湖のほとりで僕達を待つ。



サドルから1時間ほどスキーで登ると頂上までの急斜の下へたどりついた。
スキーで上がれるのもここまで、ここでスキーをバックパックにつけて登る。
岩の隙間の雪がついている所を一歩一歩、両手を使いながらよじ登る。
前回、登頂を断念した場所もここだ。



急な場所を登りきると一気に景色が広がる。
眼下には真っ青な水を湛えたワカティプ湖、遠くに雪を載せた南アルプス、そして目の前にはダブルコーンが見えた。
山頂までは20mほど、両側が切り落ちたナイフリッジを行く。
一歩踏み外せば岩場を滑落するので、慎重に歩を進め山頂にたどり着いた。


地元の新聞に9歳の女の子が父親と一緒にシングルコーンを登って滑った記事があった。
世界のてっぺんにいるようだったという女の子のコメントが載っていた。
確かにここに立てばそう思うだろう。
いつも遠くから見ているダブルコーンが目の前にある。
何百回、この山を街から見上げたことだろう。
似たような景色を体験して行った気になるのと、実際に自分がその場所に立つのとでは違うものがある。
今はバーチャル・リアリティーなどというものがあるようで。色々な事柄が本物のように体験できるらしい。
だが一歩踏み間違えれば死ぬ、というようなピリピリした緊張感と同時に存在する景色の美しさは体験できないと思う。
それこそが生きる証ではなかろうか。
そして僕はそれを大切にしたい。





急な山は登るより下る方が大変である。
事故の確率が多いのも下りである。
雪がついていればスキーで下る方が歩くより安全だ。
それはスキーの技術があればの話である。
スキーの技術があっても高度にびびってしまえば普段通りに滑れなくなる。
先行した二人組はたぶん怖くなってしまったのだろう。
岩場をゆっくり三転確保の姿勢で下って行ったが、僕とトーマスは頂上からスキーで下ることにした。
二人組が下っている斜面を避け、その横の雪がついている所から下り始めた。
まっさらな斜面にスキーで踏み込むと同時に、表面20cmぐらいの緩んだ雪が足元から雪崩始めた。
雪は斜面を滑り落ち、その下の崖に吸い込まれるように消えていく。
雪が見えなくなってからもしばらくは音が続いていた。
この下には人はいないはずだよな、大丈夫大丈夫、ここは登ってくるルートじゃない、そんな想いが頭をよぎった。
雪が落ち着いてからゆっくりと下る。
斜度は50度を超えていることだろう。
雪の少ない岩場を超えればダブルコーンとシングルコーンの間のシュートが見えてきた。
ここからはお楽しみの時間だ。
斜度が急なので緩んだ雪がすぐに落ちる。
その雪に足をすくわれないように滑っていく。
すでにアドレナリンは全開、全身全霊をかけて滑る。
狭いシュートを抜け、荒れていないリップを見つけては当て込み、岩を避けながらターンを刻んだ。





湖のところまで滑るとリチャードが待ちくたびれた顔で言った。
「お前たち、よくやったな。あまりに時間がかかるから落ちたんじゃないかと、携帯に何回も電話したんだぞ」
「あ、いけねえ、携帯、車に置いて来てた」
「バカだなあ」
下までまったりと滑り、車に戻ると案の定、携帯にはリチャードからのコールがいくつも入っていた。
家に帰り、装備を干して、夕餉の支度。
トーマスは今晩泊まりなので、男二人で七輪ナイトなのだ。
シマアジの良さそうな奴があったので捌いて刺身。
アスパラのベーコン巻き、焼きナス、マッシュルーム、シマアジのあら、豚肉の酒粕と味噌漬けなどを七輪で焼く。
先ずは自慢のボヘミアンピルスナーで乾杯。
そして全黒の酒とトーマスが造った酒。
気の合う仲間と山へ行くのもいいが、気の合う仲間と七輪を囲み酒を飲むのも良い。
シングルコーンからの滑降。
50歳の節目というタイミングにあの山を滑ったことは一生ものの思い出になった。
きっとあの山を見る度に僕はこの日の事を思い出すだろう。