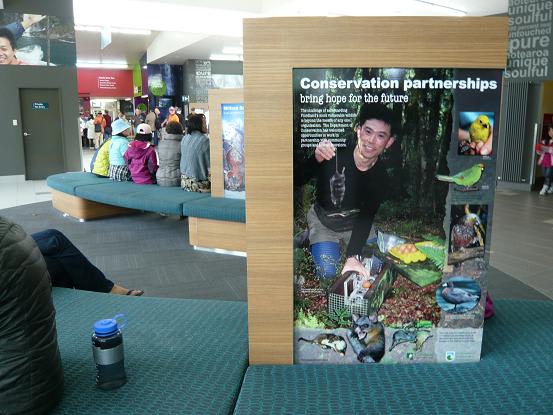ボクがよく言う言葉だが、幸せは常にここにある。
その幸せとは何か?
それは人によって違う。
違って当たり前である故に、同じ事で幸せを感じると嬉しい。
ご飯を一人で食べるより誰かと一緒に食べるのが美味しいというのはそういうことだ。
一緒にお酒を飲むと楽しい。
一緒にパウダーを滑ると楽しい。
一緒に山歩きをすると楽しい。
全てそれである。
これが幸せのバイブレーションだ。
だが人間というものは九割が幸せで満たされていても残りの一割に意識を向けてしまう。
「○○がないから自分は不幸せだ」と言う人は多い。
そしてそれを人のせいにする。
幸いなことに僕の周りにそういう人はいない。
以前聞いた話だが、ある人はニュージーランドに住んでいることに幸せを感じられず、いつも日本に帰りたいと言っているそうだ。
じゃあ帰ればいいじゃないか、と言うと旦那に騙されてここに住むはめになったと言う。
ではそんな騙すような旦那を選んだ自分の責任はどこへいったのだろう。
ニュージーランドに住むと決めたのは自分の選択ではなかったのか?
そういう人と話をしても出てくる言葉は「でもね・・・」とか「だって・・・」であり会話が進まない。
多分ここで文句を言っている人は、たとえ日本に帰っても文句を言い続けることだろう。
その人の意識が不満に向かっているうちは、どんな状態であれ不満なのだ。
もしそういう人がボクの前に現れたら、ボクはちびまるこちゃんに出てくる丸尾君のように「ずばり、あなたは自分自身を不幸せにしているでしょう」と言いきってしまう。
そしてそういう人は本質を突きつけられる事を潜在的に怖れている。
なので僕の前に現れない。
よってボクの周りには幸せな人が集まってくる。
引き寄せの法則どおりである。
自分の意識をどこに向けるか。
当たり前にご飯が食べられることに意識を向けるか。
美味しい水が飲めることに意識を向けるか。
健康で働けることに意識を向けるか。
家族と一緒に過ごせることに意識を向けるか。
それとも自分にはこれが足りないという、足りないものに意識を向けるか。
あとは本人次第であり、ボクがなんと言おうと「でもね」と言い続ける人にはボクの言葉は伝わらない。
さらに追い討ちをかければ「でもね」の人が聞きたい言葉とは
「そうだそうだ、あなたは悪くない。悪いのは○○だ。」
○○の所に入る言葉は、同僚、友達、家族、上司、ひいては会社、国、社会、世界。
なんでもありだな。
「あなたの考え、行動が今ある状況を創りあげているんですよ」
と言うと逆切れして
「じゃあ私が悪いと言うの?」
と怒り出す。
良いとか悪いとかの問題ではないということが理解できない。
お話にならないとはこういうことだ。
何をもって幸せと呼ぶかはその人の価値観に基づくものなので他人があれこれ言っても仕方が無い。
貯金が趣味で銀行口座のお金が増えるのを見るのが楽しみ、という人の話を聞いたことがあるが、それでその人が幸せならばそれでいいだろう。
あなたの価値観は間違っていますよ、などと言い出すことなど大きなお世話であり、押し付けの考えこそ間違っている。
ただ自分とは違う、それだけなのだ。
ボクの幸せとは健康で美味い物を食うというものだから、その努力を惜しまない。
最高に美味い卵かけご飯を食べるためにニワトリを飼い、土鍋でご飯を炊く。
ある友達はこれを食べて「卵かけご飯、やばいです」と言った。
そうそれぐらいに美味いのだ。
そういう話をお客さんにもするが、ある人はすごく理解をしてくれるがある人は興味を示さない。
ただ、家の卵かけご飯の旨さはボクが知っている。
そしてその瞬間の幸せはどこか遠い記憶で残っているものだ。
人間は生まれてきた時に、全ての記憶を消して生まれてくる。
生まれたばかりだと覚えていても成長するにつれ忘れてしまうものらしい。
一杯の水を飲んで幸せだった記憶。
美味しい健康的な食べ物を食べて幸せだった記憶。
その他全ての幸せな記憶。
幸せとは思い出すことである。
意識をどこに向けるのか。
それは個人の選択である。
それによって今ある状況は天国にも地獄にもなる。
天国と地獄はあの世にあるのではない。
今、この状態でこの世にあるのだ。
それに気づき思い出した時、全ての物事は信じられないくらいスムーズに動く。
ネガティブな要素が無いわけではない。
先日は家のニワトリのペケが死んでしまった。
その前日まで元気に卵を産んでいたのだが、ある日突然死んでしまった。
自給自足を目指すなどとエラソーなことを言っているが、ボクはその鶏を食べる気になれなかった。
気が乗らないものは仕方がない。
庭の片隅に穴を掘り鶏を埋めその上にフィジョアの木を植えた。
娘が水をかけ、家族三人で手を合わせ拝んだ。
生きとし生けるものは全て死ぬ。
この世の道理である。
鶏が死んでしまったことは悲しかったが、ボクは家族でこういうことをすることに幸せを覚えた。
いずれこの木も大きくなり実をつけてくれることだろう。
そしてその実を食べ「ああ幸せだな」などと言うだろう。
意識をどこに向けるか。
そして幸せであることを思い出すことにより、自分を高め周りを明るくする。
それを感じる瞬間。
それがこの世に生まれてきた理由であり、全ての答はそこにある。
その幸せとは何か?
それは人によって違う。
違って当たり前である故に、同じ事で幸せを感じると嬉しい。
ご飯を一人で食べるより誰かと一緒に食べるのが美味しいというのはそういうことだ。
一緒にお酒を飲むと楽しい。
一緒にパウダーを滑ると楽しい。
一緒に山歩きをすると楽しい。
全てそれである。
これが幸せのバイブレーションだ。
だが人間というものは九割が幸せで満たされていても残りの一割に意識を向けてしまう。
「○○がないから自分は不幸せだ」と言う人は多い。
そしてそれを人のせいにする。
幸いなことに僕の周りにそういう人はいない。
以前聞いた話だが、ある人はニュージーランドに住んでいることに幸せを感じられず、いつも日本に帰りたいと言っているそうだ。
じゃあ帰ればいいじゃないか、と言うと旦那に騙されてここに住むはめになったと言う。
ではそんな騙すような旦那を選んだ自分の責任はどこへいったのだろう。
ニュージーランドに住むと決めたのは自分の選択ではなかったのか?
そういう人と話をしても出てくる言葉は「でもね・・・」とか「だって・・・」であり会話が進まない。
多分ここで文句を言っている人は、たとえ日本に帰っても文句を言い続けることだろう。
その人の意識が不満に向かっているうちは、どんな状態であれ不満なのだ。
もしそういう人がボクの前に現れたら、ボクはちびまるこちゃんに出てくる丸尾君のように「ずばり、あなたは自分自身を不幸せにしているでしょう」と言いきってしまう。
そしてそういう人は本質を突きつけられる事を潜在的に怖れている。
なので僕の前に現れない。
よってボクの周りには幸せな人が集まってくる。
引き寄せの法則どおりである。
自分の意識をどこに向けるか。
当たり前にご飯が食べられることに意識を向けるか。
美味しい水が飲めることに意識を向けるか。
健康で働けることに意識を向けるか。
家族と一緒に過ごせることに意識を向けるか。
それとも自分にはこれが足りないという、足りないものに意識を向けるか。
あとは本人次第であり、ボクがなんと言おうと「でもね」と言い続ける人にはボクの言葉は伝わらない。
さらに追い討ちをかければ「でもね」の人が聞きたい言葉とは
「そうだそうだ、あなたは悪くない。悪いのは○○だ。」
○○の所に入る言葉は、同僚、友達、家族、上司、ひいては会社、国、社会、世界。
なんでもありだな。
「あなたの考え、行動が今ある状況を創りあげているんですよ」
と言うと逆切れして
「じゃあ私が悪いと言うの?」
と怒り出す。
良いとか悪いとかの問題ではないということが理解できない。
お話にならないとはこういうことだ。
何をもって幸せと呼ぶかはその人の価値観に基づくものなので他人があれこれ言っても仕方が無い。
貯金が趣味で銀行口座のお金が増えるのを見るのが楽しみ、という人の話を聞いたことがあるが、それでその人が幸せならばそれでいいだろう。
あなたの価値観は間違っていますよ、などと言い出すことなど大きなお世話であり、押し付けの考えこそ間違っている。
ただ自分とは違う、それだけなのだ。
ボクの幸せとは健康で美味い物を食うというものだから、その努力を惜しまない。
最高に美味い卵かけご飯を食べるためにニワトリを飼い、土鍋でご飯を炊く。
ある友達はこれを食べて「卵かけご飯、やばいです」と言った。
そうそれぐらいに美味いのだ。
そういう話をお客さんにもするが、ある人はすごく理解をしてくれるがある人は興味を示さない。
ただ、家の卵かけご飯の旨さはボクが知っている。
そしてその瞬間の幸せはどこか遠い記憶で残っているものだ。
人間は生まれてきた時に、全ての記憶を消して生まれてくる。
生まれたばかりだと覚えていても成長するにつれ忘れてしまうものらしい。
一杯の水を飲んで幸せだった記憶。
美味しい健康的な食べ物を食べて幸せだった記憶。
その他全ての幸せな記憶。
幸せとは思い出すことである。
意識をどこに向けるのか。
それは個人の選択である。
それによって今ある状況は天国にも地獄にもなる。
天国と地獄はあの世にあるのではない。
今、この状態でこの世にあるのだ。
それに気づき思い出した時、全ての物事は信じられないくらいスムーズに動く。
ネガティブな要素が無いわけではない。
先日は家のニワトリのペケが死んでしまった。
その前日まで元気に卵を産んでいたのだが、ある日突然死んでしまった。
自給自足を目指すなどとエラソーなことを言っているが、ボクはその鶏を食べる気になれなかった。
気が乗らないものは仕方がない。
庭の片隅に穴を掘り鶏を埋めその上にフィジョアの木を植えた。
娘が水をかけ、家族三人で手を合わせ拝んだ。
生きとし生けるものは全て死ぬ。
この世の道理である。
鶏が死んでしまったことは悲しかったが、ボクは家族でこういうことをすることに幸せを覚えた。
いずれこの木も大きくなり実をつけてくれることだろう。
そしてその実を食べ「ああ幸せだな」などと言うだろう。
意識をどこに向けるか。
そして幸せであることを思い出すことにより、自分を高め周りを明るくする。
それを感じる瞬間。
それがこの世に生まれてきた理由であり、全ての答はそこにある。