
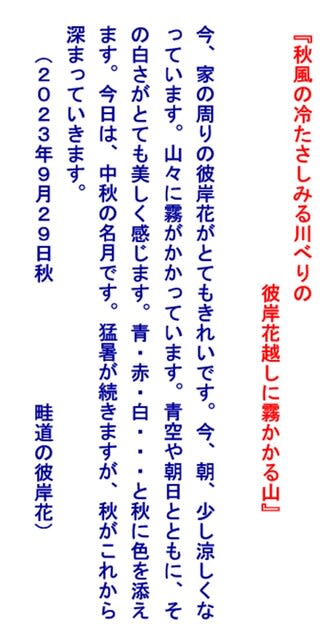
今日は、中秋の名月です。
夜、道路を歩いていると、今日の夜空は雲もなく、月がとてもきれいに輝いていました。

中秋の名月といえば、月見団子。
「ひと昔。秋は作物の収穫期。月が満ちた姿を模した丸い団子は、豊作への祈りや感謝はもちろん、物事の結実や幸福の象徴ともされ、供えた後の団子を食べることで健康と幸福を得られると考えられています。

月がよく見える場所に台を置き、十五夜にちなみ15個の団子を大皿にうず高く盛るのが昔ながらの伝統的な供え方。
そうかあ。15個か。
食べすぎないように気をつけよう。山のような形に団子を積むのは、一番上の団子が霊界に通じると信じられていたからともいわれています。」
なるほど。昔の人は、いろいろと考えています。
でも一番上の団子は食べることができるのだろうか。

そして、さらに月を見るなら、すすき。
「背の高い稲穂は神様が降り立つ「依り代(よりしろ)」だと信じられてきました。
そのため神様へのお供え物として米や稲穂をよく用いましたが、中秋の名月の時期はまだ穂が実る前です。
それで、形が似ているススキを稲穂の代わりに供えたことが風習の起源だといわれています。」

クラスの子どもたちにも、帰りの会の時に、中秋の名月の話をしました。

「今日、見よう。」
という子どももいました。
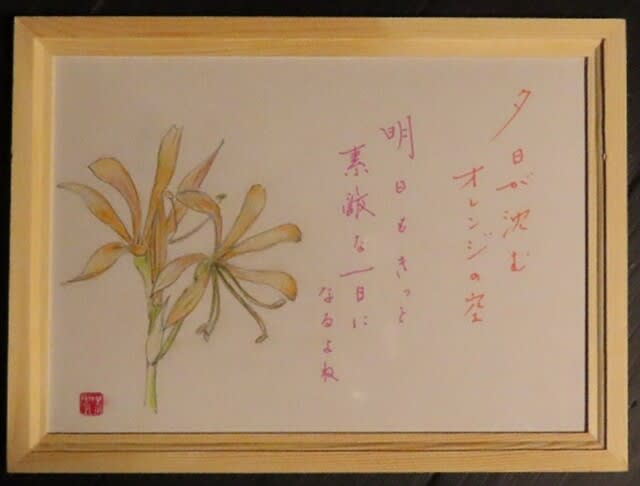
中秋の名月。ちょっと気持ちよい川風を浴びながら、眺めることができました。




















