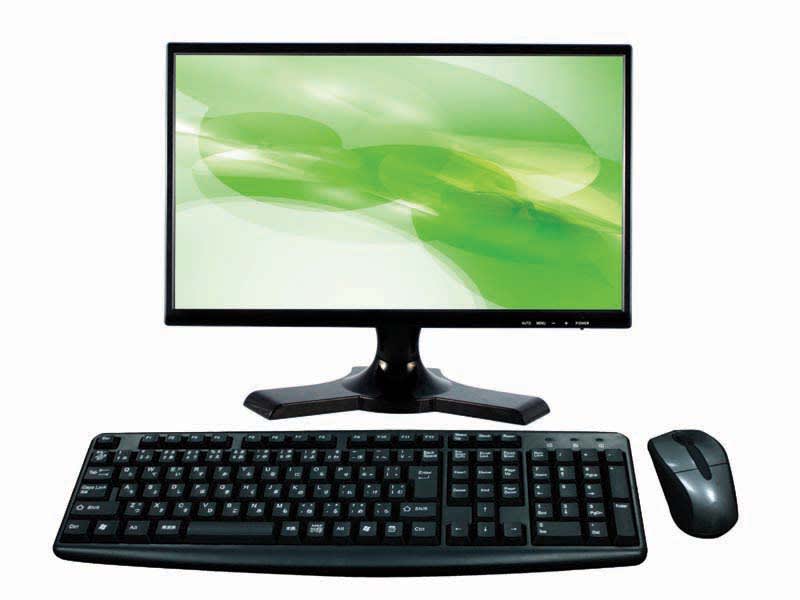年末があわただしさを運んでも
年末があわただしさを運んでも動きの中にも心にゆとり

明日から12月です。受験という空気の中から、また街に出ると、流れる音楽から年末という雰囲気が出てきています。毎朝、BGMを学校に着いてから校内に流しているのですが、昨日から、ちょっとおしゃれして、「クリスマスソング」(オルゴール)を選曲しました。廊下に出て、クリスマスソングのオルゴールの音色を聴いていると、なんとなくうきうきしてきます。(自己満足かもしれない・・・)
しかし、学校はクリスマスの訪れが近くなるとともに、年末。一昨日から昨日にかけて生徒にとっては嫌な(?!)期末テストでした。
やっと今日、終わりました。生徒たちもそれぞれに一生懸命に勉強してきたみたいです。朝、校門に立って、通る生徒に、
「ちゃんと、試験勉強したかなあ。」
と聞くと、「頑張った。」という生徒の声が多くありました。
1年生の朝の「三光タイムⅠ」(学習タイム)の時間に行くと、静かに自分たちで学習を進めています。緊張感が漂っています。
年末に入り、わたし自身の仕事でも受験やいろんな仕事の詰めもしなければなりません。
昨日は、朝から、夕方まで来校される方が多くありました。また今日は、高校などとの連絡会などに参加をしました。
基本、生徒たちのためと思いながら、ていねいに対応しているつもりです。しかし、していることに生徒たちの姿がないことが多いので、ふと時間の合間に、「子どもたちのことを忘れているのではないか。」と疑心暗鬼になります。
今日もテストでしたが、テストの様子もちょっと見に行くことができていません。昼休みも「合唱のパート練習を頑張ってしていたのよ。」と生徒から言われても、聴きに行っていません。
どのような役割を持とうが、子どものすがたを見ることは、この時期少なくなりますが、できる限り、子どもたちのことを考えての自分なりの行動をしていきたいです。
昨日は、朝7時過ぎから、夜の8時近くまで来校される方で対応をしていきました。これからこんな時間も増えていくと思いますが、子どもたちと接する時間も大切にしていけるように心がけたいです。













 あと少し本番までの過ごす日の
あと少し本番までの過ごす日の