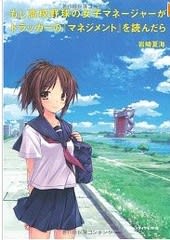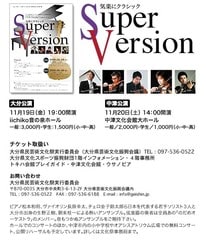今、パソコンでのインターネットの普及、携帯電話の多様な利用方法などデジタル的な生活は欠かせないものになっています。その傾向は、さらにどんどんと幅が広がっています
今、パソコンでのインターネットの普及、携帯電話の多様な利用方法などデジタル的な生活は欠かせないものになっています。その傾向は、さらにどんどんと幅が広がっています



数年前にはこれほどまでに、テレビや携帯電話などが発達するとは思いませんでした。インターネット、携帯電話、テレビのデジタル化・・・道具に人間が使われているようなそんな気がする今日この頃です。
家のテレビは、まだアナログです。テレビをつけているとき、テレビの画面の下には、
「2011年(平成23年)7月24日までに終了します。」
まだまだ先だと思っていましたが、アナログの終わりも間もなく告げます。
今、そのデジタルテレビなどの工事が行われています。
で、先日の休みに、工事の方が来て、
「今日、工事をさせてもらっていいですか。」
短時間だと聞いてOKをしました。
テレビの方は、家の外まで配線が終わりました。あとは、中の工事をすれば、アナログからデジタルへと変わっていきます。さっそく中の工事をする業者の方に依頼しました。
さらに家の方では、昔から、無線放送がありました。非常災害のとき、時報、地区の行事などを知らせていました。それも今回の工事に伴って、デジタル化になりました。その装置もつけていきました。
それが、すごいんです。(勝手にすごいと思っているのかも知れません~)なんと、それには、ラジオがついているのです。FM大分・FM福岡・FMNHK・ノースFMなどの4チャンネルをデジタル放送で聴くことができるのです。クリアーな音です。おーっ。文明開化です。
今までにラジオをつけると、じゃーという音とともに、かろうじて聴けるかなあというチャンネルもありますが、よく聴けるのは見事、ハングル語です。韓国からの放送が日本の放送局を上回っていました。
この装置は、台所に設置してもらいました。ご飯を食べながら、FMが聴ける!感動の瞬間でした。すごくゴージャスな生活になったような気がしました。まさに時代の夜明けです。