
第069回国会 参議院決算委員会 第5号
昭和四十七年九月十四日(木曜日)
午後一時一分開会
<資料>「憲法と個別的自衛権と集団的自衛権」
水口宏三参議院議員による質疑 会議録・下
※注 これは昭和47年10月14日政府提出資料「集団的自衛
権と憲法との関係」を出す前提になった国会質疑の会議録
です。前記事の安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合
憲論」トリック(1) 論拠文書の由来を知らせないと併せ
てご覧ください。
※注 水口宏三参議院議員の「質疑会議録」全文のうち、「憲法
と個別的自衛権と集団的自衛権」に関わる部分を下に転記
した。【 】は川本が付した。
※注 (答弁)国務大臣(増原恵吉君) → 防衛庁長官
説明員(久保卓也君) → 防衛庁防衛局長
説明員(吉國一郎君) → 内閣法制局長官
説明員(高島益郎君) → 外務省条約局長
○水口宏三君 一週間でこの重大なことが決定できれば非常にわれわれ好都合でございますから、次の機会に御質問させていただきます。
それでは次に、国連憲章五十一条の個別的並びに集団的自衛権のことでございますけれども、このうちの集団的自衛権というのはどういう意味合いのものか、これを法制局長官にぜひ御見解を伺っておきたいと思います。
○説明員(吉國一郎君) 御承知のように、この国連憲章第五十一条の個別的及び集団的の固有の自衛の権利と申しますことばは、第二次大戦前には、集団的自衛権という概念は、国際法上あまり明確にとらえられておりませんで、いわば戦後の、戦後と申しますか、戦時中、戦争中からの集団安全保障体制というような形を頭に入れまして、国際連合憲章で集団的ということばが、言わばつけ加えられて、従来の自衛権の観念に付加されたということが学者の通説になっております。
自衛権と申しますのは、もちろん国際法上、昔から唱えられておる一つの観念でございまして、自国なり自国民に対する急迫不正の侵害があった場合、これを防衛するという、端的に申せば、そういうことであろうと思いますが、いまでは個別的自衛の権利ということで説明されておりますが、旧来の自衛権は、まさに自国が攻められた場合、これに対応して武力を行使するということに限られておったわけでございます。その後づけ加えられた集団的という形容詞によって、含まれることになりましたいわば集団的自衛権というものは、Aという国とBという国が非常に緊密な関係がある。どの程度、緊密な関係かはいろいろ国際法上、議論があると思いますが、Bという国にとって、Aという国の存立が危うくなるということは、自分の国の存立が危うくなるにひとしいと申しますか、非常に利害関係として強い関心を持っておるという場合に、Aという国が攻められた場合に、Bという国がこれを援助して、兵力を行使するということを集団的自衛ということで説明しております。この集団的自衛という観念は、ことばとしては戦後できたものでございますけれども、一九二〇年代から集団的安全保障という観念は、ある程度地域的に認められた観念であると思います。
○水口宏三君 どうも専門家に対してこういうことを申し上げるのは失礼かもわかりませんけれども、私は、集団的自衛権と集団的安全保障体制というものとは、これは異なると思うんです。むしろ本来の集団的安全保障体制こそ国連憲章であり国連である、たまたま五十一条が特別に異物的に入れられたから論議が紛糾するのであって、むしろこの五十一条の集団的自衛権については、憲法調査会の中でも相当論議しておることは、私から申し上げるまでもないと思いますけれども、この中でも、いま長官のおっしゃったような見解もあれば、あるいは特定国が侵略を侵した場合に、むしろ懲罰的な意味でやるのだということもございますが、むしろおおかたの意見としては、むしろこれは、正当防衛の自然権のうちの一つとしてこれを認めるという立場をとっておるのが一般的だと思うんです。そうなりますと、いまのお話のように、Aという国とBという国が非常に密接な関係にある、C国からA国が攻撃をされた、その場合に3国がA国を援助するというのは、私は非常に危険だと思う。むしろA国に対する攻撃は即自国に対する攻撃である、自国の安全を脅かされることであるといって、ここでA国と一緒に軍事行動をとる。このことがむしろ集団的自衛権の基本的概念だと思うんです。それを援助するということになってくると、これはもうすでに自然権的なものではなしに、援助には当然相手方の意思もあるだろうし、取りきめもあるだろうし、あるいは地球を半回りしても援助は援助ですからね。それで実はこれがむしろ拡大解釈をされて、アメリカが地球の裏側にあるベトナムを攻撃しておるのか――これはまあ余談になりますけれども、いずれにしても、法的概念としての五十一条の集団的自衛権というのは、正当防衛権的な自然権である。したがって、Aが攻撃された場合にBが軍事行動を起こすのは、まさにB自国の安全を守るためであるというふうに解釈するのが、むしろ集団的自衛権の本来の概念ではないかと思いますけれども、その点法制局長官は、半分そのような御答弁をなされておると同時に、半分は何か旧集団共同防衛――何といいますか、条約のような御答弁をなさっておるんですが、どちらでございますか。
○説明員(吉國一郎君) 外務省から……。
○水口宏三君 いや、憲法概念としてひとつ法制局長官に念を押しておきたいと思う、安保条約を言っているわけではないですから。
○説明員(吉國一郎君) これは国際法上の概念でございますから、外務省条約局長から御説明申し上げたほうがいいと思いまして、いま条約局長を指定したわけでございますが、いまの水口委員のおっしゃるように、集団的自衛権の説明のしかたにはいろいろあると思います。先ほど私も、AとBが一定の関係にあって、A国に対して攻撃があった場合に、B国がこの攻撃に対して兵力を行使するということを申しまして――武力を行使すると申しましたが、そういうことで自国に対する攻撃と同じように、その国を防衛するということであろうと思います。
それからもう一つ、国際法上の固有の権利だということについては、まさに国連憲章に書いてございますように、固有の権利であると思います。その説明のしかたは、まあ刑事法の説明の場合の正当防衛で、これは、自己やまたは他人に対する危害を予防するため、やむを得ざるに出たる行為というようなことで説明をしておりますが、そのような観念を国際法学に取り入れまして、正当防衛権の説明をしておると思いますので、いま仰せられましたような説明でよろしいんじゃないかと思います。
○水口宏三君 それでは、五十一条の集団的自衛権ということを、これをそのとおりに再確認いたしたいと思います。
そこで、この集団的自衛権とわが国とのかかわり合いにつきましては、まず最初に出てまいりますのは、いろいろございますけれども、サンフランシスコ講和条約の中に、この集団的自衛権に触れた部分があるわけなんですね。これは私から申し上げるまでもなく、平和条約のこれは五条のC項ですね、五条のC項に「連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」と、これが一つございますね。それから日ソ共同宣言の中にも、相互にこれを持っていることを相互に確認をいたしましたね。それから私は、一番これが明確になったのは、現在の日米安保条約だと思うんです。日米安保条約の中では、私からこれも申し上げるまでもないんでございますけれども、その前文に「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」、そして「よって、次のとおり協定する。」、つまり、集団的自衛権をわが国が持っているということをお互いに確認し合って、そして安保条約をつくったんだということを明確にしておるわけですね。少なくとも国連憲章でいう集団的自衛権というものは、サンフランシスコ講和条約、日ソ共同宣言、特に日米安保条約の基礎をなしていると、こう考えてよろしゅうございますか。
○説明員(高島益郎君) ただいま先生が御指摘のとおり、集団的自衛権というのは、国連憲章で初めて各主権国に認められた権利というふうになっておりますが、この点につきまして、先ほど先生御指摘のとおり、平和条約第五条C項に、日本が初めて独立を認められたときに、主権国としてこのような権利を持つということを確認をされております。安保条約も、したがいまして、日本が主権国として、当然そのような権利を持つということを前提にしまして結ばれたということでございます。
ただ、一つだけ指摘しておきたいと思いまするのは、日本には集団的自衛権はもちろん主権国としてございまするけれども、これは憲法第九条の解釈からいたしまして、そのような権利を行使することはできない、これははっきりいたしております。したがって、この日米安保条約そのものも、第五条をごらんになればおわかりのとおり、つまり相互防衛条約ではなくて、日本が米国の力によって安全を守る、日本は米国の領土防衛をしないというたてまえになっております。この点はつまり、日本が集団的自衛権を行使できないということの実は裏側の証明になろうかと思います。
○水口宏三君 その点は、私は納得できないんです。
それじゃ防衛庁長官にお伺いしますけれども、防衛庁長官は、憲法上の問題として海外派兵はできないとおっしゃいましたね。しかし現在の憲法のどこにそういうことが書いてあるんですか。
○国務大臣(増原恵吉君) この問題はひとつ法制局長官からお答えいたしたいと思います。
○説明員(吉國一郎君) これは、憲法九条でなぜ日本が自衛権を認められているか、また、その自衛権を行使して自衛のために必要最小限度の行動をとることを許されているかということの説明として、これは前々から、私の三代前の佐藤長官時代から、佐藤、林、高辻と三代の長官時代ずうっと同じような説明をいたしておりますが、わが国の憲法第九条で、まさに国際紛争解決の手段として武力を行使することを放棄をいたしております。しかし、その規定があるということは、国家の固有の権利としての自衛権を否定したものでないということは、これは先般五月十日なり五月十八日の本院の委員会においても、水口委員もお認めいただいた概念だと思います。その自衛権があるということから、さらに進んで自衛のため必要な行動をとれるかどうかということになりますが、憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいるということを放置するというところまで憲法が命じておるものではない。第十二条からいたしましても、生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてございますので、いよいよぎりぎりの最後のところでは、この国土がじゅうりんをせられて国民が苦しむ状態を容認するものではない。したがって、この国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみにあえがなければならない。その直前の段階においては、自衛のため必要な行動はとれるんだというのが私どもの前々からの考え方でございます。その考え方から申しまして、憲法が容認するものは、その国土を守るための最小限度の行為だ。したがって、国土を守るというためには、集団的自衛の行動というふうなものは当然許しておるところではない。また、非常に緊密な関係にありましても、その他国が侵されている状態は、わが国の国民が苦しんでいるというところまではいかない。その非常に緊密な関係に、かりにある国があるといたしましても、その国の侵略が行なわれて、さらにわが国が侵されようという段階になって、侵略が発生いたしましたならば、やむを得ず自衛の行動をとるということが、憲法の容認するぎりぎりのところだという説明をいたしておるわけでございます。そういう意味で、集団的自衛の固有の権利はございましても、これは憲法上行使することは許されないということに相なると思います。
○水口宏三君 いまの法制局長官の答弁、私最初に申し上げた憲法論と政策論がどうもごっちゃになっていると思うんですね。と申しますことは、憲法では何らその点については触れていないわけですよ。憲法第九条は戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認ですね。しかしこれに対して、従来の自民党だけでなしに、前の自由党もそうですけれども、自衛権を否定しているものではない。これは私たちもそう思います。自衛権の行使の形態としての武力の行使は、これを禁止しているというのが、われわれの解釈であり、それから政府なり、これまでの政府の解釈は、いや自衛権の行使の形態としての武力の行使は認めているんだと。ところがいまの外務省の条約局長の話を聞くと、集団的自衛権の行使は認めていないとおっしゃるけれども、いまの法制局長官の御説明の中で、憲法のどこにそれがあるか全然明確になっていませんよ。自衛権そのものすら不明確なんですね。自衛権そのものすら憲法では規定をしていない。自然権として認めているというあなた方の解釈です。また、われわれもそう解釈しております。むしろ自然権である自衛権そのものの行使の形態を否定したのが九条だと、そう解釈する以外に、法制局長官のおっしゃるように、集団的自衛権は行使できないんだというようなことは憲法上どこから出てくるんですか。
○説明員(吉國一郎君) お答え申し上げる前に申し上げなきゃいけませんことは、自衛権というものは、確かに国際法上固有の権利として国連憲章第五十一条においても認めておるところでございます。自衛権というのはいわば一つの権利でございまして、その自衛権に、国連憲章で認められる前は個別的――インディビデュアルというような形容詞をつけないでザ・ライト・オブ・セルフディフェンス――自衛権ということで、いわば個別的自衛権と申しますか、最近、学者の用いますことばでは個別的自衛権というものを表現していたんだと思いますが、国連憲章になりまして、このインディビデュアルのあとにオアだったと思いますが、インディビデュアル・オア・コレクティブという形容詞がつきまして、個別的及び集団的の固有の自衛の権利というふうなことばづかいになったわけでございます。したがって――したがってと申しますか、自衛権というものはいわば一つの権利、所有権というような権利がございまして、その自衛権の発動の形態としてインディビデュアルに発動する場合とコレクティブに発動する場合とあるという観念じゃないかと思います。憲法第九条の説明のしかたとして自衛権、自衛権と言っておりましたのは、いわば狭い意味のインディビルデュアル・セルフディフェンス・ライトというようなものを頭に置いて説明をしてきたわけでございまして、広い意味の自衛権という形になりましても、自衛権というものは一つで、その発動の形態がインディビデュアルかコレクティブだという説明をいたしますと、先ほど申し上げましたように、日本の憲法第九条では、先ほどおっしゃいましたように、国際紛争解決の手段としては武力の行使を放棄しております、自衛権があるかどうかということも問題だと仰せられましたが、その件につきましては、少なくとも最高裁の砂川判決において自衛権が承認をされております。その自衛権を持っているというところまでは最高裁の判決において支持をされておりますが、これから先が政府の見解と水口委員やなんかの仰せられますような考え方との分かれ道になると思います。
先ほど私が申し上げましたのは、憲法前文なり、憲法第十二条の規定から考えまして、日本は自衛のため必要な最小限度の措置をとることは許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には国土を守るため、国土、国民を防衛するために必要な措置をとることまでは認められるのだという説明のしかたをしております。その意味で、いわばインディビデュアル・セルフディフェンスの作用しか認められてないという説明のしかたでございます。
仰せのとおり、憲法第九条に自衛権があるとも、あるいは集団的自衛権がないとも書いてございませんけれども、憲法第九条のよって来たるゆえんのところを考えまして、そういう説明をいたしますと、おのずからこの論理の帰結として、いわゆる集団的自衛の権利は行使できないということになるというのが私どもの考え方でございます。
○水口宏三君 いまの長官のお答え、何かちょっと……、十二条、十三条とおっしゃいますが、十二条、十三条というのは関係ないんじゃないですか。――それはまあいいです。憲法をごらんになっていただくと十二条は自由及び権利の保持、濫用禁止、利用責任の問題である。十三条は個人の尊重の問題ですね。別に九条とは直接関係がないと思います。
それはさておきまして、私はいままで、だからそういうことがあろうかと思ってずっと詰めてまいったのであって、まず第一に海外派兵の問題から入り、海外派兵はできないんだということは、これはまあ早急に具体的な態様を御検討願う、五十一条の集団的自衛権というものがまさに正当防衛の自然権であるということについて、これは法制局長官はお認めになったわけですね。正当防衛のこれは特殊な、つまり自衛権というものを個別的自衛権と集団的自衛権に分けたのは行使の形態を分けたにすぎないのであって、本質は自衛権というものにあると思うんです。それは当然自然権として持っているものである、だからこそサンフランシスコ条約にも日ソ共同宣言にも、また日米安保条約の基本としてこれは据えられておるわけですね。
その行使しないというのは、これは憲法論ではなくて政策論なんです。憲法にそんなことは全然書いてない。それはむしろ前文の思想をもし強調なさるならば、これはまさに、第九条というものは自衛権の行使の形態としての武力の行使を禁止したと見るのが常識ですよ。憲法前文に引っかけて、個別的自衛権は武力でもって行使できるが、集団的自衛権は武力で行使できない、自然権を制約するような、そういう規定がどこにあるのですか、前文に……。まして十二条、十三条は全然関係ないです。
○説明員(吉國一郎君) 先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第一段に、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」ということで、この憲法を制定いたしまして、さらに憲法第九条の規定を設けたわけでございます。その平和主義の精神というものが憲法の第一原理だということは、これはもうあらゆる学者のみんな一致して主張することでございます。
そして「日本国民は、恒久の平和を念願し、」のあとのほうに、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」ということで、平和主義をうたっておりますけれども、平和主義をうたいまして、武力による侵略のおそれのないような平和社会、平和的な国際社会ということを念願しておりますけれども、現実の姿においては、残念ながら全くの平和が実現しているということは言えないわけでございます。
で、その場合に、外国による侵略に対して、日本は全く国を守る権利を憲法が放棄したものであるかどうかということが問題になると思います。そこで国を守る権利と申しますか、自衛権は、砂川事件に関する最高裁判決でも、自衛権のあることについては承認をされた。さらに進んで憲法は――十三条を引用いたしましたのは、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」ということで、個人の生命、自由及び幸福追求の権利を非常に重大な価値のあるものとして、第十三条は保障しようとしているわけでございます。
そういうことから申しますと、外国の侵略に対して平和的手段、と申せば外交の手段によると思いますが、外交の手段で外国の侵略を防ぐということについて万全の努力をいたすべきことは当然でございます。しかし、それによっても外国の侵略が防げないこともあるかもしれない。これは現実の国際社会の姿ではないかということになるかと思いますが、その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底でございます。
その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が――日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。
○水口宏三君 それは後半は政策論ではないですか。憲法上ですね、そういうことを明確に規定している条文はどこかということを私は伺っているのです。むしろこれには二つの根拠があって、国連憲章五十一条から出てくる自然権、正当防衛の自然権としての集団的自衛権という概念と、それから日本国憲法第九条から出てくる、あなた方のおっしゃる自衛権という概念と、その概念があいまいだから、常に政策論でもってそこをつながなければならなくなるわけですね。
たとえば先ほどのお話の、明らかに日本に向かって艦隊が攻めてくる場合には当然これを迎撃する。だからこれはもう集団的自衛権というものとまさに密接な関係――その国が侵されることは日本の安全が脅かされるという、つまり日本の安全が脅かされるというのは、まさに日本国民の生命、財産が脅かされるということですよ。そうでしょう、長官、日本の安全が脅かされるということは。そういう場合にのみ正当防衛権的な自然権として集団的自衛権を認めているのであって、それを何か個別的自衛権と集団的自衛権とは全く別な概念であって、それを何か政策的につないで十三条を間に入れるなんというのはこっけいですよ、それは。法律論じゃないですよ、それは。明確にしてください、そこのところ。
○説明員(吉國一郎君) 政策論として申し上げているわけではなくて、第九条の解釈として自衛のため必要な措置をとり得るという説明のしかた――先ほど何回も申し上げましたが、その論理では、わが国の国土が侵されて、その結果国民の生命、自由及び幸福追求に関する権利が侵されるということがないようにする、そのないようにするというのは非常に手前の段階で、昔の自衛権なり生命線なんていう説明は、そういう説明でございましたけれども、いまの憲法で考えられておりますような自衛というのは最小限度の問題でございまして、いよいよ日本が侵されるという段階になって初めて自衛のための自衛権が発動できるという、自衛のための措置がとり得るということでございますので、かりにわが国と緊密な関係にある国があったとして、その国が侵略をされたとしても、まだわが国に対する侵略は生じていない、わが国に対する侵略が発生して初めて自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的自衛のための行動はとれないと、これは私ども政治論として申し上げているわけでなくて、憲法第九条の法律的な憲法的な解釈として考えておるわけでございます。
○水口宏三君 納得できませんね。わが国と密接な関係にあるということは、たとえばアメリカと非常に密接な関係がありますね。じゃアメリカがどこかの国から攻撃されたからといって、直ちにわが国の安全は脅かされません。そうでしょう。だから最初に、私はむしろ集団的自衛権というのは正当防衛権的な自然権であるということを長官お認めになっているわけですよ。だから密接であるということは、単なる政治的な密接さとか、あるいは経済的な密接さではなしに、まさにその国が脅かされるということが、わが国の安全、すなわちわが国民の生命、財産を脅かされるということであって、そのときに初めて集団的自衛権というものが発動できるからこそ、正当防衛権的な自然権ということが言えるんじゃないですか。そこを何かあいまいに密接な密接なとおっしゃるけれども、わが国の国民の生命、財産が脅かされるまではと言うけれども、一方、久保防衛局長に聞けば、明らかにわが国を攻撃するという艦隊に対しては、その艦隊に向かって攻撃することは当然の防衛行動であると、こういうお話があるから、どうしてそこが結びつくのですか。だから法制局長官は密接なということばでごまかしている。密接なというのは政治的に密接である、経済的に密接であるという意味じゃないですよ。まさにわが国民の生命、財産に影響を与えるか与えないかということは、これは正当防衛権的な自然権として成立するかしないかのけじめじゃないですか。
○説明員(吉國一郎君) 私が密接と申し上げました、密接ということばを使って申し上げたつもりでございますのは、たとえわが国と非常に密接な関係がある国があったとしても、その国に対する攻撃があったからといって、日本の自衛権を発動することはできないという意味で、密接のことばを使ったわけでございまして、いま水口委員の仰せられますように、わが国と安全保障上と申しますか、国家の防衛上緊密な関係にあるその国が攻められることは、日本の国が攻められると同じだというような意味の考え方はしておりません。
○水口宏三君 そうすると、集団的自衛権というのは拡大されるわけですか。私はむしろ、先ほど申し上げた憲法調査会の論議を見ても、正当防衛の自然権として、これを一応国際的にも、また憲法調査会の中での論議でもそれを大体認めているわけですね。正当防衛の自然権というものは集団的自衛権に該当し得るということは、これは明らかにわが国民の生命、財産、こういうものが脅かされるという前提でなければ、これは私は発動できないだろうと思うのです。ただ密接さということばにはいろいろな密接さがあると思う。そうでなくて、この場合は、まさにAという国が攻撃されることがわが国の国民の生命、財産を脅かされるというところにあるのじゃないですか。それを、あなたさらに拡大して、そういう意味で言ったのじゃないのだというふうになってきたら、どことでも軍事同盟を結んで戦争できるじゃないですか。
○説明員(吉國一郎君) 国際法上の観念としての集団的自衛権、集団的自衛のための行動というようなものの説明として、A国とB国との関係が一定の緊密な関係にあって、そのA国とB国が共同防衛のための取りきめをして、そうしてA国なりB国なりが攻められた場合に、今度は逆にB国なりA国なりが自国が攻撃されたと同様として武力を行使する、その侵略に対して。そういう説明は、国際法上の問題としてはいま水口委員の仰せられましたとおりだろうと思います。ただ日本は、わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういうことだろうと思います。憲法九条は戦争放棄の規定ではございますけれども、その規定から言って、先ほど来何回も同じような答弁を繰り返して恐縮でございますけれども、わが国が侵略をされてわが国民の生命、自由及び幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置をとるというのは、憲法九条でかろうじて認められる自衛のための行動だということでございまして、他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、それに対して、その他国が侵略されたのに対して、その侵略を排除するための措置をとるというところは、憲法第九条では容認してはおらないという考え方でございます。
○水口宏三君 どうも法制局長官の御答弁はときどき変わるのですけれども、他国の防衛なんかと私いつ言いました。他国の防衛なんということは、これはもう集団的自衛権に絶対入らないのです、初めから。何回も私申し上げているでしょう。これは憲法調査会でも言っているように、自国にとっての正当防衛の自然権なのです。どういう場合が成立するのですか、自国の国民の生命、財産が脅かされる場合に、これに対して行動起こす、これがまさに正当防衛の自然権じゃないですか、それを他国の防衛のために集団的自衛権を発動するのはおかしい。これは初めから集団的自衛権から逸脱しているのです。私が申し上げているのは、そういう状況において集団的自衛権が発動できないという憲法上の規定がないではないか。あなた方は第九条の解釈、ことに前文についてさっきあなたるるおっしゃいましたけれども、前文は宣言的なものであって、残念ながらこのとおりいっていない、このとおりいっていないから第九条で自衛権の発動もやむを得ないのだ、そういうことをおっしゃっている。自衛権の発動、武力行使の形態もやむを得ないのだということをおっしゃっている。しかも集団的自衛権というのはまさにそれに該当するではないか。何も初めから二つ自衛権があるのではない、自衛権というのは一つです。しかもそれはあくまで自国の国民の生命、財産が脅かされた場合、これを守るための自然権である。これを私はむしろ憲法上の、あるいは国連憲章上の基本的解釈だということは、だからこそ前に念を押した上でこの論議を進めているのです。ときどきお変えになる。わが国は他国の防衛のために出ていかない――そんなことはあたりまえのことですよ、一言もそんなことは言っていない。いかがですか。
○説明員(吉國一郎君) 先ほどの、他国を防衛するということばづかいはけしからぬというお話ですが、集団的自衛権と申しますのは、さっき申しましたように、A国とB国がいわば防衛上の関係として緊密な関係にあって、相互に防衛をするということを取りきめをするという関係にあった場合、A国に対する侵略があった場合にB国がそのA国に対する侵略は自国に対する攻撃と同視して、その侵略に対して武力を行使するということでございますので、まあ簡単に比喩的に、他国を防衛するということばを申したわけでありまして、刑事法上の正当防衛の観念を、正当防衛権申しますか、正当防衛の観念を国際法学上取り入れて、国際法上固有の権利として自衛の権利を説明するのに用いたという説明を、先ほど私申し上げました。その観念を変えたつもりは全くございません。
○水口宏三君 それは法制局長官、非常に大きなミスを犯していらっしゃるのじゃないですか。大体、集団的自衛権の場合に、あらかじめA国とB国が取りきめを行なう、このことはむしろ一般的には五十一条の集団的自衛権の拡大解釈であるといわれているのですね。これは五十一条は、私が言うまでもなく、急迫不正の侵略が行なわれた場合ですね、その場合に自然権として発動されるものであって、前提として取りきめがあるかないかなんということは、全然関係ないですよ。それを拡張して現在不必要に取りきめを行なっているところに問題があるのじゃないですか。どこに取りきめなんという規定がありますか、五十一条に。だからこそ自然権といわれているのじゃないですか。
○説明員(吉國一郎君) 私が取りきめと申しましたのは、取りきめが絶対なければいけないということではもちろんないと思います。ただ、その取りきめも何もなしに、そのA国とB国がそういう関係にあった場合に、A国が侵略されたというのでB国が当然にそれを助けるというものではなくて、その場合には事前の段階でA国の要請なり、あるいはA国の承認が要るのだろうと思います。そういうものを、一般的には取りきめという形で事前に合法化するといいますか、合理化するということを一般普通の場合にはこうだということで申し上げたつもりです。
もう一つは、取りきめさえあればいいということではございませんで、A国とB国とが防衛上緊密な関係になければならぬ――先ほどおあげになりました、非常に地球の反対側にあるような遠隔の地との間にも、取りきめさえあればいいというようなことになっては困るというようなお話がございましたけれども、そういうものが容認されるということは私は考えておりません。
○水口宏三君 それでもなおかつこの五十一条の解釈として、取りきめがあるときはもちろん論外です。明示の要請があった場合に限るかどうかということすら、これはいままで確定しておりませんね。むしろこれは自然権である以上、明示の要請を必要としないという解釈のほうが一般解釈だと思うのです。これはなぜかといえば、A国にとってはB国に対する攻撃が自国の国民の生命、財産を脅かすものとみた場合に、これはA国が出ていくということは、まさに自衛権の発動だから、B国からの明示の要請がなくてもいいのだという解釈のほうが、むしろ私は一般的自然権としての解釈だと思います。それをあなたは、明示の要請がなければいかぬとおっしゃるけれども、それはそういう解釈にお立ちになっているのですか。
○説明員(吉國一郎君) これは国際法の問題で、私それほど専攻したわけではございませんので、あるいは条約局長から補足してもらったほうがいいかと思いますが、大体の大かたの学説では、そういうことであったと、私いまの記憶では考えております。
それから、ついでと申しては恐縮でございますけれども、たとえばケルゼンのような学者は、コレクティブ・セルフディフェンス・ライトというものについて、自衛権の観念に入れることは、もともと無理だというような説明をしている学者さえあることをつけ加えておきます。
○水口宏三君 いまいいことをおっしゃった。そこで私は、まさに集団的自衛権が乱用されているところに問題がある。大体、集団的自衛権という観念が、本来の国連憲章のサンフランシスコの原案にはございませんですからね。これはダンバートン・オークス会議ですか、あそこで初めてアメリカ側から入れられ、五十三条の旧敵国の文言がソ連側から入れられたというのは、私が申し上げるまでもないことだと思います。そういう意味で、集団的自衛権というものは、初めから非常にあいまいなものであるが、少なくとも法的解釈としては、正当防衛に関する自然権であるというのがいま確立をしている。それを前提にして、日米安保条約が締結されているにもかかわらず、あえて日本は集団的自衛権を行使しないというのは、これはまさに政策論じゃないですか。法律論じゃないですよ。この点、条約局長いかがですか。
○説明員(吉國一郎君) 私の、これはお答えと申し上げるより釈明みたいなものでございますが、平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。その自衛権には、形容詞がついておりまして、個別的及び集団的自衛の固有の権利があるということで、条約上うたわれておりますが、これは国際法上の問題として、日本が自衛権を持っている、その自衛権というのは個別的及び集団的なものであるということを国際法上うたったわけでございまして、憲法上こういう権利の行使については、また別途措置をしなければならない。憲法ではわが国はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論として、その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているつもりでございます。
○水口宏三君 それじゃ、まあこの問題はまだ何回か機会がありますから、これ以上論争してもしかたがないと思います。ただ、私が申し上げたいのは、集団的自衛権に対する解釈について法制局長官がしばしばこれをお変えになってきている。さっき申し上げた正当防衛の自然権であるという立場に立って、この場合の解釈は、まさに日本国民の生命、財産が脅かされるような状況というものは、これが正当防衛のための自然権であるとすれば、どこかの国がある艦隊を率いて日本を攻撃する場合と、当然Bという国を通って日本を攻撃する場合とあるでしょう。そういう場合、Bが攻撃されることは即わが国の国民の生命、財産を脅かされると思って、これに対して防衛するのだ、これが集団的自衛権だというふうに解釈するのなら、これは私はどうも妥当なような気がいたしますが、これ以上論争いたしません。
ただし、ここで、もしいま法制局長官がおっしゃるように、憲法上集団的自衛権というものの行使が禁止されているという解釈にお立ちになるなら、何で日米安保条約の前文に、権利を有することを確認し、次のとおり協定するというような条項が入ってくるのですか。これは明らかに放棄しているものなら、日本が集団的自衛権を持っていないということを前文に明記すべきではないですか。
○説明員(高島益郎君) これはサンフランシスコ平和条約をはじめ、ほかの文書にもございますけれども、日本が主権国としてこういう権利を持っているということを確認しただけのことでございまして、安保条約そのものの中では、そのような意味での集団的自衛権は日本は行使できないということを前提に全体が起草されております。と申しますのは、先ほどもちょっと申しましたけれども、日米安保条約というものは、いわゆる安保条約の中では非常に特殊な条約でございまして、相互防衛条約になっておらない。それはまさに日本に集団的自衛権を行使することができない憲法上の制約があるからそうなっているということでございます。前文は、何回も申しますけれども、他の平和条約その他の文書と同じように、日本が主権国家として当然持っていることをここに確認したということだけの意味でございます。
○水口宏三君 それは条約局長、サンフランシスコ条約をお読みになってごらんなさい。これは日本がみずからの意思でもってやったのじゃないのですよ。つまり講和する相手国が日本にそういうものを認めるという、許容するということにすぎない。日本から何ら積極的にそれについて意思表示をしていないのです。日ソ共同宣言の場合もソ連は日本に、日本はソ連に認めているのですね。ところが安保条約だけは、相互に持っていることを、両国が固有に持っている、これを確認しているんですね。相互に両国が持っていることを確認しているんですよ。だから、サンフランシスコ条約、日ソ共同宣言から見ると、これは明らかに日本が集団的自衛権を持っている、しかもその行使について何ら前文には制限をうたっていないんですね。とすれば、これはまあ当然いままでの自然権としての集団的自衛権の行使というものを安保条約では禁止しているんだということには全然ならないと思います。結局、いままでの条約をずっと羅列してきて安保条約へきて、ついにこれはもう、相互にお互いが持っていることを確認し合ったんですね。それでどうして日本だけが集団的自衛権を放棄するなんということが出てくるんですか。
○説明員(高島益郎君) それは、先ほどから吉國長官が御答弁しておられますとおり、憲法の自己抑制というのがございまして、日本には集団的自衛権はあるけれどもこれを行使できない、そういうたてまえで安保条約ができておるということを申しておるわけでございます。
○水口宏三君 それでは、私もう一回。あとで統一見解を伺いたいんでございますけれども、どうもいままでの御答弁を伺っていると、少なくとも国連憲章五十一条の集団的自衛権に対する一般的な概念、日本国憲法第九条に対する解釈、これを法制局長官は十三条までお加えになった、あるいは憲法の前文まで引用なさった、それらを含めて、何で憲法第九条というものが集団的自衛権の行使を――を自己抑制とおっしゃっているが、禁止でしょう、禁止していると見ていいんでしょう――禁止しているのか、その点をもう少し文書で明確にしていただきたい。いままでの論議では納得できないんです。いま申し上げたような五十一条における集団的自衛権というものの概念、それから憲法前文、九条、十三条、それから日米安保条約、これらを含めて、日本が集団的自衛権の行使を憲法上禁止されているということをもう少し国民にわかりやすく言っていただきたいんですね。おそらくきょうの論議を聞いて国民は何が何だかわからないわけです、このままでは。自己抑制だなんて――自己抑制というのは、私非常に主観的なものであって、だから当然憲法論議である以上、それは解釈の相違もございましょうが、これは単なる解釈の問題ではないと思うんですね。その点明確にひとつ文書でもって御回答いただきたいんでございますけれども、増原防衛庁長官いかがでしょうか。
○国務大臣(増原恵吉君) なお、御趣旨をよく承りましたので、検討いたしましてお答えをいたします。この際申して恐縮ですが、先ほど海外派兵の統一解釈と申しますか、一週間ぐらいと申しましたが、いまもお話を聞いておって、これは両者まことに一体のものでございまして、約一カ月ぐらいの御猶予をいただきたいということで、解釈を申し上げる……。文書をもってやることはよろしゅうございます。文書でお答えをさせることにいたします。
○水口宏三君 そうすれば、これを伺うのはちょっとあまり意味がなくなるのでございますけれども、日米共同声明の例の韓国条項と台湾条項でございますね、これはまさに日本の自衛とは全く無関係である、自衛権の行使とは無関係であると解釈してよろしいんでございますか。増原防衛庁長官。
○説明員(高島益郎君) 先ほどから申しておりますとおり、日本は集団的自衛権を行使することができないというたてまえでございますので、韓国であろうとどこであろうと、外国との関係におきまして、日本の持ついわゆる個別的な自衛権との関係では何ら関係はございません。
○水口宏三君 いやいや、個別的な自衛権とは関係がないかもわかりませんけれども、私が申し上げるのは、少なくとも日米共同声明の中では、韓国の安全は日本の安全と非常に緊密な関係にあるということが書いてありますね。韓国に――日本を攻撃する意図を明らかに持ったと思われるどこかの国の軍隊が、韓国を軍事攻撃し、韓国を占領する。それは日本にとっての非常な脅威でございますね。そういう場合であっても、集団的自衛権の行使は行なわない、そう解釈してよろしいんですか。
○説明員(高島益郎君) 確かに先生の御指摘のような事態は、非常に日本にとっても脅威であろうかと思います。しかし、これに対処する日本の行為としましては、集団的自衛権は行使できないということは、確固たる立場でございます。
○水口宏三君 それでは、一応海外派兵の問題につきましてはその程度にいたしたいと思います。











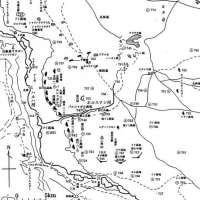



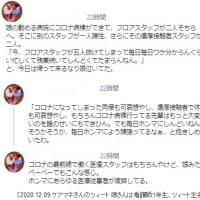





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます