
ミッジ・ユーロが率いていた(第2期)ウルトラヴォックスが、ニューウェイヴの流れの変化と共に下降線に入ったラインで発表された作品「ラメント」。
1984年作品。
そこには、コニー・プランクとベルリンの壁際で創られた圧倒的作品「エデンの嵐」のヴォルテージは無い。
「エデンの嵐」からたかだか3年程度の後のことなのに。
主観的思い入れとしての「エデンの嵐」が、生涯の100枚に入る作品、という感情が、そこには大いに作用していた。
時代は、インダストリアルと、もう一方では、アコースティックなナマ音へと向かっていた。

当時クロスオーバーイレブンでも掛かった「マン・オブ・トゥー・ワールド」「ハート・オブ・ザ・カントリー」は、それまでの音像には無い方向のたそがれの感覚。
それは、瞬時落胆だったが、その後聴き込めば、新しい彼らの音であり、この2曲は愛していた/いる。
■Ultravox 「Man Of Two Worlds」1984■
他には、シングルカット曲も含めて如何にもウルトラヴォックスらしい曲が収録されていたが、この作品に至るまでに、既に創られた音の撫で返しであって、自分には響かなかった。
当時、メロディメーカーとして稀有な才能を持ったミッジ・ユーロならば、その程度のことはお茶の子さいさい。。。と、高い期待・要求を抱き過ぎていたのだろう。
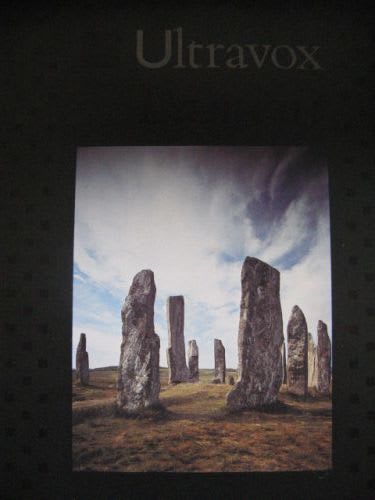
ロッキンオンのアルバムレビューで、「ラメント」が担当盤となった渋谷陽一さんは、こんな風なことを言っていた。
本当は、彼らは新しい音楽を発明したバンドなのに、音楽には特許というものが無いので、フォロワーを含めて、後から来た新しい音楽家によって淘汰されてしまう。
それは、テクノ/ニューウェイヴのミュージシャンの宿命とも言えるのだが、割りに合わない商売領域だな、と。
確かに、ある程度骨格のベースがある分野では、そういうことは起きないのだが、ゲイリー・ニューマン始め、多くの音楽家に当てはまる事実だった。
しかし、だからと言って、「より新しく・より遠くへ」と向けて鍛錬していた・意志を持つ音楽家をけがされたような気分になってしまい、渋谷さんの発言に不快感をあらわにした記憶がある。
それを言っちゃあおしめえよ、と思った。
と同時に、「ロック」という用語が化石化した80年代には、アウェイな戦いだった中で、「ロッキンオン」をビジネスの軌道に乗せねば、という編集長の顔が覗ける発言でもあった。
■Ultravox 「Heart Of The Country」1984■


























