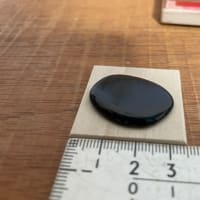元々、安定志向が無いのかもしれない。
大学も、物理学から、中国史に、
ある時本屋で読んだ、石田幹之助先生のお書きになった「長安の春」を読んで、
忽ち、習うならこの方、と、勝手に決め込んで、国学院に、編入してしまいました。
たぶん、家の仕事柄か,漢文に慣れていたというのもあるかもしれません。
高校ぐらいから、暇があると戦国策や淮南子等読みふけり、
友達と遊ぶというより、諸葛孔明や曹操等に親しみを感じ、張遼が大の仲良しみたいな生活送っていましたから、
中国と言うのにかなり親しみを持っていたのでしょう。
またそのころ、NHKラジオで、小泉文夫さんの、世界の民族音楽など、
毎週土曜の夜が楽しみで、お金がたまると、タブラや、シタール等、
当時としてはとても手に入りにくい楽器を、なんとかルート探って、買い集めたり、
時間があれば、チェロ弾いたり、フルート吹いたり、
今思えば、この二胡作りの下地を作っていたのかもしれないと、
最近思うようになってきています。
幸いにも、周りが職人だらけの世界で生きてきましたから、
物を作りだすということは自分の中で、食事をするのと同じレベルで、
考えもせず、手が動きます。
他のことには、かなり飽きっぽいのに、作ることだけは、やめられません。
食事や睡眠と同じことなのでしょう。
さて、みんなは大学卒業し、いざ就職ということになった時、
自分は何をしたいのか、それこ中学生のような疑問が浮かびました。
多分、ホントにそれまでは、働いて生きていくという事が解っていなかったようです。
自分が何をしたいのかが解らないという、不安、
もしかしたらみなさんも、覚えがあるのかもしれません。
ともかくも、食わなければ、と、大学時代からやっていた大道具の会社に、そのまま籍を置き、
やり始めたのは、考えるということでした。
ある人に、おまえは考えているのか?と叱咤された時、
多分その方は、自分の生きていくまともな生活を、という意味だったと思うのですが、
何を間違えたのか、考えるというのはどういうことなのか、考え始めてしまったのです。
それから、考えることが解る本、いわゆる、哲学と言う物が書いてある本、
片端から読み始めました。
それこそ、「ソフィーの世界」みたいなことを自分で始めて見たのです。
こんなこと二胡作るのに何の関係も無いようですが、
おおありなのです。
物を作りだすために必要な考え方、ということがあります。
それは漠然とした、人生の、というようなことではありません。
物を作りだすというのは、関連するあらゆる事を、如何に深く知って、
如何にそれらを関連付けて、思い描いたイメージの中に組み込み、
具体的な形にまで持っていくかという、考え方の作業でもあるのです。
二胡、楽器、木、皮、音、響き、振動、波長、波、粒子、光、素粒子、クオーク、超弦、
時間、
耳、手、脳、感性、心、精神、神経、心理、人、人々、民族、国、歴史、環境、自然
そして地球、太陽系、銀河、銀河宇宙、
これら、全て二胡作るのに必要だと思いませんか?
その考えることを始めようとした時出会った言葉が、
「考え方を考えてみる」ということでした。
人はどうやって考えているのかということに、先ずぶつかってしまったのです。
続く
西野和宏
大学も、物理学から、中国史に、
ある時本屋で読んだ、石田幹之助先生のお書きになった「長安の春」を読んで、
忽ち、習うならこの方、と、勝手に決め込んで、国学院に、編入してしまいました。
たぶん、家の仕事柄か,漢文に慣れていたというのもあるかもしれません。
高校ぐらいから、暇があると戦国策や淮南子等読みふけり、
友達と遊ぶというより、諸葛孔明や曹操等に親しみを感じ、張遼が大の仲良しみたいな生活送っていましたから、
中国と言うのにかなり親しみを持っていたのでしょう。
またそのころ、NHKラジオで、小泉文夫さんの、世界の民族音楽など、
毎週土曜の夜が楽しみで、お金がたまると、タブラや、シタール等、
当時としてはとても手に入りにくい楽器を、なんとかルート探って、買い集めたり、
時間があれば、チェロ弾いたり、フルート吹いたり、
今思えば、この二胡作りの下地を作っていたのかもしれないと、
最近思うようになってきています。
幸いにも、周りが職人だらけの世界で生きてきましたから、
物を作りだすということは自分の中で、食事をするのと同じレベルで、
考えもせず、手が動きます。
他のことには、かなり飽きっぽいのに、作ることだけは、やめられません。
食事や睡眠と同じことなのでしょう。
さて、みんなは大学卒業し、いざ就職ということになった時、
自分は何をしたいのか、それこ中学生のような疑問が浮かびました。
多分、ホントにそれまでは、働いて生きていくという事が解っていなかったようです。
自分が何をしたいのかが解らないという、不安、
もしかしたらみなさんも、覚えがあるのかもしれません。
ともかくも、食わなければ、と、大学時代からやっていた大道具の会社に、そのまま籍を置き、
やり始めたのは、考えるということでした。
ある人に、おまえは考えているのか?と叱咤された時、
多分その方は、自分の生きていくまともな生活を、という意味だったと思うのですが、
何を間違えたのか、考えるというのはどういうことなのか、考え始めてしまったのです。
それから、考えることが解る本、いわゆる、哲学と言う物が書いてある本、
片端から読み始めました。
それこそ、「ソフィーの世界」みたいなことを自分で始めて見たのです。
こんなこと二胡作るのに何の関係も無いようですが、
おおありなのです。
物を作りだすために必要な考え方、ということがあります。
それは漠然とした、人生の、というようなことではありません。
物を作りだすというのは、関連するあらゆる事を、如何に深く知って、
如何にそれらを関連付けて、思い描いたイメージの中に組み込み、
具体的な形にまで持っていくかという、考え方の作業でもあるのです。
二胡、楽器、木、皮、音、響き、振動、波長、波、粒子、光、素粒子、クオーク、超弦、
時間、
耳、手、脳、感性、心、精神、神経、心理、人、人々、民族、国、歴史、環境、自然
そして地球、太陽系、銀河、銀河宇宙、
これら、全て二胡作るのに必要だと思いませんか?
その考えることを始めようとした時出会った言葉が、
「考え方を考えてみる」ということでした。
人はどうやって考えているのかということに、先ずぶつかってしまったのです。
続く
西野和宏