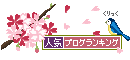久し振りに箕輪城址を歩いて参りました。昨年の秋以来ですので久し振りです。元教育長さんと学芸員のOさんはお元気でボランティア活動を行っているかな?

搦手口から二の丸へ向かう道(道の写真左側は馬出が在った所)

今日は二股を左折し右に大堀切を見ながら西虎口へ向かいます。


平成28年完成の郭馬出(かくうまだし)西虎口に建つ門も時の経過と共に幾分、サマになって来ました。此処は南側に出撃する拠点の役割があったそうです。屋根から落ちる雨水を受ける為の排水用の溝も極めて良好に残っていた様です。


東屋の立つ二の丸跡地。桜は未だ満開に至らず8分咲きといったところでした。直ぐ上の写真、ハクモクレンは樹齢430年、箕輪城の歴史をずっと見続けてきた老樹です。昨年は先ず先ずの花を持っていた記憶が有りますが今年は疎らに咲いているだけでした。
今日はO氏一人でしたので先生はどうされたのか尋ねますと体が余り丈夫でないため息子さんに冬の寒い期間は外出を止められていると言う事でした。「木橋が完成しましたから行ってみますか?」と言うので今日は案内をお願いする事に。

御前曲輪跡地、満開にはあと数日掛かりそうです

O氏が石を投げ入れ井戸の深さを計測、20mある様です。この井戸の底から長野氏累代の墓石が多数見つかった事は私も学習済みです。


本丸跡地にはセイヨウタンポポは一つも見られず日本タンポポのみが無数に咲いています。以前お聞きした事ですが西洋タンポポは先生が日本タンポポに拘り根を掘り出し絶やしているとの事でした。因みに違いですが日本タンポポは写真の様に総苞片が上を向いておりますが西洋タンポポは総苞片が反り返っているのが唯一の見分け方です。



この木橋は本丸(左)と蔵屋敷(右)を繋いでおりますが発掘調査で16世紀に使われていた木橋の橋脚の礎石が当時のままの位置で2石確認されましたので形は移城先の高崎城(和田城)の絵図を参考に着手されたとの事です。この橋を渡り米などを運んだのでしょうね。


O氏は城内の植物にも詳しく、6月になるとこの一角に香りの強い三つ葉の原種、こちらにはシラトリ・・が咲きますよ。こちらはお茶の木の群生で霜から守る様に杉が植えられている所をみますと戦後に植林されたものでしょうねと仰っておりました。今日は解説付きでの箕輪城址探訪でしたが知識が如何に薄かった事か。改めて実りの有る探訪となりました。