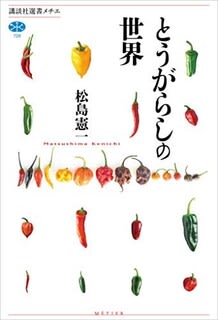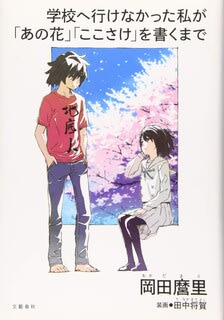松島憲一 「とうがらしの世界」読了
1冊まるごとトウガラシの本だ。著者は唐辛子を専門に研究している研究者だそうだ。
構成は唐辛子の生態とトウガラシの食文化となっている。(種としてのとうがらしは漢字で、食材としてのとうがらしはカタカナで分けられている)
まず、生態について、
世界で栽培されている唐辛子は大きく五つの品種に分かれている。
以下の5種類だ。
アニューム種・・世界中で栽培されていて、日本のトウガラシもこの種類 タカノツメ、ししとう、ピーマンもこの種類
フルテッセン種・・タバスコ、トムヤムクンに使うプリック・キーヌーが代表で中米と東南アジアでよく栽培されている。
キネンセ種・・ハバネロ、ブートジョロキアなど、超激辛の品種。ハバネロは2006年までギネスブックで世界一辛いトウガラシであったが、SBカプマックス(SB食品が開発したそうだ。)にとってかわられ、それも3ヶ月でブートジョロキアに奪われた。その後も、トリニダード・スコーピオン・ブッチ・T カロライナ・リーパー(カロライナの死神)などという激辛唐辛子この品種のなかで生まれているそうだ。
バッカートゥム種・・ほぼ中南米域でしか栽培されていないのであまりなじみがない。
プッペセンス種・・アンデスの高地のみで栽培されている。
人間がトウガラシを食べるようになったのは約6000年前と言われている。原産地域は中南米で、それがヨーロッパ、アジアにもたらされたのはコロンブスが新大陸を発見してからだ。タバコとともにもたらされた。それが東に向かって伝搬してゆくのだが、日本には、一説によると1542年には入っていた可能性がある。遅くとも1680年には日本に入っていた。ポルトガルから、もしくは朝鮮半島から伝来したと考えられる。
その後100年ほどで一般的な食材となった。「和漢三才図絵」には約80種類掲載されているほど品種改良もされた。
注目の辛味成分についてであるが、カプサシノイドと言われる20種類ある成分が辛味の素である。その中の、カプサイシン、ジヒロカプサイシン、ノルジヒロカプサイシンが主なもので他の成分は検査機器では検出できないほど微量ということだ。
ダイエット効果もあるそうで、脂肪の蓄積を抑え、抑える前に消費させる能力があるらしいが食欲も増進してしまうのでそれほどの効果は期待できない。
ちなみに、ピーマンとパプリカはカプサイシンを作れない。それはカプサシノイドの化学合成過程にある。果実の中で別々に合成されたフェノール類とベンゼン環が結合してカプサシノイドができるのだが、ピーマンやパプリカはそれを結合することができない。
シシトウでたまに辛いものに当たるのは、偶然それが結合されてしまった結果ということだ。そのシシトウであるが、シシトウは種が少ない実はとても辛いらしい。ストレスと単為結果によって種ができずに実がなってしまうとカプサイシンができてしまう。種が少ないとリグニンという種の表皮を硬くする成分を作り出すフェノール類の行き場がなくなり辛くなるらしい。
シシトウは実の先端の形が丸くて獅子の頭の形に似ているというので、獅子頭という文字から名前がついた。今のシシトウは和歌山が発祥で、京都の田中とうがらしという種が病気で廃れる前に和歌山県に導入されていて、そこから全国に広まった。和歌山県は今でも3位の生産量をほこっている。
トウガラシの辛味は、隔壁、胎座というところで合成される。種が辛いというのはウソだそうだ。実の熟し具合ではいつ頃が一番辛いかというと、赤くなるとカプサイシンは減少しはじめるので赤くなる寸前が一番辛い。でも、樹皮もけっこう辛いように思うが・・。
スコビルという単位についてはまったく説明されていないが、調べてみると、『トウガラシのエキスの溶解物を複数(通常は5人)の被験者が辛味を感じなくなるまで砂糖水に溶かし、その倍率をスコビル値としていた。』いまでは測定器があるそうだが、わりといい加減っぽいから学問の世界では使われないのかもしれない。この本では、1グラム当たりのカプサシノイドの含有量で辛さの度合いを表していた。
それで比べると、ハバネロは鷹の爪の16倍、ブートジョロキアは30倍の辛さになる。
環境でも辛さが変わり、リン酸が多くなると辛味が弱くなるそうだ。ある年、まだ叔父さんの畑で植え始めてもらったころ、叔母さんが枯らせたら一大事だと丹精込めすぎて全然辛くないトウガラシができたことがあった。この説は絶対に正しいと実感している。
トウガラシのほかにも辛いものがある。
コショウはピペリン、山椒はサンショオーール、ショウガはショウガオールとジンゲロールなどいろいろあるがカプサイシンには及ばない。
ワサビはかなり辛い。これはアリルイソチオシアネートという物質で、シニグリンという物質が細胞が壊れるとミシロジナーゼという酵素が働いてアリルイソチオシアネートになる。揮発性が高いので鼻にツンとくる。大根も同じ成分が入っている。
ここまでが植生に関する話題を拾ってみたものだ。
食文化については国や地方ごとに書かれている。辛い食べ物は好きだが、好んで食べに行こうともしないのでここに書かれていることもあまりピンとこない。それにトウガラシって国ごとに固有の品種があり、それを家で作って真似てみようということもできないので、ふ~ん、そうなんだという感想だ。
トウガラシの発祥の地の中南米域ではトウガラシは旨味の食材としても食べられていた。また、チョコレートに入れて飲んでいたともいうが、いったいどんな味だったのだろうか・・。
ヨーロッパにもたらされていろいろな国でいろいろな料理が作られているようだが、ペペロンチーノくらいしかピンとこない。アフリカにいたってはよけいにわからない
南アジアではブータンがすごい。辛味の強いトウガラシを野菜として食べているらしい。ここへは一度行ってみたいと思った。
タイ、ここもすごい。トムヤムクンの国だが、ここにはプリック・キーヌーというトムヤムクンに欠かせないトウガラシは相当辛いらしい。
中国の激辛料理といえば四川料理だが、その特徴は、山椒(花椒)と合わせた香りと激辛のコンビネーションだそうだ。日本には中華料理屋なんていくらでもあるからこれくらいはどこかへ食べに行かないとだめだな。
韓国のトウガラシは意外や日本のトウガラシよりも辛くないらしい。無茶苦茶辛いとキムチにあれほど入れられないそうだ。そうはいっても、毎年買ってくる苗は「韓国激辛トウガラシ」という名前がついている。事実相当辛い。よく考えたら、ほかの激辛トウガラシを食べたことがないから比較をしたことがない。ということは、僕は意外と辛いものには弱いのかもしれない。これはショックな現実を突きつけられた。確かに、渡船屋の奥さんに分けてあげた時の感想が、「マイルドな辛さで美味しかった。」だった。彼女の感想は意外と正しかったのかもしれない。そして僕はほんとうのトウガラシの世界を知らないのかもしれない・・。

しかし、韓国はやっぱりというかなんというか、コロンブスの大陸発見以前から唐辛子があったという研究発表が2009年にされたそうだ。
豊臣秀吉が朝鮮に出兵したときに初めて韓国人はトウガラシを知ったという説もあるくらいだからキムチの歴史もそれほど古くはないと思うのだが・・。
最後に日本のトウガラシ事情だが、大半は辛くない品種だとはいえ、現在40種類もある。ただ、味のメインがトウガラシという料理には出会えない。「激辛」という言葉が流行語大賞1986年だそうだ。それ以来テレビでもいろんな激辛料理が紹介されているが風味付けのひとつという位置付けだ。まあ、日本にはワサビという強敵があるし、様々な調味料もあるからなかなか一般的にはなりにくいのかもしれない。
日本のトウガラシといえば鷹の爪だが、今の鷹の爪は原種ではないそうだ。今は房成りだが原種は節成りの形をしていたという。たしかに叔父さんの家の鷹の爪は房成りで実は上を向いている。熟してくると赤と緑のコントラストがきれいだ。その点、激辛韓国トウガラシは少し黒みがかっているので邪悪さを感じるような辛さの雰囲気はあるけれども美しさはない。だから無茶苦茶辛いのだと思っていたのだが・・。
最後に、どうしてトウガラシは実に辛味を蓄えるようになったかということである。カプサイシンの成分であるリグニンは種皮を硬くするのにも使われる。そのせいで唐辛子の種の種皮は薄いそうだ。そうまでして辛くなったのは鳥に食べてもらってより広く拡散しようという戦略を取ったからだ。哺乳類は種をすりつぶして食べてしまうので糞となって出たころには発芽できる確率が低い。鳥は種を丸のみにするので種皮が薄くても大丈夫で、カプサイシンを嫌わないという違いがある。鳥は飛ぶことができるからより遠くへ種を運んでくれる。
カプサイシンのおかげで哺乳類から守られていたはずだが、人間はその辛さの魅力に取りつかれ、世界中に唐辛子の種を拡散させた。忌避するはずの哺乳類に助けられて唐辛子は世界中に生息域を広げることができたというのである。
これがこの本のオチである。