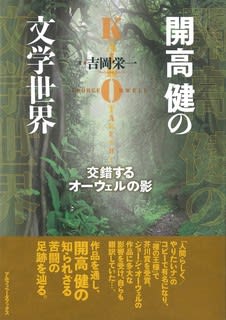吉岡栄一 「開高健の文学世界」読了
著者はオーウェルの研究者だそうだ。僕は1冊も読んだことがないけれども1年ほど前、「共謀罪(改正組織的犯罪処罰法)」が成立するかどうかというときにオーウェルの物語のような世界になってしまうぞなどとマスコミが騒いだので広く知られるようになったように思う。そして著者は師は若い頃にオーウェルに傾倒し、無意識のうちにその作品が相当な影響を受けているというのだ。
確かに師には「動物農場」の翻訳があるけれどもそうだからといって師の著作にオーウェルの影響が色濃く反映されているというのはあまりにも独りよがりのような気がする。
著者によると、師が世間に認められるようになった「パニック」や芥川賞受賞作「裸の王様」にもその寓意性が共通していて、その後発表されている小説やノンフィクションにもいたるところにその痕跡が見られるというのだ。
しかしながら、この本にも書かれているけれども、師は若い頃に読んだことがあるけれどもそれほど心に残るものがなく、後年興味を持ったということなので、ご本人がそうではないと言っているにもかかわらず、いやいや、そんなことを言いながら心の奥底ではそうとうな影響を受けているに違いないのだと論ずるのはどうも合点がいかない。そもそも、師は小説を執筆するときには他の作家の影響を受けたくないという思いでまったく本を読まなかったそうだ。読んだのは聖書や百人一首、レストランのメニューくらいだったらしい。
僕は「パニック」や「裸の王様」に寓意性みたいなものがあるとは思えない。しいて言えば、人間というのは、どうしようもなく自分らしく生きることができない生き物であるということを伝えたかったのではなかったのだろうか。いや、そういうことさえもなく、あとは自分で考えろということに違いないとも思う。それが純文学というものだ。ましてや、後期のいわゆる求心力で書いたと言われる一連の作品には寓意性はないだろう。きっと。
そういう無理な主張を除けばすこぶるよくわかりやすい書評になっていると思う。たくさんの他の作家や評論家の書評が紹介されていたり、作品の紹介が時系列にされているというところも師の歴史を追いやすいところだ。
著者はたまたま読んだ師の翻訳した「動物農場」読み書評を書こうとしたらしいけれども、多分、共謀罪のおかげでオーウェルという作家が世間に知られるようになって、急いで出版を考えたのではないだろうか、だから、あまりにも誤字と脱字が多い。こんなに多い本も珍しいのではないだろうか。それも文学作品の書評でありながら。だから余計にオーウェルの影が作品の随所に見られるという主張がまったく嘘っぽく見えてくる。
普通に書いてくれればかなり親切な本であったことを思うと残念であるけれども、これまた普通に書いてしまうとあまり世間受けしないというジレンマがあるだろうと思うと、まあ、こうでもしなければ仕方がなかったというところだろうか。
著者はオーウェルの研究者だそうだ。僕は1冊も読んだことがないけれども1年ほど前、「共謀罪(改正組織的犯罪処罰法)」が成立するかどうかというときにオーウェルの物語のような世界になってしまうぞなどとマスコミが騒いだので広く知られるようになったように思う。そして著者は師は若い頃にオーウェルに傾倒し、無意識のうちにその作品が相当な影響を受けているというのだ。
確かに師には「動物農場」の翻訳があるけれどもそうだからといって師の著作にオーウェルの影響が色濃く反映されているというのはあまりにも独りよがりのような気がする。
著者によると、師が世間に認められるようになった「パニック」や芥川賞受賞作「裸の王様」にもその寓意性が共通していて、その後発表されている小説やノンフィクションにもいたるところにその痕跡が見られるというのだ。
しかしながら、この本にも書かれているけれども、師は若い頃に読んだことがあるけれどもそれほど心に残るものがなく、後年興味を持ったということなので、ご本人がそうではないと言っているにもかかわらず、いやいや、そんなことを言いながら心の奥底ではそうとうな影響を受けているに違いないのだと論ずるのはどうも合点がいかない。そもそも、師は小説を執筆するときには他の作家の影響を受けたくないという思いでまったく本を読まなかったそうだ。読んだのは聖書や百人一首、レストランのメニューくらいだったらしい。
僕は「パニック」や「裸の王様」に寓意性みたいなものがあるとは思えない。しいて言えば、人間というのは、どうしようもなく自分らしく生きることができない生き物であるということを伝えたかったのではなかったのだろうか。いや、そういうことさえもなく、あとは自分で考えろということに違いないとも思う。それが純文学というものだ。ましてや、後期のいわゆる求心力で書いたと言われる一連の作品には寓意性はないだろう。きっと。
そういう無理な主張を除けばすこぶるよくわかりやすい書評になっていると思う。たくさんの他の作家や評論家の書評が紹介されていたり、作品の紹介が時系列にされているというところも師の歴史を追いやすいところだ。
著者はたまたま読んだ師の翻訳した「動物農場」読み書評を書こうとしたらしいけれども、多分、共謀罪のおかげでオーウェルという作家が世間に知られるようになって、急いで出版を考えたのではないだろうか、だから、あまりにも誤字と脱字が多い。こんなに多い本も珍しいのではないだろうか。それも文学作品の書評でありながら。だから余計にオーウェルの影が作品の随所に見られるという主張がまったく嘘っぽく見えてくる。
普通に書いてくれればかなり親切な本であったことを思うと残念であるけれども、これまた普通に書いてしまうとあまり世間受けしないというジレンマがあるだろうと思うと、まあ、こうでもしなければ仕方がなかったというところだろうか。