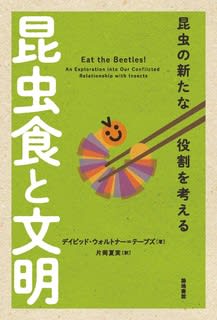デイビッド・ウォルトナー=テーブズ/著、片岡 夏実/訳 「昆虫食と文明―昆虫の新たな役割を考える 」読了
何かのコラムで、地球の食糧危機を救うのは昆虫食だと読んだことがある。それに、「イッテQ」に出てくるタレントたちはほとんど全員、虫を食べた時の感想が“美味しい”と言っているので、虫を食べることでバラ色の世界が開けるのだろうかとこんな本を読んでみた。
しかしながら、やはり虫には嫌悪感を感じる。SF映画では突然人を襲ってくる動物というのはだいたい昆虫型をしているし、伝染病を媒介する。農産物に被害を及ぼして地球を食糧危機にさらす可能性をもっているのも昆虫だ。モーセがエジプトに災いをもたらしたのもバッタだ。だから、人間というのは基本的に昆虫に対しては親近感よりもむしろ嫌悪感の方が勝っている。はずだ。
ただ、節足動物の一角を占める昆虫はやはり同じ節足動物であるエビやカニと味が似通っているらしく、森三中もイモトアヤコも、「エビだ。」「カニだ」と言っている。僕も山形でイナゴの佃煮を食べさせてもらったことがあるけれども確かに美味しかった。そのときに言われたのが、ハチノコはもっと美味しいということだった。そういえば、イモトアヤコは芋虫を食って、濃厚なミルクのようだと言っていた。そうなってくると、人と一緒で、見た目というよりも慣れなのかもしれない。
しかしながら、エビやカニは水中にいて空気中に置いておくといずれは死んでくれるけれども、虫はそうはいかないんじゃないだろうか。いつまでも箱かビンのなかでモゾモゾやっていると思うとやっぱり抵抗がある。
栄養価は高く、カイコの蛹は人間の食用に適するタンパク質の世界保健機関(WHO)の要求を満たすアミノ酸組成だそうだ。(釣り餌のさなぎ粉を食いながら生きてゆけるということか・・)当のコラムには、生産効率もなかなかで、家畜を育てるよりもはるかに効率がいいと書いていたが、この本ではそれほどでもなく、水の使用量だけが少ない程度だという。じゃあ、無理して昆虫を食べなくても牛や豚を食べればいいじゃないかと思うのだが、著者はそのメリットのひとつとして、害虫である昆虫を食べるということは、害虫が減るので殺虫剤を使うことなく農産物を害虫から守ることができるというのだ。
う~ん、これが理にかなっているのかどうかというとなんだか疑問に思うのだけれども、実際そんなことを実践して害虫が減ったという例もあるそうだ。
いっぽうで世界の人口が持続的に食料を確保するためには昆虫食はどうしても必要であると主張する人は多く、現在でも数億人の人口が昆虫を常時口にしている事実から、欧米の文化圏の人たちも昆虫を食べるべきだと啓蒙する団体は、やはり、先入観を捨て去れば食べることができる。生の魚を食べる日本の文化も1世代も過ぎないうちに定着したのだからできないことはないという。しかし、魚と虫を一緒にされても困るのではあるけれども・・。
しかしながら、昆虫食が普及してゆくとして、そこには様々な問題が発生してくると著者は予想する。たとえば、生産を増やすためには人工的に増殖をしなければならないけれども、そこには環境汚染という問題がついてまわる。また、市場が成熟してくると、アフリカや東南アジアで子供や女性といった腕力のない人たちの収入源となっている昆虫の採集が他者に取って変わられるということが出てくる。また、倫理的な観点からは、「虫をどうやって苦痛なく殺して食材に加工するか。」というような、牛や豚なんかの家畜に対する倫理観と同じようなものを当てはめて考えなければならないというのである。
しかし、虫は痛みを感じるのだろうか・・。
食べるものすべてが虫になるということはないのであろうけれども、食料の20%が虫で賄われるとすると、5日に一度は虫を食べるということになる。ハンバーグが出てきて、この肉はバッタ製ですなんて言われると躊躇してしまうのだ。
そんな時代がすぐに来ることはないのだろうけれども、そんなにしてまで生きる必要があるのかなどと思ってしまう。東南アジアの国々は多分ずっとそんな生活が続いているのだろうけれども、そこはやっぱり生きてきた文化の違いだから仕方がない。しかし、どこの遺跡でも、ウンコの化石からは当時の人たちは昆虫を食べていたという痕跡が出るそうだ。そう考えると、ご先祖様たちに叱られてしまいそうなのである。
著者も、食が多様になっていく中で、昆虫食が普通の献立になればいいと書いている。それくらいでいいのである。どうやら、昆虫を食べると素晴らしい未来が開かれているというよりも、食べたい人は食べればいいし、そんな文化を持っていなかったらわざわざ食べる必要もないのじゃないかというありきたりのような結論が僕の中で出てくるのである。
これはあくまでも珍味の範疇でいてほしいと願うのだ。
著者は疫学者で詩人だそうだ。もともと翻訳された本というのは文化的な背景の違いもあるのか読みにくいと思いながら読んでいるのであるけれども、おまけに詩人が書いたとなるとほとほと読みにくい文体になっていた。翻訳者の癖というのもあるのだろけれども、教養のない一般人にも分かるような文体とちょっとした解説入れておいてくれないものだろうかと思うのである。
何かのコラムで、地球の食糧危機を救うのは昆虫食だと読んだことがある。それに、「イッテQ」に出てくるタレントたちはほとんど全員、虫を食べた時の感想が“美味しい”と言っているので、虫を食べることでバラ色の世界が開けるのだろうかとこんな本を読んでみた。
しかしながら、やはり虫には嫌悪感を感じる。SF映画では突然人を襲ってくる動物というのはだいたい昆虫型をしているし、伝染病を媒介する。農産物に被害を及ぼして地球を食糧危機にさらす可能性をもっているのも昆虫だ。モーセがエジプトに災いをもたらしたのもバッタだ。だから、人間というのは基本的に昆虫に対しては親近感よりもむしろ嫌悪感の方が勝っている。はずだ。
ただ、節足動物の一角を占める昆虫はやはり同じ節足動物であるエビやカニと味が似通っているらしく、森三中もイモトアヤコも、「エビだ。」「カニだ」と言っている。僕も山形でイナゴの佃煮を食べさせてもらったことがあるけれども確かに美味しかった。そのときに言われたのが、ハチノコはもっと美味しいということだった。そういえば、イモトアヤコは芋虫を食って、濃厚なミルクのようだと言っていた。そうなってくると、人と一緒で、見た目というよりも慣れなのかもしれない。
しかしながら、エビやカニは水中にいて空気中に置いておくといずれは死んでくれるけれども、虫はそうはいかないんじゃないだろうか。いつまでも箱かビンのなかでモゾモゾやっていると思うとやっぱり抵抗がある。
栄養価は高く、カイコの蛹は人間の食用に適するタンパク質の世界保健機関(WHO)の要求を満たすアミノ酸組成だそうだ。(釣り餌のさなぎ粉を食いながら生きてゆけるということか・・)当のコラムには、生産効率もなかなかで、家畜を育てるよりもはるかに効率がいいと書いていたが、この本ではそれほどでもなく、水の使用量だけが少ない程度だという。じゃあ、無理して昆虫を食べなくても牛や豚を食べればいいじゃないかと思うのだが、著者はそのメリットのひとつとして、害虫である昆虫を食べるということは、害虫が減るので殺虫剤を使うことなく農産物を害虫から守ることができるというのだ。
う~ん、これが理にかなっているのかどうかというとなんだか疑問に思うのだけれども、実際そんなことを実践して害虫が減ったという例もあるそうだ。
いっぽうで世界の人口が持続的に食料を確保するためには昆虫食はどうしても必要であると主張する人は多く、現在でも数億人の人口が昆虫を常時口にしている事実から、欧米の文化圏の人たちも昆虫を食べるべきだと啓蒙する団体は、やはり、先入観を捨て去れば食べることができる。生の魚を食べる日本の文化も1世代も過ぎないうちに定着したのだからできないことはないという。しかし、魚と虫を一緒にされても困るのではあるけれども・・。
しかしながら、昆虫食が普及してゆくとして、そこには様々な問題が発生してくると著者は予想する。たとえば、生産を増やすためには人工的に増殖をしなければならないけれども、そこには環境汚染という問題がついてまわる。また、市場が成熟してくると、アフリカや東南アジアで子供や女性といった腕力のない人たちの収入源となっている昆虫の採集が他者に取って変わられるということが出てくる。また、倫理的な観点からは、「虫をどうやって苦痛なく殺して食材に加工するか。」というような、牛や豚なんかの家畜に対する倫理観と同じようなものを当てはめて考えなければならないというのである。
しかし、虫は痛みを感じるのだろうか・・。
食べるものすべてが虫になるということはないのであろうけれども、食料の20%が虫で賄われるとすると、5日に一度は虫を食べるということになる。ハンバーグが出てきて、この肉はバッタ製ですなんて言われると躊躇してしまうのだ。
そんな時代がすぐに来ることはないのだろうけれども、そんなにしてまで生きる必要があるのかなどと思ってしまう。東南アジアの国々は多分ずっとそんな生活が続いているのだろうけれども、そこはやっぱり生きてきた文化の違いだから仕方がない。しかし、どこの遺跡でも、ウンコの化石からは当時の人たちは昆虫を食べていたという痕跡が出るそうだ。そう考えると、ご先祖様たちに叱られてしまいそうなのである。
著者も、食が多様になっていく中で、昆虫食が普通の献立になればいいと書いている。それくらいでいいのである。どうやら、昆虫を食べると素晴らしい未来が開かれているというよりも、食べたい人は食べればいいし、そんな文化を持っていなかったらわざわざ食べる必要もないのじゃないかというありきたりのような結論が僕の中で出てくるのである。
これはあくまでも珍味の範疇でいてほしいと願うのだ。
著者は疫学者で詩人だそうだ。もともと翻訳された本というのは文化的な背景の違いもあるのか読みにくいと思いながら読んでいるのであるけれども、おまけに詩人が書いたとなるとほとほと読みにくい文体になっていた。翻訳者の癖というのもあるのだろけれども、教養のない一般人にも分かるような文体とちょっとした解説入れておいてくれないものだろうかと思うのである。