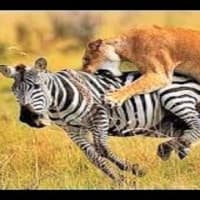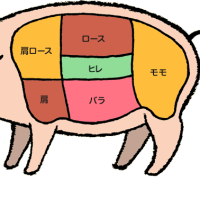本を読んでうなったのは久しぶりだ。『ブラック企業』(文春新書)という本である。私のFBに紹介されていたので買ってみた。

若者の就職難、ニート、フリーターといった問題が出てきたのは、日本が豊かになりすぎたためではないか?大学が増えすぎて分数の足し算さえできないような学生が増えたためではないか?なぞと、私は漠然と考えていた。
だがこの本は、問題の本質はもっと別のところにあると見破っていた。一言でいえば、日本型の終身雇用的な習慣の「いいとこどり」をした企業ほど伸びるような構造に、日本社会がなってしまっているのだと私には読めた。
また、「最近の若い者は・・」という文脈では捉えきれない構造的な問題を、現在の雇用システムはかかえているとも読めた。
新人研修の厳しさが取り上げられていたが、それは生産的な厳しさでなく、社員を服従させるための手段だという主張には説得力があった。読み物や映画でしか知らないが、昔の軍隊がそのような教育(馴化)やっていたのではないかと連想した。著者は「マインド・コントロール」という言葉も使っている。
著者は晩婚化問題、少子化問題にも言及している。これらはとどのつまり、雇用問題だと説明している。
本書の内容にも感心したが、そのような言説を発表する著者にも感心した。著者はまだ30歳を過ぎたばかりである。それでいて、この堂々とした論陣はどうだ。大したものである。
若手の社会学者とか、若手のサブカルチャー評論家なぞがテレビに出ていて、一見目新しいことを言っているが、心から同意はできなかった。
ところが、この本の著者には説得された。日本の若い論客も捨てたものではないなぁと、少しばかり嬉しくなったので報告する。

若者の就職難、ニート、フリーターといった問題が出てきたのは、日本が豊かになりすぎたためではないか?大学が増えすぎて分数の足し算さえできないような学生が増えたためではないか?なぞと、私は漠然と考えていた。
だがこの本は、問題の本質はもっと別のところにあると見破っていた。一言でいえば、日本型の終身雇用的な習慣の「いいとこどり」をした企業ほど伸びるような構造に、日本社会がなってしまっているのだと私には読めた。
また、「最近の若い者は・・」という文脈では捉えきれない構造的な問題を、現在の雇用システムはかかえているとも読めた。
新人研修の厳しさが取り上げられていたが、それは生産的な厳しさでなく、社員を服従させるための手段だという主張には説得力があった。読み物や映画でしか知らないが、昔の軍隊がそのような教育(馴化)やっていたのではないかと連想した。著者は「マインド・コントロール」という言葉も使っている。
著者は晩婚化問題、少子化問題にも言及している。これらはとどのつまり、雇用問題だと説明している。
本書の内容にも感心したが、そのような言説を発表する著者にも感心した。著者はまだ30歳を過ぎたばかりである。それでいて、この堂々とした論陣はどうだ。大したものである。
若手の社会学者とか、若手のサブカルチャー評論家なぞがテレビに出ていて、一見目新しいことを言っているが、心から同意はできなかった。
ところが、この本の著者には説得された。日本の若い論客も捨てたものではないなぁと、少しばかり嬉しくなったので報告する。