「屋台」というと、どのようなものを想像されるだろうか?私が連想するのは、祭りの出店ではない。あれは、「夜店」と言った。昼間も出ているから「露店」と呼ぶこともあった。
むろん、京都の祇園祭の「屋台」なんて連想しない。私が考えるのは以下のような移動式の店舗である。

この画像は、dai という人が描いたCGである。手前にカウンターがある。CGには描かれていないが、カウンターの前に椅子が4脚ほど置いてある。客は椅子に座ってカウンターにおでんや酒を置いて、飲食をするのだ。カウンターの向こうには親父がいる。
とにかく安い。今ならコンビニでおでんやカップ酒を売っているから、それを買ってコンビニのビュッフェみたいなところで食せば、屋台と同じような雰囲気が味わえるかもしれない。
博多の屋台は名物とされているが、あんなの屋台ではない。普通店舗の居酒屋よりもむしろ高い。刺身なんかを置いてある。だいたい冷蔵庫がある屋台はありえない。そして、博多の屋台は移動できない。
本来の屋台は写真のように車輪が付いていなくてはならない。いつでも移動できるようにだ。
私が学生時代、大学病院の向かいにいつも居るおでんの屋台があった。友人と1回だけ利用した。コップ酒1杯とおでん3個くらいで100円くらいだったと思う。
三波春夫の「月がわびしい路地裏の屋台の酒のほろ苦さ。知らぬどうしが小皿叩いてちゃんちきおけさ」という歌は、まさにあのころのこういう屋台を歌った歌だ。
実際、友人と座った時はわびしかった。南こうせつの「神田川」という大ヒット曲があるが、まさにあの時代のあのわびしさを言い当てているのだ。
むろん、京都の祇園祭の「屋台」なんて連想しない。私が考えるのは以下のような移動式の店舗である。

この画像は、dai という人が描いたCGである。手前にカウンターがある。CGには描かれていないが、カウンターの前に椅子が4脚ほど置いてある。客は椅子に座ってカウンターにおでんや酒を置いて、飲食をするのだ。カウンターの向こうには親父がいる。
とにかく安い。今ならコンビニでおでんやカップ酒を売っているから、それを買ってコンビニのビュッフェみたいなところで食せば、屋台と同じような雰囲気が味わえるかもしれない。
博多の屋台は名物とされているが、あんなの屋台ではない。普通店舗の居酒屋よりもむしろ高い。刺身なんかを置いてある。だいたい冷蔵庫がある屋台はありえない。そして、博多の屋台は移動できない。
本来の屋台は写真のように車輪が付いていなくてはならない。いつでも移動できるようにだ。
私が学生時代、大学病院の向かいにいつも居るおでんの屋台があった。友人と1回だけ利用した。コップ酒1杯とおでん3個くらいで100円くらいだったと思う。
三波春夫の「月がわびしい路地裏の屋台の酒のほろ苦さ。知らぬどうしが小皿叩いてちゃんちきおけさ」という歌は、まさにあのころのこういう屋台を歌った歌だ。
実際、友人と座った時はわびしかった。南こうせつの「神田川」という大ヒット曲があるが、まさにあの時代のあのわびしさを言い当てているのだ。












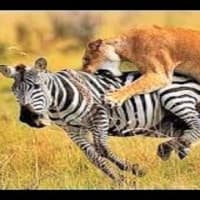






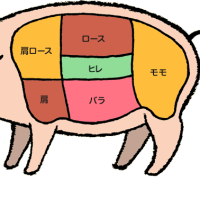
小さな屋台なのに超人気で、いつも屋台の周りをたくさんの男たちが取り囲んでいました。男たちは、NHKとその向かいの三井物産のビルで残業をするサラリーマンでした。
私はそのころ、内幸町から歩いて15分くらいの愛宕町の実家に住んでいました。受験勉強に疲れて小腹が空くと、この屋台にラーメンを食べに行きました。一杯いくらだったか忘れましたが、前金を払うと食券の代わりに割り箸をくれました。順番がきてアツアツの丼を受け取ると、屋台のカウンターや椅子は満員ですから、NHKか三井物産のビルの大理石のような石でできた土台に腰を掛けて、ラーメンを食べたものです。昼間、このあたりを通ると、ビルの土台のあちこちに、ラーメン丼を置いた丸い跡が付いていました。
割り箸を握りしめて行列を作り、一緒にラーメンを食べた40年代の男たちは、エネルギッシュでかっこよく見えました。その何年か後、就職試験の対象に放送局と総合商社を選んだのは、この屋台のラーメンの影響があったのかもしれません。
高度成長の時代は過ぎ去り、NHKも三井物産も内幸町から移転してしまい、屋台のラーメン屋は千駄ヶ谷に店を構えたと聞きました。割り箸を握ってがむしゃらに働き勉強していた時代から、何もかもが変わってしまいました。今夜、藤圭子の訃報を聞き、同じ時代を生きた彼女にとって、現代はさぞや生きづらい世の中だったのだろうなと考えています。
チャルメラの音が面白く、中学時代にチャルメラを買ってきたことがあります。(そのころ僕はクラリネットをやっていましたので、すぐに吹けました。)
ただ、父親が屋台のラーメンを嫌っていたことから、僕は屋台のラーメンを食べたことがありません。父親が嫌う根拠は「不潔だ」ということです。別の人が食べたどんぶりをバケツの水でササッと流し、バケツの水がすでに白くなっているのがイヤだったそうです。
その後、覚えておられるかどうか「手首ラーメン」の事件があって、いよいよ食べられなくなってしまいました。一度くらい経験しておけばよかった。
このブログに、流しの焼きイモ屋がいなくなったと書いたら、どなたかが、スーパーで安く焼きイモを売るようになったからだろうとか、当地にはまだあるといったコメントをいただきました。
あのころは、まだ行商人が多かったですね。みな必死に働いていた。そうした底辺から出てきたのが藤圭子でしたね。(もと「流し」だったというのはプロダクションが作った作り話かもしれませんが。)
僕は医者になってから早々に、尊敬する院長(故人)に酒場に連れて行ってもらいました。まだ「流しの歌手」がいました。ギターひとつで何でも歌えました。すぐにカラオケが爆発的に普及して「流しの歌手」は撲滅されました。それ以後、日本はバブルに突入していきました。なんだか毎日がお祭りみたいでした。