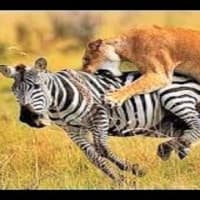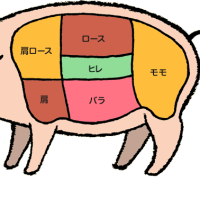(郵便車スユ15(2001)。ウィキメディアコモンズより引用。spaceaero2 氏によるCCライセンス。)
表題のような題名の絵本を小学校1年生のころ読みました。都会の幼い孫が北国の田舎に住むおばあちゃんに手紙を出すという物語仕立てです。
孫がポストに手紙を投函するところから始まり、中央郵便局での手作業による郵便の仕分け(当時は郵便番号なぞありません)、続いて写真のような鉄格子の入った郵便車が疾走します。こうして孫の手紙は運ばれていきます。
列車の鉄格子から、郵便(小包や現金書留も含む)とはいかに大事なものなのかを子どもは学びます。(現在ではほとんどが空輸だそうですね。郵便車を見かけません。)
山奥に住むおばあちゃんの家までは、現地の郵便配達人が徒歩で運びます。雪深く、配達人は膝まである雪を掻きわけて、おばあちゃんの家まで突き進みます。
ここで感動しない子どもはいないでしょう。昨日、私は郵政の悪口を書きましたが、根底には尊敬の念をもっているのです。
(数学者でエッセイストの藤原正彦氏は、イギリスに国際小包はまず届かない、何回も催促してやっと届いても中味が抜かれていると書いています。職務に忠実でない者たちが間に何人も挟まると、生産性がゼロになる例ですね。)
※今日、気にとまった短歌
五円玉一つのアイスキャンディよ冷房など無き高校のころの (杉並区)本間木丈