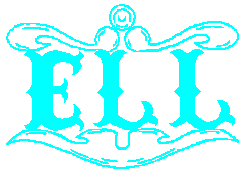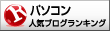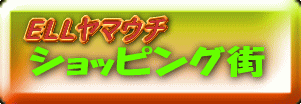日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
人というものは、結構、他人の目を気にしてしまうことがあります・・・
例えば、服装や髪形を気にする・・・というのは・・・
少なからず他人の目を意識しているんだと思うんですよね。
ということは、他人に認めてもらいたいという心理が働いているんじゃないのかな・・・
まじめ過ぎるくらいの人が仕事上で鬱状態になったりするのは、
責任感が強く・・・失敗したら自分のせい・・・などと考えてしまうらしいんですよね。
こういうタイプの人って・・・2月9日のブログ
ネガティブな考えの人! 「認知行動療法」で少しでも前向きに!
他人に認めてもらうことで自らの価値を感じる「承認依存」、
問題が起きると責任は自分にあると思う「自己非難」、
ミスをするとひどく動揺する「完全主義」の度合いが、通常より強い傾向がみられた・・・
と、臨床心理士の方が仰ってたらしいんです。
だから、そのためにも認知行動療法は必要な気がします・・・
事実、私の姉も私たちの言葉や接し方でホンマに前向きな考え方に変わってきました・・・
この考え方は、ひきこもりの人たちに対しても通用するような気がするんですが・・・如何なんでしょうね・・・
今朝は、ひきこもりから脱した新社会人に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、4月26日読売新聞夕刊より抜粋~

自転車で出勤する片岡さん。「家
族のためにも早く一人前になりた
い」と話す(大阪市旭区で) 今月入社した製袋 加工会社では研修の日々が続く。緊張する場面も多いが、上司から「失敗なしには成長できない」と言われ、最近は少し肩の力が抜けるようになった。朝、出社時に自転車で駅に向かっていると、昔と別人になったように感じる。
 保育園児の頃から、集団の中にいると「モヤッとした怖さ」を感じた。小学校で休みがちになり、5年生の時は1日も登校できなかった。中学に入学して2日目、作文の書き方が分からず、「この先、出来ないことばかりだろう」と思うと、翌日から登校できなくなった。
保育園児の頃から、集団の中にいると「モヤッとした怖さ」を感じた。小学校で休みがちになり、5年生の時は1日も登校できなかった。中学に入学して2日目、作文の書き方が分からず、「この先、出来ないことばかりだろう」と思うと、翌日から登校できなくなった。
自室にこもり、教師が来ると布団をかぶってやり過ごした。夜中にパソコンに向かい、外が明るくなると寝た。体重が増え、トイレに行くだけで息が切れた。
幼いころから母の浩子さん(49)と姉(25)との3人暮らし。「心配ばかりかけ、迷惑な存在だ」と負い目を感じた。「死にたい」とつぶやき、パソコンで「自殺」という言葉を検索した。
17歳のある日、自殺に関する本を買ってきてほしいと浩子さんに伝えた。「いざとなれば死ねると思えたら、気持ちが楽になるはずだ」と必死に考えた末のことだった。
浩子さんは根負けして買ってきたが、心配で毎晩、片岡さんの部屋をのぞいた。だが、片岡さんはその日を境に死を口にしなくなった。浩子さんの勧めで支援機関に通った。夜に姉に付き添ってもらい、ジョギングを始めた。3人で山登りにも出かけた。
浩子さんに「ゆっくりでいい。一緒に乗り越えていこう」と励まされ、「自力で人生を歩み、家族の力になりたい」と考えるようになった。検索する言葉は「アルバイト」に変わった。
18歳を前に、大阪府立大手前高(大阪市)の定時制課程に入学。集団の中にいると「怖さ」がよみがえる日もあったが、「あの頃に戻りたくない」と登校を続けた。
スーパーでレジ打ちのバイトも始めた。客と言葉を交わす機会が増え、自分から同級生に話しかけられるようになった。バドミントン部に入り、4年で部長になり、定時制高校の府大会で優勝した。高校はほぼ皆勤で、就職も決まった。「どん底を経験したから、この先どんなに辛いことでも乗り越えられる」と話す。
苦しい時期に毎晩、涙ながらに「変わりたい」と話す自分に、母は「絶対に助けるから」と寄り添ってくれた。「僕が変われたのは家族の見守りや支えがあったから」。初任給で、母と姉に食事をごちそうしたいと考えている。
例えば、服装や髪形を気にする・・・というのは・・・
少なからず他人の目を意識しているんだと思うんですよね。
ということは、他人に認めてもらいたいという心理が働いているんじゃないのかな・・・
まじめ過ぎるくらいの人が仕事上で鬱状態になったりするのは、
責任感が強く・・・失敗したら自分のせい・・・などと考えてしまうらしいんですよね。
こういうタイプの人って・・・2月9日のブログ
ネガティブな考えの人! 「認知行動療法」で少しでも前向きに!
他人に認めてもらうことで自らの価値を感じる「承認依存」、
問題が起きると責任は自分にあると思う「自己非難」、
ミスをするとひどく動揺する「完全主義」の度合いが、通常より強い傾向がみられた・・・
と、臨床心理士の方が仰ってたらしいんです。
だから、そのためにも認知行動療法は必要な気がします・・・
事実、私の姉も私たちの言葉や接し方でホンマに前向きな考え方に変わってきました・・・
この考え方は、ひきこもりの人たちに対しても通用するような気がするんですが・・・如何なんでしょうね・・・
今朝は、ひきこもりから脱した新社会人に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、4月26日読売新聞夕刊より抜粋~
家族 次は僕が支える
5年のひきこもり脱し 新社会人に
学校や仕事に行かず、孤立している「ひきこもり」の若者は全国で54万人いると推計されている。社会への復帰が課題となる中、中学1年から5年間、ひきこもりを経験した大阪市旭区の片岡勝也さん(23)はこの春、社会人として一歩を踏み出した。自ら命を絶つことを考えた時期もあったが、家族の支えで外に出られるようになり、少しずつ自信をつけていった。今は「僕が家族を支える番」と思っている。
(宮原洋)

自転車で出勤する片岡さん。「家
族のためにも早く一人前になりた
い」と話す(大阪市旭区で)

自室にこもり、教師が来ると布団をかぶってやり過ごした。夜中にパソコンに向かい、外が明るくなると寝た。体重が増え、トイレに行くだけで息が切れた。
幼いころから母の浩子さん(49)と姉(25)との3人暮らし。「心配ばかりかけ、迷惑な存在だ」と負い目を感じた。「死にたい」とつぶやき、パソコンで「自殺」という言葉を検索した。
17歳のある日、自殺に関する本を買ってきてほしいと浩子さんに伝えた。「いざとなれば死ねると思えたら、気持ちが楽になるはずだ」と必死に考えた末のことだった。
浩子さんは根負けして買ってきたが、心配で毎晩、片岡さんの部屋をのぞいた。だが、片岡さんはその日を境に死を口にしなくなった。浩子さんの勧めで支援機関に通った。夜に姉に付き添ってもらい、ジョギングを始めた。3人で山登りにも出かけた。
浩子さんに「ゆっくりでいい。一緒に乗り越えていこう」と励まされ、「自力で人生を歩み、家族の力になりたい」と考えるようになった。検索する言葉は「アルバイト」に変わった。
きっかけは不登校や人間関係
昨年9月の内閣府の調査では、15~39歳の若い世代で半年以上自宅からほとんど外出しないひきこもりの状態にある人は、全国に約54万人いると推計された。
当事者49人に聞いたひきこもりのきっかけは「不登校」「職場になじめなかった」が各9人で最多。ひきこもりを脱した158人に役立ったことを尋ねると、家族や友人、医療・支援機関などの存在が挙げられた。
相談窓口として、都道府県や政令市計68か所に「ひきこもり地域支援センター」がある。15~39歳の人が働くことに悩みを抱える場合は、全国173か所の「地域若者サポートステーション」で支援が受けられる。
一方、文部科学省の2015年度調査によると、小中学校で不登校の児童生徒は約12万5000人。不登校になった本人に関する要因は「『不安』の傾向がある」が30.6%と最多。本人以外の要因は「家庭状況」(37.7%)、「友人関係」(26.4%)などがあった。
児童生徒を対象にした相談や支援は、全国の教育委員会が設ける教育センターや教育支援センター(適応指導教室)などで行われている。
当事者49人に聞いたひきこもりのきっかけは「不登校」「職場になじめなかった」が各9人で最多。ひきこもりを脱した158人に役立ったことを尋ねると、家族や友人、医療・支援機関などの存在が挙げられた。
相談窓口として、都道府県や政令市計68か所に「ひきこもり地域支援センター」がある。15~39歳の人が働くことに悩みを抱える場合は、全国173か所の「地域若者サポートステーション」で支援が受けられる。
一方、文部科学省の2015年度調査によると、小中学校で不登校の児童生徒は約12万5000人。不登校になった本人に関する要因は「『不安』の傾向がある」が30.6%と最多。本人以外の要因は「家庭状況」(37.7%)、「友人関係」(26.4%)などがあった。
児童生徒を対象にした相談や支援は、全国の教育委員会が設ける教育センターや教育支援センター(適応指導教室)などで行われている。
18歳を前に、大阪府立大手前高(大阪市)の定時制課程に入学。集団の中にいると「怖さ」がよみがえる日もあったが、「あの頃に戻りたくない」と登校を続けた。
スーパーでレジ打ちのバイトも始めた。客と言葉を交わす機会が増え、自分から同級生に話しかけられるようになった。バドミントン部に入り、4年で部長になり、定時制高校の府大会で優勝した。高校はほぼ皆勤で、就職も決まった。「どん底を経験したから、この先どんなに辛いことでも乗り越えられる」と話す。
苦しい時期に毎晩、涙ながらに「変わりたい」と話す自分に、母は「絶対に助けるから」と寄り添ってくれた。「僕が変われたのは家族の見守りや支えがあったから」。初任給で、母と姉に食事をごちそうしたいと考えている。