この数ヶ月、藤田端討論をはじめいろいろなネタを提供し続けてくれた藤田孝典氏。
藤田氏の主張をツイッター上で眺めてきた。
その藤田氏が、ZOZO社長の1億円お年玉イベントでついに不満を爆発させた。
○拝啓、ZOZO前澤友作様「1億円バラマキ、本当に下品です」『藤田孝典』 2019/01/09
個人が私財をどう処分しようとその個人の勝手であり、それを第三者が難癖つけるのはただの嫉妬でしかない。
この嫉妬に満ちた文章の中に、雇用や会社の利益、賃金についての藤田氏の考え方が随所に表れている。この中にある誤りや問題点、気になったところを指摘していこう。
近年、東証に上場する企業、急成長する企業は、派遣労働者、非正規雇用を大量に利用して利益をあげてきた。彼らの富の源泉は、低賃金労働者への労働力搾取に起因している。その成長や利益の背後には、大量の派遣労働者が存在している。
======【引用ここまで】======
汗を流す、一生懸命働く、こうした努力は、それだけでは価値や利益を生じない。
真夏に穴を掘って埋める作業は大変な労力であり、これに従事する人は相当な汗を流すことになるだろう。しかし、ただ穴を掘って埋めても世の中に何の価値ももたらさないし、何ら利益を生じさせない。
労働には適切な方向付けが必要である。労働から利益を上げるために、事業主は、その労働によって何を生み出しどこへ提供するか企画しなければならない。この企画が的外れなものであれば、利益を上げることはできない。
ここで重要なのは、利益は後から生じるもの、ということだ。
商品を開発し、生産し、販売先を確保し、代金を回収して初めて利益が生じるわけだが、数か月で利益が出れば早い方。数年、10年以上かかることもあるだろう。
このため、利益と賃金を連動させて考えると問題が生じる。
「雑木林を開墾して田んぼを作り、米を作って売ろう」
と考えたとする。
作業員を募集する際には、労働時間、条件、内容を考慮して、似たような他の作業と同じ程度かそれ以上の額を支払うことを約束して募集することになる。
伐採や土壌改良に3年かかり、開墾後の春に田植え、夏に草刈り、秋に収穫、そして冬に米が売れて初めて利益になる、としよう。
この時、開墾2年目に作業員が地主に対し
「雇用されて開墾に従事して丸1年が経過したのに、一度も賃金が払われないのはどういうことか」
と苦情を述べた。地主から
「まだ利益が出てないんだから賃金なんて払えるわけないだろ。2年後の収穫を待っておくれ」
と言われて、納得する作業員はいないだろう。みんな辞めてしまう。
利益が出るまでの間であっても、作業員に賃金を支払うことを約束しなければ雇用契約は成立しない。この間の賃金は、地主が予め調達した資金の中から支払われることになる。
雇用契約が成立し、3年の開墾を終えて春の田植えを終えた後に、台風で稲が全滅し、あるいは洪水で開墾地そのものが流されてしまったとしよう。地主には利益どころか莫大な損失が生じる。それでも、地主は作業員に対し、作業してもらった期間に応じて契約に基づく賃金を支払わなければならない。払えなければ破産するしかない。
地主は、様々なリスクを負っている。
災害が起きるかもしれない、
稲が病気になって収穫ができないかもしれない、
逆に豊作で米価格が大暴落するかもしれない、
作付けした米の品種の人気が思ったより低くて高値で売れないかもしれない、
空前のパスタブーム到来で誰も米に見向きしなくなるかもしれない、
等、様々なリスクに晒されている。そうした将来の不確実なリスクの中、地主は作業員に対し雇用期間中の賃金を約束し、予め調達した資金の中から賃金の支払いを続けなければならない。
逆に言えば、契約に基づき賃金が支払われている限り、そこに倫理的な問題は生じない。利益が生じる前に、地主と作業員との間で金額や労働条件について同意しているからだ。また、最低賃金法(=「未熟練労働者切捨法」)に定める以上の金額を払っていれば、法的な問題も生じない。
さて。
4年間契約どおり賃金を払い続けて開墾を終え、作付けを済ませて無事に収穫を迎え、販売した結果、予想より大きな利益が出たとする。
この利益は、地主のものである。
地主がその利益の中から、
「作業員のみんな、今までありがとう!収穫祝いとして一時金を支給します!」
と配るのは、あくまで地主の任意によるものだ。
作業員の側から
「収穫の利益は俺たちのものだ。地主が独り占めにしてずるいなぁ」
と愚痴をこぼすのは勝手だが、外部から
「作業員の主張は当然であり、地主が利益を作業員に分配するのは義務である」
と強制するのであれば、災害や不作、販売不振によるリスクも作業員が分担して負うべきだろう。
作業員は、
「不作で予想利益の半分になったから、当面、賃金も半分ね」
と言われて、果たして納得するであろうか。
「利益が出る前に賃金を払う」という雇用の枠組みそのものが崩壊するのではないか。
「事業主と労働者で利益を山分け、損失も山分け」
という仕組みは、企業内の一体感を高める上で効果的かもしれない。
しかし、多くの労働者はこれを望んでいるのだろうか。
会社が倒産する寸前まで賃金が契約どおり支払われるのが良いか、それとも、会社の利益と損失に比例してその都度賃金が上下するのが良いか。
賃金が契約通り支払われているのに、企業の業績が良い時だけ
「事業主が大きな利益を得るのは不当だ」
と主張するのは、無責任な妬み、やっかみでしかない。
彼らの言う社員や従業員のなかに派遣労働者は含まれていないばかりか、正社員との待遇差別も著しい。
派遣や非正規は好きでやっているのではないか、という意見もあるが、「不本意非正規の状況」(厚生労働省)によれば、正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者(不本意非正規)の割合は、非正規雇用労働者全体の14・3%(平成29年平均)である。相変わらず、不本意非正規の数も多い。
======【引用ここまで】======
日本では、正社員を一旦雇用すると、解雇するのが難しい。
雇用して勤務させてみて、
「この人はうちの会社に全然向いていない」
と気付いても、これを理由にすぐ解雇することはできない。
仮に解雇しても、訴訟になれば、裁判所が
「本当に向いてないのか、研修を受けさせたりして能力向上を試みたか、配置転換で対応できないか」
等と難癖をつけて解雇に待ったをかけてしまう。
これは正社員労組が、企業や世間に対し長く求めてきた主張でもある。
こうした裁判所や労組の動きは、企業側に
「正社員を一度雇うとクビにできないから、採用は控えよう」
と正社員の雇用数を抑制する方向に作用した。
正社員数を抑える一方で、繁忙期と閑散期の人員必要数の調整を非正規雇用や派遣労働者で行う仕組みが出来上がった。
その結果が、
「正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者(不本意非正規)」
の増加である。椅子取りゲームの椅子が中々空かないから、周りの人は早く座りたいのに延々と回り続けることになる。
解雇規制が雇用の流動性を阻害し、ここから正規・非正規の身分格差や年功賃金体系、新卒一括採用といった慣行が成立している。同一労働同一賃金を妨げているのが解雇規制だ。
正社員は、こうした解雇規制や年功賃金といった手厚い身分保障を持っているが、これは非正規雇用の犠牲の上に成り立つものである。
正社員労組や自治労の主催するシンポジウムや講演会でひっぱりだこの藤田氏が、どの面下げて正社員と非正規労働者の格差を語るのだろうか。
もし、藤田氏がこうしたシンポジウムや講演会の中で
「正社員である組合員のみなさんの身分保障は、非正規雇用の方々がいるから可能なんですよ。あなた達への手厚すぎる身分保障が格差の原因です」
と説いて回っているのであれば別だが。
日本の相対的貧困率は15・7%(平成27年)と主要先進国の中でも高い。日本は貧困に苦しむ国民が多い国である。なかでも働く労働者の貧困であるワーキングプアは大きな社会問題となっている。
子供の貧困も働く親の所得の低さに原因があり、その背景にはワーキングプア問題がある。特にシングルマザーの貧困は、先進諸国最悪の相対的貧困率を記録するほど深刻であり、女性のひとり親の多くが非正規雇用で働いている。
======【引用ここまで】======
相対的貧困率は、貧困層の多さではなく格差の度合いを示すものだ。
みんなが貧しくなれば相対的貧困率は改善する。みんな貧しくなることによって格差は是正されるが、果たしてこれは良い事だろうか。
また、相対的貧困率は貯蓄の有無を考慮しない数値であるため、高齢化が進めば相対的貧困率も上がる。相対的貧困率は実際の貧困の状況を表さない。
相対的貧困率と貧困の具体的内容とが入り混じっている文章を見かけた時は、相対的貧困率に関する部分を全部飛ばして読んでも全く問題ない。飛ばした方が、具体的にどういう状態にあって貧困に苦しんでいるかがスッキリして分かりやすくなる。
相対的貧困率が高いことを問題視する人は多いが、相対的貧困率が以前と比べて下がった場合にこれを素直に評価する人は少ない。湯浅誠氏くらいじゃなかろうか。
○子どもの貧困率が減った! 何がどう変わったのか 湯浅誠
他の人は、
「相対的貧困率が下がったとは言え、他の指標が~」
等と言って改善を認めない。
それなら、最初から相対的貧困率を貧困の指標として用いなければ良いではないか。
なお、女性のひとり親の多くが非正規雇用で働いている原因も、正社員の身分保障が手厚すぎる点にある。このことについては上述のとおり。
同社は、これら低賃金労働者の存在に甘えて、株価の高騰や企業の成長を維持しているにすぎない。どれだけ株価高騰、企業価値の向上は経営陣の手腕だと言おうが、現場の労働者がいなければ生産や流通を担えないし、富は絶対に発生しない。古くはカール・マルクスが19世紀に大著『資本論』において喝破した内容である。
======【引用ここまで】======
マルクスが唱えた内容は、20世紀前半にミーゼスやハイエクが「社会主義経済計算論争」で批判したものであり、この批判のとおりにソ連体制は行き詰まった。マルクスは「亡霊」であり、労働価値説を初めとする誤った言説とともに一刻も早く成仏してもらうのが良い。
労働者がいなければ富は発生しない、それはそうである。
しかし、経営者がいなければ雇用は発生しない。
労働者と経営者を繋ぐものが契約である。
そして、契約において賃金の額を定める最大の要素は、他の企業の類似の労務内容なら幾ら位になっているか、という賃金相場である。
労働者と経営者が任意の契約によって繋がっていて、その契約内容が守られている限り、そこに搾取という概念は生じない。
この街宣活動に至った理由は、私の元に派遣労働者から匿名で相談が寄せられたからでもある。相談は業務内容に比例して賃金があまりにも安いというものだ。正社員の賃金や待遇は一定程度担保されているが、派遣労働や非正規の現場は凄惨(せいさん)だというのである。
彼女の訴えによれば、時給は3年間働いても1000円のままであり、責任をもって顧客の配送先である住所や名前など個人情報を扱うにしては低すぎるというものだ。これらの信ぴょう性を確認するための行動だった。
新習志野で多くの派遣労働者と話をすることができた。前澤社長や田端氏は現場の倉庫には足を運んで派遣労働者の声を聞いていないことも理解できたし、匿名の彼女の訴えは真実だとも理解できた。実際に新習志野で話した20歳代前半男性の派遣労働者は「僕の時給は1000円です。個人情報を大量に管理していますし、この賃金では安いと思います。社長が1000億円もかけて月に行くというなら僕らの賃金を上げてもらいたいというのが正直なところです」と語った。
======【引用ここから】======
藤田氏は
「個人情報を扱っているから、時給1000円では安い」
という非正規労働者の声を紹介しているが、どこを読んでもその理由が伝わってこない。
個人情報を扱っていない他の業務は現状維持でも良いが、個人情報を扱う私の賃金は高くしろということなのだろうか。
藤田氏は
「誰にでも出来る仕事の給料は上がらない」
といった主張を
「上から目線で労働者を蔑視する」
ものとして批判している。
では、
「時給1000円は個人情報を扱うにしては低すぎる」
は良いのだろうか。暗に、個人情報を取り扱う業務と比べて、他の業務を上から目線で蔑視していないだろうか。
もし、他の企業で、個人情報を扱う類似の業務が時給1200円の所があれば、ZOZOの非正規雇用を離れて他の会社に行けば良い。離職が企業にとって最も有効な圧力である。そうなれば、雇用の流出を止めるため時給引き上げを検討せざるを得なくなる。
ところで、
======【引用ここから】======
彼の職務内容を聞けば、責任ある正社員が行うべき業務を派遣労働者が低賃金で担っている。
======【引用ここから】======
藤田氏に相談した派遣労働者は、自身が低賃金であることを憤っているようだ。
それって、派遣元企業に相談すべき内容ではなかろうか。
ホームページでZOZOのアルバイト採用を見ると時給1000円となっていたが、派遣元企業はZOZOへ派遣した派遣労働者の賃金を幾らで設定しているのだろうか。
末端の労働者を重視しない企業であれば、株価にも影響するだろう。実際にZOZOの株価はピーク時(5000円弱)と比較して、直近では2000円程度まで下げている。
======【引用ここから】======
私は前半で
「事業主と労働者で利益を山分け、損失も山分けで良いのか?」
という疑問を投げかけた。
ZOZOもいつまでも上り調子というわけにはいかないだろう。
時には損失を出す時もあるだろう。
株価も業績も、上がる時もあれば下がる時もある。
そんな時に、
「去年までは時給1000円だったが、去年からは業績が良かったので1300円に上げました。でも今年は業績が悪いから最低賃金スレスレまで下げます。」
と言われて、藤田氏界隈は納得するのだろうか。
しないでしょ?絶対に納得しないでしょ?
「あらかじめ定められた契約内容に基づき1000円払うべきだ!」
って要求するでしょ?
(※ ところで。
ZOZOの株価がピーク時と比べて下がった理由を、
「末端の労働者を重視していないから」
と考える投資家は居るのだろうか?
多分、別の理由だと思うんだけどね。 )
======【引用ここから】======
私はブラック企業ユニオン、首都圏青年ユニオン、プレカリアートユニオン、エキタスなどの労働組合や市民団体と共に、「お年玉企画」といった煙幕に巻かれることなく、企業の利益の源泉を追求し、貧困や格差の原因にメスを入れていきたいと思っている。
======【引用ここまで】======
マルクスという度数の合っていない眼鏡を捨てて、ピントを合わせてから世の中を眺めてみましょう。
煙に巻かれるどころか、そもそもぼやけて前がハッキリ見えてないでしょ?
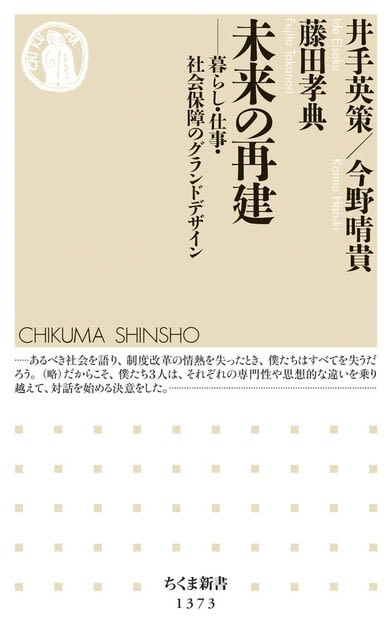
読んでて気分の悪くなる一冊ですが、感想文を近日アップ予定。
(と自分を追い込んでみる)
藤田氏の主張をツイッター上で眺めてきた。
その藤田氏が、ZOZO社長の1億円お年玉イベントでついに不満を爆発させた。
○拝啓、ZOZO前澤友作様「1億円バラマキ、本当に下品です」『藤田孝典』 2019/01/09
個人が私財をどう処分しようとその個人の勝手であり、それを第三者が難癖つけるのはただの嫉妬でしかない。
この嫉妬に満ちた文章の中に、雇用や会社の利益、賃金についての藤田氏の考え方が随所に表れている。この中にある誤りや問題点、気になったところを指摘していこう。
【利益と賃金】
======【引用ここから】======近年、東証に上場する企業、急成長する企業は、派遣労働者、非正規雇用を大量に利用して利益をあげてきた。彼らの富の源泉は、低賃金労働者への労働力搾取に起因している。その成長や利益の背後には、大量の派遣労働者が存在している。
======【引用ここまで】======
汗を流す、一生懸命働く、こうした努力は、それだけでは価値や利益を生じない。
真夏に穴を掘って埋める作業は大変な労力であり、これに従事する人は相当な汗を流すことになるだろう。しかし、ただ穴を掘って埋めても世の中に何の価値ももたらさないし、何ら利益を生じさせない。
労働には適切な方向付けが必要である。労働から利益を上げるために、事業主は、その労働によって何を生み出しどこへ提供するか企画しなければならない。この企画が的外れなものであれば、利益を上げることはできない。
ここで重要なのは、利益は後から生じるもの、ということだ。
商品を開発し、生産し、販売先を確保し、代金を回収して初めて利益が生じるわけだが、数か月で利益が出れば早い方。数年、10年以上かかることもあるだろう。
このため、利益と賃金を連動させて考えると問題が生じる。
【利益は後から生じる】
田舎の例えで恐縮だが、地主が事業主となって「雑木林を開墾して田んぼを作り、米を作って売ろう」
と考えたとする。
作業員を募集する際には、労働時間、条件、内容を考慮して、似たような他の作業と同じ程度かそれ以上の額を支払うことを約束して募集することになる。
伐採や土壌改良に3年かかり、開墾後の春に田植え、夏に草刈り、秋に収穫、そして冬に米が売れて初めて利益になる、としよう。
この時、開墾2年目に作業員が地主に対し
「雇用されて開墾に従事して丸1年が経過したのに、一度も賃金が払われないのはどういうことか」
と苦情を述べた。地主から
「まだ利益が出てないんだから賃金なんて払えるわけないだろ。2年後の収穫を待っておくれ」
と言われて、納得する作業員はいないだろう。みんな辞めてしまう。
利益が出るまでの間であっても、作業員に賃金を支払うことを約束しなければ雇用契約は成立しない。この間の賃金は、地主が予め調達した資金の中から支払われることになる。
雇用契約が成立し、3年の開墾を終えて春の田植えを終えた後に、台風で稲が全滅し、あるいは洪水で開墾地そのものが流されてしまったとしよう。地主には利益どころか莫大な損失が生じる。それでも、地主は作業員に対し、作業してもらった期間に応じて契約に基づく賃金を支払わなければならない。払えなければ破産するしかない。
地主は、様々なリスクを負っている。
災害が起きるかもしれない、
稲が病気になって収穫ができないかもしれない、
逆に豊作で米価格が大暴落するかもしれない、
作付けした米の品種の人気が思ったより低くて高値で売れないかもしれない、
空前のパスタブーム到来で誰も米に見向きしなくなるかもしれない、
等、様々なリスクに晒されている。そうした将来の不確実なリスクの中、地主は作業員に対し雇用期間中の賃金を約束し、予め調達した資金の中から賃金の支払いを続けなければならない。
逆に言えば、契約に基づき賃金が支払われている限り、そこに倫理的な問題は生じない。利益が生じる前に、地主と作業員との間で金額や労働条件について同意しているからだ。また、最低賃金法(=「未熟練労働者切捨法」)に定める以上の金額を払っていれば、法的な問題も生じない。
さて。
4年間契約どおり賃金を払い続けて開墾を終え、作付けを済ませて無事に収穫を迎え、販売した結果、予想より大きな利益が出たとする。
この利益は、地主のものである。
地主がその利益の中から、
「作業員のみんな、今までありがとう!収穫祝いとして一時金を支給します!」
と配るのは、あくまで地主の任意によるものだ。
作業員の側から
「収穫の利益は俺たちのものだ。地主が独り占めにしてずるいなぁ」
と愚痴をこぼすのは勝手だが、外部から
「作業員の主張は当然であり、地主が利益を作業員に分配するのは義務である」
と強制するのであれば、災害や不作、販売不振によるリスクも作業員が分担して負うべきだろう。
作業員は、
「不作で予想利益の半分になったから、当面、賃金も半分ね」
と言われて、果たして納得するであろうか。
「利益が出る前に賃金を払う」という雇用の枠組みそのものが崩壊するのではないか。
「事業主と労働者で利益を山分け、損失も山分け」
という仕組みは、企業内の一体感を高める上で効果的かもしれない。
しかし、多くの労働者はこれを望んでいるのだろうか。
会社が倒産する寸前まで賃金が契約どおり支払われるのが良いか、それとも、会社の利益と損失に比例してその都度賃金が上下するのが良いか。
賃金が契約通り支払われているのに、企業の業績が良い時だけ
「事業主が大きな利益を得るのは不当だ」
と主張するのは、無責任な妬み、やっかみでしかない。
【正社員 対 非正規雇用】
======【引用ここから】======彼らの言う社員や従業員のなかに派遣労働者は含まれていないばかりか、正社員との待遇差別も著しい。
派遣や非正規は好きでやっているのではないか、という意見もあるが、「不本意非正規の状況」(厚生労働省)によれば、正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者(不本意非正規)の割合は、非正規雇用労働者全体の14・3%(平成29年平均)である。相変わらず、不本意非正規の数も多い。
======【引用ここまで】======
日本では、正社員を一旦雇用すると、解雇するのが難しい。
雇用して勤務させてみて、
「この人はうちの会社に全然向いていない」
と気付いても、これを理由にすぐ解雇することはできない。
仮に解雇しても、訴訟になれば、裁判所が
「本当に向いてないのか、研修を受けさせたりして能力向上を試みたか、配置転換で対応できないか」
等と難癖をつけて解雇に待ったをかけてしまう。
これは正社員労組が、企業や世間に対し長く求めてきた主張でもある。
こうした裁判所や労組の動きは、企業側に
「正社員を一度雇うとクビにできないから、採用は控えよう」
と正社員の雇用数を抑制する方向に作用した。
正社員数を抑える一方で、繁忙期と閑散期の人員必要数の調整を非正規雇用や派遣労働者で行う仕組みが出来上がった。
その結果が、
「正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者(不本意非正規)」
の増加である。椅子取りゲームの椅子が中々空かないから、周りの人は早く座りたいのに延々と回り続けることになる。
解雇規制が雇用の流動性を阻害し、ここから正規・非正規の身分格差や年功賃金体系、新卒一括採用といった慣行が成立している。同一労働同一賃金を妨げているのが解雇規制だ。
正社員は、こうした解雇規制や年功賃金といった手厚い身分保障を持っているが、これは非正規雇用の犠牲の上に成り立つものである。
正社員労組や自治労の主催するシンポジウムや講演会でひっぱりだこの藤田氏が、どの面下げて正社員と非正規労働者の格差を語るのだろうか。
もし、藤田氏がこうしたシンポジウムや講演会の中で
「正社員である組合員のみなさんの身分保障は、非正規雇用の方々がいるから可能なんですよ。あなた達への手厚すぎる身分保障が格差の原因です」
と説いて回っているのであれば別だが。
【相対的貧困率は要らない】
======【引用ここから】======日本の相対的貧困率は15・7%(平成27年)と主要先進国の中でも高い。日本は貧困に苦しむ国民が多い国である。なかでも働く労働者の貧困であるワーキングプアは大きな社会問題となっている。
子供の貧困も働く親の所得の低さに原因があり、その背景にはワーキングプア問題がある。特にシングルマザーの貧困は、先進諸国最悪の相対的貧困率を記録するほど深刻であり、女性のひとり親の多くが非正規雇用で働いている。
======【引用ここまで】======
相対的貧困率は、貧困層の多さではなく格差の度合いを示すものだ。
みんなが貧しくなれば相対的貧困率は改善する。みんな貧しくなることによって格差は是正されるが、果たしてこれは良い事だろうか。
また、相対的貧困率は貯蓄の有無を考慮しない数値であるため、高齢化が進めば相対的貧困率も上がる。相対的貧困率は実際の貧困の状況を表さない。
相対的貧困率と貧困の具体的内容とが入り混じっている文章を見かけた時は、相対的貧困率に関する部分を全部飛ばして読んでも全く問題ない。飛ばした方が、具体的にどういう状態にあって貧困に苦しんでいるかがスッキリして分かりやすくなる。
相対的貧困率が高いことを問題視する人は多いが、相対的貧困率が以前と比べて下がった場合にこれを素直に評価する人は少ない。湯浅誠氏くらいじゃなかろうか。
○子どもの貧困率が減った! 何がどう変わったのか 湯浅誠
他の人は、
「相対的貧困率が下がったとは言え、他の指標が~」
等と言って改善を認めない。
それなら、最初から相対的貧困率を貧困の指標として用いなければ良いではないか。
なお、女性のひとり親の多くが非正規雇用で働いている原因も、正社員の身分保障が手厚すぎる点にある。このことについては上述のとおり。
【はぁ、マルクスですか】
======【引用ここから】======同社は、これら低賃金労働者の存在に甘えて、株価の高騰や企業の成長を維持しているにすぎない。どれだけ株価高騰、企業価値の向上は経営陣の手腕だと言おうが、現場の労働者がいなければ生産や流通を担えないし、富は絶対に発生しない。古くはカール・マルクスが19世紀に大著『資本論』において喝破した内容である。
======【引用ここまで】======
マルクスが唱えた内容は、20世紀前半にミーゼスやハイエクが「社会主義経済計算論争」で批判したものであり、この批判のとおりにソ連体制は行き詰まった。マルクスは「亡霊」であり、労働価値説を初めとする誤った言説とともに一刻も早く成仏してもらうのが良い。
労働者がいなければ富は発生しない、それはそうである。
しかし、経営者がいなければ雇用は発生しない。
労働者と経営者を繋ぐものが契約である。
そして、契約において賃金の額を定める最大の要素は、他の企業の類似の労務内容なら幾ら位になっているか、という賃金相場である。
労働者と経営者が任意の契約によって繋がっていて、その契約内容が守られている限り、そこに搾取という概念は生じない。
【個人情報を扱うにしては低すぎる?】
======【引用ここから】======この街宣活動に至った理由は、私の元に派遣労働者から匿名で相談が寄せられたからでもある。相談は業務内容に比例して賃金があまりにも安いというものだ。正社員の賃金や待遇は一定程度担保されているが、派遣労働や非正規の現場は凄惨(せいさん)だというのである。
彼女の訴えによれば、時給は3年間働いても1000円のままであり、責任をもって顧客の配送先である住所や名前など個人情報を扱うにしては低すぎるというものだ。これらの信ぴょう性を確認するための行動だった。
新習志野で多くの派遣労働者と話をすることができた。前澤社長や田端氏は現場の倉庫には足を運んで派遣労働者の声を聞いていないことも理解できたし、匿名の彼女の訴えは真実だとも理解できた。実際に新習志野で話した20歳代前半男性の派遣労働者は「僕の時給は1000円です。個人情報を大量に管理していますし、この賃金では安いと思います。社長が1000億円もかけて月に行くというなら僕らの賃金を上げてもらいたいというのが正直なところです」と語った。
======【引用ここから】======
藤田氏は
「個人情報を扱っているから、時給1000円では安い」
という非正規労働者の声を紹介しているが、どこを読んでもその理由が伝わってこない。
個人情報を扱っていない他の業務は現状維持でも良いが、個人情報を扱う私の賃金は高くしろということなのだろうか。
藤田氏は
「誰にでも出来る仕事の給料は上がらない」
といった主張を
「上から目線で労働者を蔑視する」
ものとして批判している。
では、
「時給1000円は個人情報を扱うにしては低すぎる」
は良いのだろうか。暗に、個人情報を取り扱う業務と比べて、他の業務を上から目線で蔑視していないだろうか。
もし、他の企業で、個人情報を扱う類似の業務が時給1200円の所があれば、ZOZOの非正規雇用を離れて他の会社に行けば良い。離職が企業にとって最も有効な圧力である。そうなれば、雇用の流出を止めるため時給引き上げを検討せざるを得なくなる。
ところで、
======【引用ここから】======
彼の職務内容を聞けば、責任ある正社員が行うべき業務を派遣労働者が低賃金で担っている。
======【引用ここから】======
藤田氏に相談した派遣労働者は、自身が低賃金であることを憤っているようだ。
それって、派遣元企業に相談すべき内容ではなかろうか。
ホームページでZOZOのアルバイト採用を見ると時給1000円となっていたが、派遣元企業はZOZOへ派遣した派遣労働者の賃金を幾らで設定しているのだろうか。
【ここで最初に戻ります】
======【引用ここから】======末端の労働者を重視しない企業であれば、株価にも影響するだろう。実際にZOZOの株価はピーク時(5000円弱)と比較して、直近では2000円程度まで下げている。
======【引用ここから】======
私は前半で
「事業主と労働者で利益を山分け、損失も山分けで良いのか?」
という疑問を投げかけた。
ZOZOもいつまでも上り調子というわけにはいかないだろう。
時には損失を出す時もあるだろう。
株価も業績も、上がる時もあれば下がる時もある。
そんな時に、
「去年までは時給1000円だったが、去年からは業績が良かったので1300円に上げました。でも今年は業績が悪いから最低賃金スレスレまで下げます。」
と言われて、藤田氏界隈は納得するのだろうか。
しないでしょ?絶対に納得しないでしょ?
「あらかじめ定められた契約内容に基づき1000円払うべきだ!」
って要求するでしょ?
(※ ところで。
ZOZOの株価がピーク時と比べて下がった理由を、
「末端の労働者を重視していないから」
と考える投資家は居るのだろうか?
多分、別の理由だと思うんだけどね。 )
======【引用ここから】======
私はブラック企業ユニオン、首都圏青年ユニオン、プレカリアートユニオン、エキタスなどの労働組合や市民団体と共に、「お年玉企画」といった煙幕に巻かれることなく、企業の利益の源泉を追求し、貧困や格差の原因にメスを入れていきたいと思っている。
======【引用ここまで】======
マルクスという度数の合っていない眼鏡を捨てて、ピントを合わせてから世の中を眺めてみましょう。
煙に巻かれるどころか、そもそもぼやけて前がハッキリ見えてないでしょ?
【追記 ~ 次回予告】
いつも藤田氏をネタにしてばかりで何か申し訳なくなってしまったので、買いました。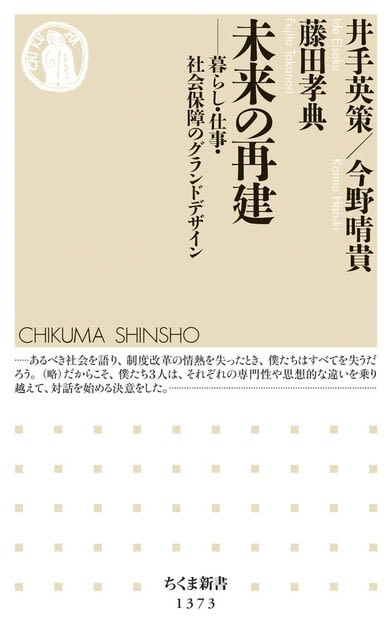
読んでて気分の悪くなる一冊ですが、感想文を近日アップ予定。
(と自分を追い込んでみる)









