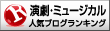文化祭や、コンクール、まだ遠い先だとは思っていませんか?
【もう三ヶ月を割っている!】標準的な文化祭は十月前後。コンクールの予選は十一月の初旬から、中旬にかけて。逆算すれば、もう三ヶ月を切り始めています。正直、創作劇を書いて上演するのは、時期的に遅いです。
【卒業生に聞きました】昨日、昨年コーチをやっていた学校の卒業生に会いました。三年間、連盟で生徒の実行委員をやっていた、いわば高校演劇OBのベテランです。「創作劇て、みんないつごろから書きはじめてんのん?」
【九月に入ってからです】と、彼は答えました。わたしも、だいたいそのくらいだと思っていました。何度かこのブログで言ってきましたが、本を書くのには、標準で三ヶ月かかります。戯曲というのはやっかいなもので、役者の体と声を使って肉体化しないと完成しません。
【例えば】友だちが家にやってきて「どうぞ、あがって」という台詞があったとします。本は、そのあとリビングの場面になり、新しい会話が始まります。小説なら、それでいいんですが、芝居は、靴を脱いで、リビングまで行くという生活(行動)が必要なのです。気を遣うかもしれません、何気ない世間話や、挨拶があるかもしれません。それを表現しなければなりません。芝居のテンポを考えると、場合によっては、暗転にして、リビングで座っているシーンに飛躍させ「うそ、ほんと!?」などと言わせ、それから起こる展開を強調しなければならないかもしれません。
【稽古をしないと分からない】ものなんです。で、稽古の過程で本は書き換えられていきます。そういうことを考えると、三ヶ月はかかります。大阪の創作劇が痩せている(と、思っています)のは、この過程をとばして、生のまま、舞台に乗せるからです。だから、もう創作劇を書くのはいささか遅きに失します。前述の卒業生は、こうも言っていました。私学のA高校は、コンクールが終わったら、すぐに来年の文化祭、コンクールに向けての台本を書き始めるのだそうです。実に一年をかけて芝居を創っています。先輩や顧問の先生の指導が、いつの間にか伝統になったのでしょう。わたしは、これを評価します。
【一般的には】やはり、九月前後になってから、本を書く学校が多いと思います。なんせ大阪は九十%を超える創作率です。くり返します。九月……いいえ、今でも、すでに遅いのです。
【そこで提案です】部室や、ロッカーに眠っている、先輩たちが演った本を読み返しましょう(できたら演出が使っていた台本) 一度上演された本は、一度稽古を通して肉体化され、観客の目に晒され、コンクールでは、審査員や、観客の講評、や評判を受けています。新作を書くよりも、効率が良いと思います。その台本の書き込みや、書き換えを味わいましょう。きっと何か光を放っています。上演されたということは、それだけの価値と重みがあります。
【創作劇】を大切にするということは、そういうことだと思うのです。本は使い捨てではないんです。例えば野球選手を考えてください。一シーズン不調だった選手は、シーズンオフに調整をやります。そして来期を目指します。戯曲にも調整の期間があっていい……あるべきだと思います。わたしは生業が本書きなので、上演される度に、できるだけ上演資料や、審査員、観客の評を集めます。そうやって、多い本だと十回近く書き換えています。そうやって戯曲というのは進化していくものなんです。
【書く手間がはぶける】わけですから(むろん、今に適うように書き換えはしなければなりませんが) その間、他の本を読んだりDVDを観たりして、本を読む目、ドラマを観る目を養ってください。こないだ「時をかける少女」を観ました。仲里依紗主演の最新作です。この「時をかける少女」は筒井康隆が1967年に発表した小説で、その後、テレビや映画でリメイクされてきました。わたしは中学生のときに小説から入りました。その後映像化されたものは全て観ました。去年作られた最新作の出来が一番だと思いました。主演の仲里依紗は、その前のアニメ版の主役である真琴の声をやっていて、いわば同じ役を、アニメと実写で演ったわけで、役の形象としては進歩していたと思いました。このように、本も役者も成長するものなのです。
【新しいものに飛びつかず】先輩が残したものを、もう一度見つめ直してください。それが既成本であれ、創作であれ。そこから、大阪の高校演劇の明日が開けてくると思います。
劇作家 大橋 むつお